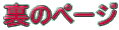
| 第Ⅵ章 治療論と治療技法(総論) |
治療論はともかく
治療技法などを明かしてしまうと、
「お仕事」がとてもやり難くなるなるのでは?
と御心配下さる方もおられるかも知れませんね。
ま、このHPを見て「ハハン、ここは‹共検討›だな」
「これは‹幻聴体験への定則的接近›だ」
などと分かる人は大したもので、
もう殆ど治療なんか必要無いか、
殆ど自力で治療を進めて行ける人で、
いずれにしても治療者はとても楽ができます (^-^)v
 |
第0節 治癒の条件
具体的なお話に入る前に、治療の最も基本的な要素について触れておきましょう。それは裏返して言えば、「治癒の為の条件」でもあります。
0)治療の対象
「治療の対象」って、改まって言うまでもなく「精神疾患」じゃないか、と言われそうですが、『精神科疾患論』でも触れていますように、その「精神疾患」は既に自明のものではありません。
もう一度まとめますと、このサイトを通じての主張は以下のとおりです。
「精神疾患」をこのように捉えることで、次のことが明らかとなります。
- 治療は、自己形成不全/愛着形成不全と外傷性過剰防衛とを共に視野に入れ、両者を適時扱っていく必要がある。
- 「原状況」の再現反復を防止する為の現実的介入(いわゆる環境調整)も、可能であれば行われるべきである。
これで、治療の対象を概ね明らかにすることができました。ここから先は、その方法を論ずることになります。
1)「抱えること」holding(Winnicott,D.W.)または
「包み込むこと」containing(Bion,W.R.)
お馴染みのウィニコットとビオンは、治療的関わり(或いはより広く「治療的配慮」と言った方がよいかも知れません)の本質を、ほぼ同じ意味の「抱えること/包み込むこと」と表現しています(精神分析業界内では英語のまま「ホールディング/コンテイニング」と言われる場合が多いようです.尚、「ほぼ同じ意味」と言うのはウィニコットの側からのお話のようで、ビオン派の側からは、「ホールディング」があくまでも発達促進的な外的~移行空間的環境の働きを指すのに対し、「コンテイニング」の方は統合的でも破壊的でもあり得る内的活動だとされているようです)。
これには次のような幾つかの次元があると同時に、それらの次元が複合して、全体としても大きく「抱えること/包み込むこと」となっていることが望まれます。
① 共に居ることによって存在自体を許容していること(を伝えること)。
最も基本的な態度ですが、これでさえ被迫害不安で一杯の患者さんには「責められている」と受け取られる場合もあります。
② 対話(逆転移を通しての解釈etc.)によって言語的理解が可能であること(を伝えること)。
通常の意味での「治療的関与」の中核とすべき関わりで、言語的理解とその伝達そのものが、患者さんの中の不安や恐怖を共に抱える営みとなります。次節以下で、その中で見出されてきた幾つかの考えや技法を紹介することになります。
③ 乳幼児的(原体験的)心性の突出による様々な行動化acting outに対し、「治療構造」を守ること(を伝えること)。
「治療構造」は精神分析学の文脈では、治療の前提である治療契約(自由連想などのマナー、頻度や時間、場所、料金etc.の取り決め)を指します。それらは自我同士の同盟(治療同盟)に基いており、その中で安全に、退行ないし乳幼児的転移が扱われるわけです。それは、次に述べる「ハードな治療構造」に対して「ソフトな治療構造」と言えるかも知れません。
病態水準が神経症よりも重くなると(つまりパーソナリティ障害や精神病のような自我そのものがしっかりしていない水準になると)「ソフトな治療構造」は治療の前提として治療関係を抱え守るものであるより、治療関係が常にそれを念頭に置き目標とすべき参照枠となるでしょう。
④ 自殺企図や不穏興奮もハードな治療構造(保護室etc.)によって安全を確保し得ること(を伝えること)。
患者さんが自らの身を守ることさえおぼつかない状況では、とりあえず安全を確保しなければなりません。無論「100%安全」ということは何処に居てもあり得ませんが、閉鎖病棟或いは保護室といったケア・ユニットが患者さんを丸ごと抱えることも治療上必要かつ有用です。
⑤ 公的保健福祉機関や種々の社会資源、更には不動産屋さんや民生委員さんなどの民間サーヴィスやご近所の方々の支援があること(を伝えること)。
これらの地域生活を営む上での援助は、それ自体重要な「抱える環境」となります。もしも親御さんとの和解が成立し関係が修復されれば、勿論「家族」も「抱える環境」として重要な支えとなるでしょう。
⑥ 触法行為に対しても司法組織(警察etc.)が対応し得ること(を伝えること)。
精神医療(のみ)では抱え切れない事態もあります。そのような場合には、警察や裁判所(更には刑務所etc.)を含めた社会システム全体で抱えることも必要となるでしょう。勿論ここまで来ると、既に「精神医療」は「抱えるシステム」のほんの「一部」ですが…
註:「抱えること」と「包み込むこと」は、乳幼児と養育者との関係性を祖形としている点でも共通しているのですが、強いて言えば「抱えること」の方が上記①~⑥を初めから視野に入れた概念であり、「包み込むこと」の方は上記②の次元を特に重視した概念であるようです。また、シミントン夫妻Joan&Neville Symingtonによる解説では、「抱えること」が専ら肯定的で発達促進的な働きを指すのに対して、「包み込むこと」の方は統合的でも破壊的でもあり得る、とされています(『ビオン臨床入門』金剛出版,邦訳77頁)。
これらの営みを通じて、人は徐々に「抱えること/包み込むこと」という機能を自らの内に取り入れ、内在化すると考えられます。⇒「こころの発達の健康な場合」
[補足0]往診と搬送(いわゆる精神科ドクターカー)の是非
幻覚妄想状態や家庭内暴力を呈している人物を医療につなげる為に、家族から往診による病院への搬送を求められることがあります。核家族/核分裂家族が普通になり、地域の有機的つながりも薄れている中で、上記のような人物を抱えたご家族の難儀は察するに余りありますが、この「往診と搬送」には考慮すべき幾つかの問題点があります。
①客観的問題性を担保できない。
精神科の強制医療が人権侵害とならない為には、強制医療が許されるだけの客観的問題性を是非とも担保する必要があります。しかし、家族はしばしば当該人物と利害関係の内にあります。病院は当該人物の入院によって収入を得ますから、これまた利害関係の内にあります。故に、「往診と搬送」は、当該人物と利害のからんだ家族と病院スタッフのみから成る密室的状況での不当な「拉致監禁」となりかねない危うさを持っているのです。
無論、現実にはそこまで悪意に満ちた状況を想定するのは行き過ぎかも知れません。しかし、そうでなくても、問題を否認しがちな当該人物から見れば、やはり「拉致監禁」と映ってしまうことになります。そして、その時に「いや、そうではなく、客観的にコレコレの(精神医学的/地域社会的)問題が生じていたでしょう?」と言い難くなるのです。
②病院という空間の外で「力」を行使することが許されるのか。
一般に(正当防衛などの特殊な場合を除いて)、社会的空間での直接的肉体的な「力」の行使は、警察以外には許されていないのではないでしょうか。
③治療への家族の不参加/消極的関与を許容したことになりかねない。
近年、「保護義務者」が「保護者」となり、更にその責任を解除する方向で検討が進んでいるようですが、それでもやはりご家族のサポートは貴重です。
例外が無いとは言いませんが、以上のような点から筆者は「往診と搬送」にはかなりの慎重派です。
2)病原性外傷体験記憶の再処理
これはEMDRが依拠している治療モデルですが、勿論、精神分析の創始者フロイトの治療モデルでもあります。
精神分析は当初、これを素朴な想起に求めていましたが、やがて「今ここで」の治療関係に転移される過去を解釈しワークスルーする、という方向に発展しました。
EMDRは両側性刺激による連想促進効果を頼りに、外傷体験記憶の自発的な再処理への援助を謳っています。(EMDRについてはおまけのページで論じています)
3)主体(主体的機能)の呼び出し/育成
たとえ、「こころの臨床事態」の大半が(拡張された)複雑性PTSDであるとしても、抑圧され忘却されていた病原的な外傷体験記憶の再想起/再構成のみでは恐らく真の「処理」には至りません。それを体験した幼少期の不可能を乗り越えてそれを首尾よく「処理」する為には、それを可能とする大人の機能としての主体の働きが必要です。
EMDRではそれを「認知の編み込み/植え付け」という技法に求めているようです。しかし、辻に拠れば、道理(主語同一性論理)を理解し、それに基く判断を述語同一性論理に基く直接体験的判断に優先させる心的態勢を獲得する為には、(この頁で以下に示しますような)根気のいる作業が必要であり、残念ながらEMDRで想定しているほど事は簡単には進まないようです (^_^;)
[補足1]「自分はどこにいるの?」
主体の呼び出しの最たるものは「自分はどこにいるの?」という呼び掛けです。
通常私達は、目の前に人間存在を認めれば、そこにその人物の「自分(=主体)」も存在するものだ、と思ってしまいます。ですから、このような問い自体全くナンセンスに思われて、敢えて発しようとは思わないものです。
ところが精神科臨床では、多くの場合、そこに「自分(=主体)」は存在しないのです。故に、こちらが「自分はどこにいるの?」と問えば答えに窮してしまう人が、意外に少なくありません。或いは、状況や感想を述べているだけの存在を「自分だ」と主張されるかも知れませんが、勿論そのようなものは「自分(=主体)」と呼ぶに値しません。
このことが見えてくれば(実は筆者にも最近ようやく見えてきたのですが)、この質問を違和感無く発することができるようになります。
これまで(2009.06.20に辻先生から同じお話を再び聴くまで)筆者は、この時に「主体としての自分が無い」ということを確認するだけに終わっていました。ここで終わっていては単なる「精神病理学者」でしかなく、辻先生は更に先を行っておられました。つまり、ここで患者さんを指差しながら「あなたはここに居るではないか、ここに居るのがあなただ!」と語りかけるのです。ここまでやって初めて、臨床家の仕事だと言えるでしょう。
[補足2]「洞察」の行方
精神分析/精神分析的精神療法に於いては、一般に「洞察」insight/Einsichtというものが重視されてきました。これは、それまで無意識的(無自覚的)であった自らの問題を言葉で言い当てることを指しています。ちなみに、「真の洞察」とされるものは「ああ!」という感動を伴うとされてきましたが、それは、その「洞察」がまさにホームでなされていて、アウェイに置かれていないことを表しています。
精神分析/精神分析的精神療法に於いては、このような洞察が得られなければ、本当に治ってはいない、と考える傾向がありました。しかし(薬物療法は当然として)例えば催眠を応用した戦略的精神療法や行動療法等では、洞察よりも「望ましい変化」を実現することに重点が置かれています。そして、うまく行けば「良循環」が生じ、「望ましい変化」は半恒久的なものとなる、というわけです。
筆者はと言えば、実は近頃ますます治療場面に於いて「洞察」を重視しなくなってきています。決して「洞察」そのものを軽視しているのではありません。確かに「言葉」を介した認識は、それがホームに於いて為される時は大変強固な拠り所となります。しかし、それも結果なのであって、直接に求めるものではない、と思うようになったのです。治療者の期待に応えてクライエントが語る「洞察」は無論のこと、そうではなくても「治療/治療関係」というシチュエーションに於いて語られる「洞察」というものは、得てしてアウェイに置かれているものです。
しかしながら、同時に筆者は、「変化」もまた結果であって、直接に求めるものではない、とも思っています。「じゃあ、お前は一体何をするんだ?」と言われるでしょうね。詳細はこのページの以下の記述に任せるとして、ごく簡潔に言ってしまえば、治療者の仕事は患者の内なる事情を「読む」ことであり治療者自らが「洞察すること」だと感じています。
ホールディングやコンテイニングによる新しい人間的な出会いを通じて、それまでの自分を客観的に見る余裕と視座を手に入れること(上記の1と3)と、それを通して過去の病原的体験と自分が抱えてきた「生の困難」との関係を洞察すること(上記の2)は、恐らく治癒の為の十分条件でしょう(それらはしかし、必要条件ではないかも知れません)。
第1節 治療的関わりの基本原則
私達「治療精神医学」的治療者は、対話的な精神療法的アプローチを最も重視し、それを関わりの中心に置くべきだと考えています。それには勿論、現存する薬剤のみで精神病やパーソナリティ障害を本当に治すことはできていない、という現実的事情が在るのですが、それだけではありません。これまでに見えてきた「心を病む」という事情からは、理論的にも薬剤の効用には限界が有るだろう、という認識からでもあります。
これはまた「(脳ではなく)心が病んでいる」と考えた場合の倫理的要請でもあります。本人の「自覚」というチャンネルを通さずに心を一方的に操作することは、マインド・コントロールに他ならないからです。
[身体的アプローチについての補足]
ここで「身体的アプローチ」という言葉で想定していますのは、いわゆる五感を介する種々の治療法です。もちろん何の言語的コミュニケーションも伴わない治療法というものは無いでしょうが、少なくともそれが副次的位置に置かれているような治療法を指しています。
精神と身体が不可分の関係にあることは言うまでもありませんが、身体的次元で影響を及ぼす、という点で「身体的アプローチ」は薬物療法に類似しています。そして、薬物療法やそれに根拠を与えている脳研究と同じく、精神疾患というものを考える、或は患者さんを援助するのに、いわゆる「身体的アプローチ」は(有用ではあるかも知れないが)必須ではない、と筆者は考えています。
0)治療的関わりの構成からの前置き
治療的関わりに、知識としての伝達が容易な部分とそうでない部分とがあることは、臨床家なら誰しもが同意する事柄でしょう。さしあたってここに記す事柄達も、「知識としての伝達が容易な部分」に相当します。
実際の治療は、これらの基本原則を踏まえながらも、臨機応変、ケースバイケースに、しばしば双方の全人格、全存在を懸けて行われます。そのような部分は、一々文字にしていると(不可能ではないにしても)膨大なものになるでしょうし、双方の人格や存在に関わったすぐれて「一期一会」的でユニークな側面なので、そのままでは他の治療者の役には立ち難いでしょう。
1)治療的対話の目的と構造
ギリシャにある、知と光の神アポロンの聖地デルポイΔελφοι, Delphoiの神託所には「汝自身を知れ」γνῶθι σεαυτόν(gnōthi seauton)と書かれていると言います。有名なオイディプス(エディプス)Oedipusの物語では、アポロン神の神託(「父を殺し母と交わる」)を自らの知恵で回避できると考えたオイディプスが、自らの出自(正体)を知らなかった為に、結局はアポロン神の神託どおりの事をしてしまいます。そして、遅ればせながら自らの真実の探求に乗り出した彼はついにそれを見出すのですが、最後はその衝撃から、真実を見抜くことができなかった自らの眼をピンで貫く、というお話です。
治療的対話の目的は、この「自分自身を知ること」に尽きます。
さて、「自分自身を知る」為には、オイディプス王のように眼を潰す必要はありませんが、眼差しを外にではなく内に向ける必要があります。この「眼差しを内に向ける」とは、「直接具体的に眼には見えない自分自身と向き合う/自分の心の真実と出会う」ということに他なりません。
赤ん坊の心性(原体験心性)にはこの「直接具体的に眼には見えない自分自身と向き合う」という芸当はできません。それは、嫌なこと辛いことを忌避し排除しようとする原体験心性に逆らって、時間をかけて少しずつ醸成されてくる能力です。それには当然、周囲の大人(養育者)のサポートが必要です(⇒親子関係の健康な場合)。このサポートが乏しいと、受け止められなかった嫌なこと辛いことは、「見てはいけない」「触れてはいけない」として心の中で様々な形で聖域化(聖なる場所は忌避される場所でもあります)されます。当然、そのような部分があると「自分自身と向き合い、自分自身を知ること」が妨げられます。
この事態を打開する為には、自分が何を忌避しようとしているのか、自分自身に問いかけてみるしかありません。つまり、自分自身との対話が必要なのです。そして、治療的対話はこの内的対話を実現し促進する為のものです。つまるところ治療者は、直接には目に見えないその人の「心の在り様を映し出す鏡」とならねばならないのです。
余談ですが、精神分析の創始者フロイトFreud,S.はこの物語に大いに感銘を受けたようで、子供の「母を愛し父を憎む気持ち」をエディプス・コンプレクスと命名しています。
この物語に於いてオイディプスは、当初よりアポロンの神意に対抗し、また女怪スピンクスSphinxの謎に挑んで見事勝利するなど、神から自立した人間、言わば近代的人間です。この彼の在り方がヒュブリス(人間の驕り)とされてアポロン神の罰を受けるのですが、ソポクレスSophoklesの手になる悲劇『オイディプス王』では、オイディプスは英雄的努力をもって自らの真実を探求して行きます。この営みをフロイトはきっと、精神分析が目指す、近代的自我による心の真実の探求と重ね合わせていたのでしょう。
ちなみに、この悲劇の発端は、オイディプスの父ライオスが若い頃に身を寄せていた恩人の息子の美少年に対し、今日ならストーカー殺人と言うべき所業に及んだことにあります(同性愛自体は古代ギリシャに於いてタブーではなかったようですが、恩人の息子を片想いの末、誘拐して殺してしまったのですから大罪です)。少年は死に際にライオスを呪って、ライオスが将来生まれる自分の子に殺されるよう大神ゼウスに祈った、とされています。どうもこのライオス王は未熟な自己愛の人であったようで(勿論神話中の人物なのですが)、妻イオカステとの生活でも、今日で言うDV(家庭内暴力domestic violence)亭主に近かったようです。そうするとこのオイディプスの物語は、「機能不全家庭に育った被虐待児」つまりAC(アダルト・チャイルド)の物語としても読める、というのが比較的最近の読解のようです(例えばアリス・ミラーMiller,A.『禁じられた知』1981)。
「地上に、声(あるいは形)は一つなのに、2本足でも4本足でも3本足でもあるものがいて、地上と空中と海中の全ての生物の中でただ一つだけ性質(ピュシス)を変える、しかも、もっとも多くの足で歩く時に足の速さが最も劣るものは何か」という謎掛けに対しての「それは人間だ、何故ならば、嬰児は4本足で、成長すると2本足で、老いると衰弱の為に杖を使い3本足であるから」というオイディプスの答えは、全く具象的な目に見える足の数の変化のみに着目した極めて不完全なものです。この時点での彼は、目に見える具体的なものにしか注意が向いていなかったのです。
それでもスピンクスはそれを正解だと認めて驚愕し、崖から身を投げて死んだとされています。何故でしょう。一説によると、答える際にオイディプスは自分自身を指さしていたとされます(そのような絵柄の美術作品が見つかっているそうです)。だとすれば、彼は言葉以上にその態度でもって(無意識的/無自覚的に)不完全な答えを補っていたのかも知れません。何故なら、彼こそは、呪われた棄て児という性質(ピュシス)[彼は生後すぐに、「自分の子によって命を失うであろう」というアポロン神の神託を恐れた父ライオス王によって両足を金のピンで刺し貫かれた上、キタイロンの山中に遺棄されていました]からコリントスの王子、後にはテーバイの王となって最も高貴な性質(ピュシス)を示す一方で、「もし故郷に帰れば、父を殺し母と交わることになろう」という神託を恐れるあまりに却って事態を見誤り、古代ギリシャに於いても獣並みの性質(ピュシス)[獣は勿論4本足です]と見做された所業に至り、盲て杖をつき追放される運命にあったからです。
(以上、吉田敦彦著『オイディプスの謎』1995年青土社刊を参照しました。)
謎を解けなかった旅人を喰ったとされる女怪スピンクスは、恐ろしい「呑み込む母親」を象徴していると考えられます。オイディプスの答えが「それは私だ!」という、まさに「自分という存在への自覚」を表していたとすれば、スピンクスがそれを聞いて退散した、というこの物語は、「人は自覚を有することではじめて原初的な母親イマーゴ(子供が抱く母親像)の支配から自由になることができる」という寓話だとも言えるでしょう。
それにしても、自らの科学的知恵によって全てを支配することができると考えている近代的人間の末裔である我々の現在の在り様が、オイディプスのそれと同様の驕り(ヒュブリス)として手酷く裁かれなければよいのですが…
2)内容的アプローチと構造的アプローチ
精神病水準やパーソナリティ障害水準の問題への精神療法的アプローチは、一般にかなり難しいものとされています。その理由の大半は、それが内容よりも構造を扱わねばならない、ということに在ると思われます。この「構造を扱う」というのが実に難しいのです。
何故「構造を扱わねばならない」のでしょうか?それは、病態が重くなればなるほど、「健康な自我/主体としての自分」が機能していないからです。その状態のままでいくら「洞察的な」内容が話し合われたとしても、患者さんの心の内に引き取られて定着すること無く、全ては流れ去ってしまいます。これは、ウィニコットWinnicott,D.W.が「分析することができるのは本当の自己だけである。偽りの自己を分析していっても、つまり内在化された環境に過ぎないものを分析していっても、それは失望に終わるだけであろう。」と述べていることに相当すると思われます。そうならせず、話し合いを意義有るものとする為には、兎にも角にも「健康な自我/主体としての自分」を呼び覚まさねばなりません。
ではどのようにすればそれは可能でしょうか?それには(治療関係の内外を問わず)様々な出来事の中で患者さんの「自我/自分」がどう機能しているのか(いないのか)、「原体験心性」にどのように支配されているのかを注意深く観察し、チャンスが有ればできるだけそれを映し出すようにすることが中心となります。そしてこの作業は、「自我/自分」と「原体験心性」そして「心の鎧」の持つ「構造的特性」に着目しなければ不可能なのです。
そうは言っても、治療セッションの最初は、患者さんのお話を傾聴するところから入ることが普通ですので、結果的に主に内容を扱うことになる傾向があります。しかし、治療関係が十分に熟してきますと(つまり、内容の多くがお馴染みのものになってきますと)、語られた個々の内容よりも、関係の中で生じている構造的パターンの方が主題となってくるものです。⇒治療の起承転結
3)共感・共検討・共決断
これらは、辻が自らの実践と他の様々な(うまくいっている)治療技法を総合し、治療的関与のエッセンスとして抽出した要素です。
①共感:これは「あらゆる治療的関わりを肯定的関係性の上に載せる」ということの為に必要な要素で、この時に共感されるべきなのは、病んでいることそのものに於いて働いている共人間的事情です。
これは原体験心性の融合合一的で直接的な性質に基づいていながら、同時に弁別的理解の裏づけ(間接化)を必要としています。もしもこの弁別的理解の裏づけ(間接化)を欠けば、「共感」はただの独り善がりの思い入れに堕してしまいます。
②共検討:これは「見るべきものを共によく見、見分けるべきものを共に見分けて行く」という営みを指しています。
③共決断:これは治療に於ける力のモーメントです。当初は「対決」とされていて、患者さんが「手に入れるべき決断」を前に逡巡している時、治療者が「背中を押す」といったニュアンスがあり、実際に力のこもった喧嘩腰(?)の遣り取りも目撃されました。しかし、最近では「決断することを独りにさせない」と修正され、例えば「そこが難しいねぇ」と明確化しながら寄り添う(或いは、決断に付き合う)というニュアンスで、より穏やかなものになった印象です。
辻は、「およそうまくいっている治療であれば(行動療法であろうと来談者中心療法であろうと精神分析療法であろうと)、必ずこれら三要素を含んでいる」と述べています。
[補足]共感(感情移入)の不可能性と可能性
自己心理学では何よりも「共感」empathy/Einfühlung(感情移入)による内側からの理解が重視されています。治療者のそうした努力の中でクライエントは自己対象転移を発展させ、それを治療者が解釈することを含めてクライエントからは自己支持的な「自己対象」と体験され、そのこと自体が(解釈された内容よりも)治療的に働く、と考えられているようです。
これはなかなか分かり易い(という意味で、優れた)定式化ですが、少し注釈が必要です。「共感」が単なる思い入れ(感情移入Einfühlung)であってはならないのです。
感情移入Einfühlung(思い入れ)に関しては、かねてよりその原理的不可能性が指摘されています。他者は不可知である(知り得ない)からこそ「他者」だからです。
しかし、ぶつかってみて、その反応を観察することはできます。そしてそれが、不可能を多少なりとも可能にします。これは、コミュニケーションの原初的な姿だとも言えますが、普段は共同体的な「一般妥当性」に支えられた「理解し易さ」によって覆われています。
治療の為の対話(コミュニケーション)に於いては、常にこの不可知と可知(=理解)のせめぎ合う次元が問題となります。この次元に最初に科学の目を持って踏み込んだのは、精神分析の創始者フロイトですが、辻は「原体験領域」を明確化することで、この次元の更に下層に到達し、その自他未分化な構造に親しむことで「他者」理解への道を大きく切り拓いています。
4)「直接話法的関与」と「間接話法的関与」
―「主体/主語」を呼び出す「よかった体験」と「わかった体験」―
筆者の理解が正しければ、治療精神医学で「間接話法的」と言われている介入は、「それは~」と解釈などを解説風に示すことを指しており、それに対して「直接話法的」と言われている介入は、理解すべき事を一つ一つのステップに分解し、遣り取りを通して一つの解釈が出来上がって行くような(但し、途中で敢えて止めておくこともあります)関わりを指しています。例を挙げてみましょう。
例えばここに、「周囲の人が自分のことをどう見ているか気になる」と訴える人がいるとします。「間接話法的関与」では「それは、あなた自身が自分のことを‹これでよい›と思えていないからではないですか?」などとなるでしょう。これで「そうですね」とすぐに本当に理解できる人は、十分な理解力/洞察力を持っておられると言えます。
一般に「間接話法的関与」が有効なのは、それを受け取ることのできる自我が存在している(機能している)場合です。そのような自我が十分に造られていない(機能していない)水準の病態では「直接話法的関与」によって、まず事態を見る「主体/主語」=自我を呼び出すことが必要となるのです。
「直接話法的関与」ですと、例えば「気になっているのは誰ですか?」或いは「あなたは(ご自分の事をどう思っておられるんですか)?」から入ることになります。そして「気にしているのは私です」という答えが得られ、自分に対する否定的な思いが語られれば(そうでないことはまず無い筈ですが)「そうすると、誰よりもまずあなたが自分のことを気にしていることになりませんか(なりますね)」といった流れになるでしょう。そして「周囲の人もあなたに対してそのように(否定的に)思っていると思っておられますね」「もしかするとそうかも知れません。確かにその可能性は無いとは言えません。周囲の人の思いや考えは直接に知ることはできませんから」「ところで、周囲の人の思いや考えはそのようにはっきりしないのですが、あなたがご自分に対して否定的な評価を下しておられることは、はっきりしていますね」「そうすると、そのご自分の思いを‹周囲の人が…›と周囲の人に置き換えている可能性はないか?と言われたらどう思われますか?」と、原体験心性の「述語主導性」に基く投影の機制について理解を促すことになるかも知れません。
或いは「気になるとダメですか?」と、投影よりも原体験心性の「ネガティヴ即排除」を扱うこともあるでしょう。
勿論治療者は努めて、それを理解できればクライエントが精神的苦境から抜け出す助けとなるであろう事柄を提示するのですが、実は、これらの「直接話法的関与」で真に重要なのは、治療者が提示しようとする事柄をクライエントが理解することではなく、理解できない時にその「理解できない(わからない)!」という戸惑いを伴った直接的体験を「そうなんですね」と共感的に理解することなのです。この共感的理解によって、直接体験の水準でクライエントは「よかった!(自分が理解され受容された)」という体験(これを「よかった体験」と呼んでおきましょう)をすることができます。
この「よかった体験」の積み重ねこそが、否定的原体験を肯定的原体験へと変容させ、少しずつではありますが道理を理解する「ゆとり」をもたらします。そして(うまく行けば)やがて、治療者が事ある毎に提示していた道理を理解できる瞬間が訪れます。この時の「わかった!」という体験(「わかった体験」)もまた極めて重要で、事態を間接化して認識する力、即ち主体の働きの端緒となるものです。
[補足]アドヴァイス(助言)について
治療場面で治療者はしばしばアドヴァイスを期待されます。しかし、アドヴァイスは一般に無効です。相手が子供であれば、アドヴァイスが有意義な場合も少なくないでしょうが、思春期以降の若者~大人の場合には、アドヴァイスで事態が好転することはあまり無いのです。何故でしょうか。
実は、「どうすれば良いのか」を多くの人は既に知っているのです。知っていてできていないのですから、同じようなことを他人が言ったからといって、できるようになる可能性は低いわけです。
知っている、と言ってもそれを自覚しているとは限りません。むしろ、本人は「知らない/分からない」と思ってます。しかし、実は知っているのです。その証拠に、アドヴァイスを試みると大抵、「そんなことは分かってる!」と反発されます。
逆に、反発されないと、それはそれで要注意です。彼/彼女が単に聞き流しているのならまだしも、逆にそれを没主体的に鵜呑みにしているかも知れません。そして、鵜呑みにしてそれがアドヴァイスどおりにできるのなら結構なのですが、多くの場合、実行する主体がそれほどにしっかりしていないのですから、事態は一向に変わりません。ですから、事態が変わらないのは自分のせいなのに、そう考える「心のホーム」ができてないので、アドヴァイスした人のせいにされてしまいます(責任のアウェイ化)。
それでは、どうして彼/彼女はアドヴァイスを求めるのでしょう?
それには、いくつかの場合が考えられます。
①自分の責任でものを考える、という姿勢が十分でない。
②今の自分を受け容れられない。その為に、代わりに受け容れて欲しい。
③実行への決断がつかない。決断から逃れないように追い詰めて欲しい。
他にもあるかも知れません。
いずれにせよ、治療者は、相手が何を求めているのかを読み取って、読み取ったことを相手に伝えるしかないのです。
5)「移行対象」transitional objectと「潜在的可能性空間」potential space
ウィニコットWinnicott,D.W.は、子供の発達に於ける重要な要素として、外界の物体(毛布やぬいぐるみなど)が子供の自由になることで自己の一部とも見做されている現象を「移行現象」transitional phenomenaと呼び、その対象を「移行対象」transitional objectと呼んでいます。そして、そのような営みが母親との口愛期的(原体験的)融合合一的在り方と母子の分離した在り方とを仲介し、後に「遊び」や「芸術」といった領野へと発展して行くと考えました。そして、そのような営みの舞台となる、乳児と母親の間、内界と外界の間、空想と現実の間の潜在的可能性を内蔵した空間を「潜在的可能性空間」potential spaceと呼びました。
先述のレンプの用語を使えば、「副現実」と「主現実」の間の領域がこの「可能性空間」だということになります)。
マイクル・バリントBalint,M.は「創造的領域」を「一者関係」と表現しましたが、「移行対象」を巡るウィニコットのこの議論は、バリントの指摘した「創造的領域/一者関係」の内実をより詳細化したとも言えます。
また、フロイトFreud,S.は『快感原則の彼岸』という些(いささ)か思弁的ながらとても示唆に富む論文に於いて、外出する母親に置いて行かれた子供(フロイトの孫)が、糸巻き車をベッドの向こうに投げて見えなくする遊びを繰り返しながら「オーFort(いない)/ダーDa(いた)」と声を上げていることを観察し、この遊びの意味を考察しています。これには様々な解釈が可能ですが、フロイトはこれを[自ら能動的に「不在」を創り出し「名指すこと」による「(母親の)不在」の克服]と捉えたようです。この時、子供が自由に扱うことができた糸巻き車もまた移行対象の一つであると言えるでしょう。
これらの指摘に共通するのは、移行対象/移行現象、可能性空間を心の健康な発達にとって重要なものであると見ていることです。この事を臨床場面に移しかえると、治療関係にも移行対象/移行現象、可能性空間が必要だ、ということになるでしょう。
例えばこのHPの掲示板も、筆者のクライエントの方々にはそのように使ってもらえれば、という思いもありました。別にそれに拘ってはいませんが… |

第2節 「起承転結」:治療の通時的理解(つまり治療の流れ)
―「馴染むこと」と「相互内在化」―
治療にも「起承転結」があるようです。
起:臨床の場での「出会い」です。この段階では治療者は、クライエントの主訴の理解とそれがもたらされている背景の解明とを中心に据えて、情報収集的にインタヴューを進めることになります。
多くの場合、「馴染み」の無い者同士が出会います。懐かしいSF映画の題名じゃないですが「未知との遭遇」ですので、不安や期待などの感情と共に、既に双方の様々な思惑(先入見)や空想が活性化しています。
従って「上手な出会い方」というものには、
①できるだけ自分の先入見から自由になる。
②相手側の先入見を同定し、明示してみる。
③その上で、人間対人間の出会いを果たす。
といった事柄が含まれます。
[補足1]治療契約と治療同盟(或いは「治療意欲」の問題)
治療契約や治療同盟、そしてそこに当然期待される治療意欲は一般に、医療行為を開始する上で前提とされる営為です。しかし、身体疾患の場合でも、治療がお手軽なものではない場合に、しばしば治療意欲が問題となります。
精神疾患の場合には、意欲の主体そのものが脆弱な為に、治療意欲の問題は一層デリケートな扱いを要します。
まず、精神病圏の問題の場合、当人が初めから十分な治療意欲を持ち得ていることは極めて稀なことでしょう。通常当人は、原心性的な無問題化の傾向と「精神病=脱落」の意識によって「自分には何も問題が無い」と思いたい、問題があったとしても「既に無くなっている」と思いたいわけです。
しかし、むしろ治療意欲が問題とされるのは、精神病圏の場合ではなく、いわゆるパーソナリティ障碍圏の場合のようです。何故でしょう?
一つには、精神病圏の場合、幻覚や妄想といったいわゆる陽性症状にしても、無為自閉といったいわゆる陰性症状にしても、当事者自らが「治療すべき症状」と認めなくても、周りの人達が(つまり社会的に)「治療すべき症状」と規定してしまうので、「治療目標」がぼやけない、ということがあるでしょう。
また一つには、パーソナリティ障碍圏の彼ら/彼女らが精神病圏の人達と違い、様々な事を要求してきたりして一見とてもしっかりしているように見えるからかも知れません。「そんなにしっかりしているのであれば当然理性的な判断に従ってきちんと治療意欲を持つべきだ、それを十分に持たないのは彼ら/彼女らの怠慢だ」というわけです。
パーソナリティ障碍の治療のところにも書きましたように、筆者は、少なくともご本人に治そうという意思が存在することが、治療の条件だと思っています。しかし、そこにより確かな「意志」を求めるのは、医療者側の不安に基く逆転移(の行動化)だと考えています。
精神病圏の場合は言うに及ばず、パーソナリティ障碍圏の場合に於いても、治療契約や治療同盟は治療の確かな前提であると言うよりは、その都度確かさを高めて行くべき治療指標の一つであると言えるでしょう。
[補足2]とりあえずの薬物投与
患者さん(クライエント)は一般に、一刻も早い苦痛の除去を求めて来られています。しかしながら、こころの問題にそのようなインスタントな解決は殆ど不可能です。しかし、抗不安薬や抗精神病薬、抗鬱薬や睡眠導入剤は、当面の不安や幻覚妄想、抑鬱や不眠を改善してくれる可能性があります。
故に、当面の困難を少しでも和らげる為に、特に治療の最初の段階では、上述のような薬剤も役に立つかも知れないことを伝えてみます。無論この時にも、薬に対して過度な期待が寄せられないよう注意する必要がありますが、もしも服薬によって多少とも症状が軽減し(たと感じ)、治療を続ける意欲と時間的余裕が得られれば、それは治療にとってとても有益なことでしょう。
承:ある程度相手に巻き込まれながら関係が進んで行きます。この「巻き込まれながら」というのは、クライエントが持ち込む原体験的幻想をある程度許容しながら、という意味ですが、精神分析で言う「転移」transferenceの発展を促す、という意味で言っているのではありません。「転移」は(理想的には)あくまでもクライエントの精神内界での出来事ですが(クライエントの幻想に巻き込まれることで治療者の側に生ずる思いを精神分析では「逆転移」counter-transferenceと呼びます)、「幻想を許容する」というのは実際の治療関係がその幻想に幾分支配されるのを許す、結果的にクライエントの持ち込む幻想に少しつき合ってしまう(厳密に言えば、クライエントの持ち込む幻想に合わせて治療者が行動化してしまう)という意味です。そのような意味での「幻想を許容すること」(治療者が逆転移から行動化してしまうこと)は精神分析的精神療法では推奨されていませんし、許容し過ぎると確かに治療にはなりません。しかし、いくら避けようとしても、このような事態は常に既に幾らかは起こってしまうものだと思います(このような意味合いを込めてか、最近「エナクトメント(実演すること)」enactmentといった概念も提出されているようです/“enactment”の辞書的意味はこちら)。
[補足3]「固い椅子」と「柔らかな椅子」
皆さんは、石のように固い椅子とふかふかのクッションの効いた柔らかな椅子とでは、どちらに座りたいと思われるでしょうか?
「固い椅子」は頑丈で壊れ難いですが、誰もすすんで座りたがらないでしょう。「柔らかい椅子」だと、体が深く沈み込んで楽ちんですが、うまく立ち上がれないかも知れません。また、棘のある人や鋏を持っている人にズタズタにされてしまうかも知れません。
クライエントの幻想に全く巻き込まれない治療者は「固い椅子」です。容易に巻き込まれてしまう治療者は「柔らかな椅子」です。なかなか難しいことではありますが、状況によって硬軟を使い分けながら、固過ぎず柔らか過ぎず、というのが「理想の治療者」なのでしょう。
そのような関わりを続ける中でお互いの事が少しずつ分かってはきますが、まだまだ手探りの状態が続きます。これは、メラニィ・クライン流に言えばPs(paranoid-schizoid position 妄想分裂態勢)的な部分対象関係水準の交流で、私達の言葉で言えば、述語同一性に基く様々な比較同定が活発に遂行される段階です。
この時、同時進行的に、より感覚的な水準で、お互いの内に徐々に「馴染み」の感覚が生じてきます(1~2週に1回の診察/面接では、この「馴染み」の感覚がはっきりしてくるのに、筆者の印象では半年~1年程度かかってしまうことが多いようです)。この感覚は言うまでもなく原体験心性に基いています。
この段階で、治療者側で徐々に「何がクライエントの問題だったのか」が却って分からなくなってくる、ということが起こりがちのようです。裏返して言えば、しばしば原点に意識的に立ち帰り、治療者の中で、或いは二人の間で、元の主訴(最初に問題となっていた事)を確認することも必要となります。
[転移性治癒]
この時期に、クライエントの症状が意外なほどに軽快し、周りの目からもクライエントの様子がえらく落ち着いて見えるということがしばしばあります。しかし、この段階でのそれは、クライエントの幻想が部分的にであれ治療者に受容(或いは共有)されて、脱落意識や孤立無援の恐怖が和(やわ)らげられたこと等によるもので、まだ「自我の成長」という意味での本当の改善ではありません。(治療者への陽性転移[治療者を理想化し慕う気持ち]とそれに対応した治療者の支持的関与による改善は、特に「転移性治癒」(註)と呼ばれています。)
(註)ポジティヴばかりのパターン:転移性治癒の深層/真相
クライエントが(しばしば無意識的にですが)治療者の期待に合わせ、治療者を失望させまいとしてポジティヴな面のみを見せ、治療者も無自覚的に治療のネガティヴな面を否認しているパターンです。それで一見良くなったかのように見えますので、「転移性治癒」とも呼ばれます。
ここには、親を治療しようとする子供の性向が持ち込まれています。クライエントは、自身の養育者にしようとしたのと同様に、治療者を癒そうとしているのです。
このように、現在の治療関係の中に過去の(主に養育者との)人間関係が持ち込まれることを一般に「転移(transference)」と言います(⇒『転移と逆転移』)。
治療者は通常は少し経験を積めばこのパターンに気づくようになるものですが、特に患者さんが知り合いであったり、知り合いの紹介の方であったりすると、治療者の順調希求(「うまくいって欲しい」という気持ち)が強まり過ぎて、このパターンに気づきにくくなるようです。
治療関係の中でこのパターンをうまく扱えなかった場合でも、このパターンを長く続けることは困難ですので、早晩変化します。その変化(悪化)が治療関係の中で起これば、それまでの「改善」が実はこのパターンだった、ということに気づかされて修復して行くこともできるでしょう。
変化が治療関係の外で密かに起こっている場合もあります。その場合には、行動化(acting out)として自傷などの衝動的行動が再燃していたりします。
もっと不幸な場合、治療は中断します。そして、時には最悪の結果に終わることもあります。
[治療的退行と破壊的退行]
時に見られるもう一つのパターンに、いわゆる「退行regression(幼児返り)」という現象があります。典型的には「甘え」(乳幼児的依存)が目立つようになり、一人にされることを恐れ、スキンシップを求めます。これが、周囲の関わる人々(特に養育者)に対応可能な様態に限局されている場合には、新たな親密体験から信頼関係、そして成熟した依存へと向かう、とても建設的なものと成り得ます(「良性退行/治療的退行」)。
しかし、このような「退行regression(幼児返り)」が、関わる人々の許容限度を超えて進む場合もあります。そのような場合は、クライエントの要求は際限無く拡大するという様相を呈し、それらを叶える為には手段を選ばない、或いは現実から遊離した混乱状態に陥る、といったことにさえなります(「悪性退行/破壊的退行」)。
退行が良性のものに留まるか悪性のものに進展するかは、無論そのクライエントが負っている心の傷の性質などにもよりますが、次に生ずる「転」の契機に於ける治療者及び治療環境の対応の如何にも大きく依存しています。
(註)厳密に言えば、「退行」というのは私達自身もしばしば経験する実にありふれた現象です。それをここで大仰に取り上げたのは、単に治療のこの辺りで目立つことが多い、という以上のものではありません。精神科臨床に於いては「常に既に生じている」とも言えるでしょう。
転:何らかの行き詰まりを契機に、変化が訪れます。この「行き詰まり」というのは、とりもなおさず、クライエント側からの原体験的幻想を治療者が幾分かは許容せざるを得なかったことから生じてきます。その為に共謀的に否認されていた現実が、やがては逃れようもなく迫ってくる局面が生じます。ここで一旦は治療関係は行き詰まるのですが、それはクライエントの維持して来た原体験的幻想が崩れる時であり、危機であると同時に、脱皮/再生への好機でもあります。クライン流に言えばPs⇔Dの(つまり妄想分裂態勢と抑鬱態勢の)激しいせめぎあいの段階で、私達の言葉で言えば、述語同一性から主語同一性への解体構築の段階です。治療的にとても重要な局面なのです。
当然の事ながら、周りの目には一旦安定し「よくなっている」と見えていたクライエントの状態が、ここに来て再び不安定となり、様々な症状や行動化(危ない事などをすること)が再び活発となります。そしてクライエントは、様々な形で治療から離脱しようとします。実際に治療が中断することも稀ではないでしょう。うまく行けば、治療関係に訪れたこのような危機を通してお互いの理解がより深まります。
この段階を首尾よく乗り切る為には、クライエントの側に治療者と治療関係への「馴染み」の感覚が十分に成立していることと、治療者の方が半歩でも先に、クライエントの在り方と関係の構造の全貌的理解を得ることが望ましいようです。
事例によって、例えば急性精神病状態で初めから入院を要した場合などは、ここまでの諸段階が急速に展開され、2~3ヶ月の入院治療で一定程度達成されることも多いように思われます。それは入院治療の大きな利点の一つだと言えるでしょう。
このような事を何度か繰り返す中で、更に相互の理解と馴染みの感覚は深まり確かなものとなって行きます。そしてどこかの時点で、お互いにどんな事があっても基本的には「想定内」だと思えるようになってきます。お互いに相手がどのような人間か、直感的に分かっているようになります。これは、お互いに相手の存在を「全体対象」whole objectとして自らの内に内在化できたことを意味している、と筆者は思っています。双方が相手の全体像を自分の内界に確立したという意味で、これは相互内在化であり、主語同一性に基いた全体対象関係の達成でもありましょう。
ところで、「相手の全てが分かる」ということは、現実には勿論のこと、論理的にもあり得ません。これは、あくまでも「この二人の関係に於いて」という厳しい限定つきのお話です。つまり、「この治療関係」という特定の文脈が存在するのです。例えばそのような間柄の人物が、別の人間関係の中では全く違う顔(こちらには馴染みの無い側面)を見せる、といったこともあり得ます。そういう点では、「自我」や「パーソナリティ」は決して「関係」に先行して存在する実体ではなく、「関係」こそが常に先行して存在し、「自我」や「パーソナリティ」はその「関係」の中でこそ実体化すると言えましょう。
そうするとこれは、より精確には「治療関係が葛藤を内包できるようになる」と言うべきかも知れません。そうして、その時の治療者・患者双方の主観的体験が「相手がどのような人間か、直感的に分かっている」という感覚なのだろうと思われます。
[補足4]私的現実と公的現実の葛藤
この段階でのドラマはまた、クライエントの「物語」が治療関係の中で推敲され共有されること、とも言えるでしょう。
当初、クライエントの語りは妄想や幻想、つまり自分だけの思い込みであったり独り善がりであったりします。それがこの段階までの間に、広く共有されている現実(公的現実)と徐々に照合されて来ているのですが、多くの場合、尚「私的現実」の「私的」という性質は否認されています。それがいよいよ正面から取り扱われ、公的現実の優位性が顕わになってくるのです。
ここでの治療者のスタンスとして、おおよそ三つのパターンを挙げることができます。
①公的現実の代弁者となって、クライエントに公的現実の何たるかを告げ知らせ、説得する。
②クライエントの私的現実と公的現実との鬩ぎ合いを、相撲の行司のようにけしかけながら至近距離で見守る。
③もっと距離を取って、クライエントの私的現実(幻想)が公的現実の前にあえなく崩れ去るまで、じっと粘り強く待つ。
この中で、①は治療者自身が公的現実を踏み外していなければ、必ずしも間違いとは言えないでしょうが、治療者の中立性という点で少々問題があるでしょう。しかし、現実の臨床に於いては、ただ「治療者が未熟である」ということではなく、クライエントの頑なな姿勢を治療的に打ち破る唯一有効な「直接対決的」方法として、採用せざるを得ないこともあります。
[補足5]最適なコミュニケーション手段としての行動化?
当然の事ですが、病理が重ければ重いほど、心的外傷が深ければ深いほど、その治療にはより完全な共感的理解、より徹底した相互内在化を必要とすることでしょう。例えば、何度も死ぬような目に遭ったクライエントに対しては、治療者の心もまた「死ぬような目」に開かれていなくてはならないでしょう。そうでなければ十分な共感的理解や十分な相互内在化は生じ難い筈です。
しかし、現実には治療者の心がそこまで「死ぬような目」に開かれているということは、よくあることではないでしょう。そして、恐らく(幸いにも?)そんな治療者の共感不足に対して、しばしばクライエントは、ひどく攻撃的になったり、規律違反等の問題行動や自殺企図といった激しい行動化で応じます。
このような行動化は治療者をはじめ周囲の関係者を大変に困惑させるものですから、一般にとかくネガティヴなものとして捉えられてきました。しかし、実にそのお蔭で治療者は(それでも何倍かに薄められたものではあるでしょうが)「死ぬような目」を擬似体験できるわけです(この間の事情をクライン派精神分析では「クライエントが受け止めかねている自分の内なる感情を、行動化を通して治療者の中に投げ入れる」projective identificationと表現していますが…)。
このように考えますと、厄介な行動化も実に合理的なコミュニケーション手段のように思えてきますから不思議です (^-^;)
ここを何とか合理的枠組みの中で乗り切り、治療関係を維持することができれば、治療は一つの山を越えたことになります。このような山場は実は何度も訪れます。それらを繰り返す中で治療が真に進展して行くことを精神分析では「ワークスルー」working through/Durcharbeitungつまり「やりとおすこと」と呼んでいます。
結:ワークスルーを経て治療が曲がりなりにも進展すれば、いずれは解決solutionという名の終結が訪れるでしょう。以上のプロセスが首尾よく進んだとしても、勿論すぐに「問題無し」となるわけではありません。従って、一定のフォローアップは必要な場合が多いのですが、お互いにどこか治療関係から自由になることを心掛けながら進むのがよいように思います。
「完全な人間」が存在しない以上「完全な終結」もあり得ないと思いますが、だからこそどこかで終結の決断は必要かも知れません。筆者は概ね成り行きに任せていますが…ここでもウィニコットWinnicott,D.W.は、クライエントが環境を自分の力で利用できるようになれば終結できる、と的確に述べています(コフートKohut,H.流に言えば「年齢に相応しい自己対象体験を享受することができるようになれば」といったところでしょう)。 |

第3節 定則的接近
幻聴体験や妄想は今でもしばしば安易に精神療法的アプローチの対象外とされていますが、統合失調症への精神療法的アプローチ(治療接近)は「治療精神医学」の中心的課題であり、その際に最もしばしば出会う訴えである幻聴体験や妄想への精神療法的治療接近は「定則的接近」として「定石/定跡」化され、とても重視されています。
今から御紹介する「定則的接近」には、二つの狙いがあります。
一つ目は勿論、その論理的内容が患者さんに理解され利用可能となることで、患者さんが幻聴や妄想の体験に支配されなくなる、ということなのですが、不安と混乱の只中にある患者さんにいきなりそのような事を期待するのは無理というものでしょう。最初は次の二つ目の方(「破滅と脱落への恐怖」への手当て)が重要です。
幻聴や妄想の体験に陥っている患者さん自身、どこかで「自分が大変な事態に陥っている、自分の身に普通の人間に生ずるとは到底思えない事が起こっている」と感じ、極度に怯えてられるものです。それに対し「治療者がそれを何か人間の思考の対象として扱い得るものであるように一生懸命言っているようだ」という印象が伝わるだけで、「普通の人間に生ずるとは到底思えない事が起こっている」という体験から来る恐怖(これは「人間からの脱落への恐怖」と連結します)を緩和し、相対化する方向に働くのです。
これらを実際に治療に使ってみようと思って頂けたとしても、以下の具体的接近手順を丸覚えする必要はありません。大切なのは、このような接近手順を産み出す基となっている「病態の構造的理解」の方です。それさえ十分に理解できれば恐らく、以下の手順は自ずと組み立てられることでしょう。
1)幻聴体験への定則的接近
これは、‹構造›を扱う第1段階と、‹内容›を扱う第2段階という、二つの段階から成っています。
[第1段階]
第1段階は、「音声」が実在のものと言えるか否かを構造面から検討することへの導入です。具体的には、
①「音声」をリアルに感じているか否か(音声の感受)の確認、
②「音声」の源が存在しているか否か(を確認しているか否か)の確認、
③傍に居る人にも同じように聞こえているか否か(を確認しているか否か)の確認、
の三つから成っています。そして、
④「音声の感受」はあっても「音源」と「同条件者同体験」が未確認であれば、「聞こえている」ではなく「聞こえる感じがする」と言うべきであることの確認、で仕上げです。
実際にこのように問うてみると、①の「音声」の聞こえ方からして「現実の音声とは違う聞こえ方だ」と言う患者さんの方が多いことに驚かされます。そして②の「音源の確認」はなされていないことが大半で、③についてはしばしば「そんな声、聞こえない」と既に家族等から反論されています。
私達としては、「人間は非常に不安になると色んな感覚が生じてくるので、①だけでは当てにならない。②③を確認できてはじめて本当に聞こえている、と言える。そうでなければ、聞こえているように感じた、と言うべきだ」といった教示を行いつつ、その理解を目指すよりもむしろ、患者さんがこのような論理にどこまでついて来れるかの方に注目します。そうすることで、この定則的接近を一種の探査針として患者さんの今居る地点(スタンス)と、提示したものからの距離(ディスタンス)とを見極めるのです。
[補足]耳を押さえてみる―定則的接近②③の代案
上記の関わり方が辻により定式化された「幻聴体験への定則的接近」の第1段階ですが、ここで「実際に音声が存在するのかしないのか」の見分け方として提案されています②の「音源の確認」と③の「同条件者同体験の確認」は、例えば「一人で居る時に壁の向こうから聞こえる」という場合等のように、実行の困難な場合が多々あります。そしてその場合には「確認できないことは分からないままに置いておく」ということになります。
それは論理的には正しいことなのですが、実際に行うのはかなり難しいことです。何故なら、大抵の場合「聞こえる」と感じる時には不安や恐怖で一杯だからです。
筆者は最近、イヤフォンで音楽を聴いていて、わざわざ言うのも恥ずかしいくらいとても簡単な見分け方に気づきました。聞こえる感じがしたその時、自分の両耳を押さえてみればよいのです。
実際の音声が空気を伝わって耳から入ってきているのであれば、両耳を押さえれば必ず聞こえ方が変わります。逆に聞こえ方が変わらなければ、それは「憑き物」か「テレパシィ」か「幻聴」でしょう。
「憑き物」や「テレパシィ」の実在を信じる、と言うのでしたら、それは「確証無き断定」であり、それ自体「妄想」だと言わねばなりません。もしも、「幻聴」だ、と納得できれば、多少は(下註)無視しておき易くなるでしょう。
(註)実は、「幻聴」だ、と納得されたように見えても、それを全く無視できない方々もおられます。そのような方々に対しては、残念ながら未だ有効な接近法を見出せていません
(-_-;)
[第2段階]
第2段階は、内容の自己所属性に関する検討、即ち、幻聴の内容が、自分の内に在る危惧や願望を反映したものであることを確認する作業です。
第1段階で次第に明らかになるように、実在性が極めて曖昧であるにもかかわらず、患者さんの多くは「幻声」を無視できません。それは、その内容がとても無視できないくらい恐ろしいか(それよりやや頻度は落ちますが)強く願っているか、なのです。幻聴体験は多くの場合、ある種の(主観的)限界状況を背景に生じています。自分の生死に係わる(かのような)強い不安と結びついた危惧や願望は、容易に無視できなくて当然でしょう。
2)妄想への定則的接近
これも、‹構造›を扱う第1段階と、‹内容›を扱う第2段階という、二つの段階から成っています。
[第1段階]
「妄想」は従来より様々に定義されていますが、要するに「確証無き断定」です。この構造的定義は、その妄想的主張の内容がたまたま現実化したとしても揺らぎません。例えば、宝くじを買ったとして、当選発表の前に「3億円当たっている!」と主張すれば、たとえ実際にそれが3億円の当たりくじであったことが後日判明したとしても、立派な妄想です。例外的事象の実在性に関しては、確証義務が生ずるのです(註)。
(註)「例外事象の確証義務」
これは、一般的でないunusualなこと、普通はありそうには思えないことが「ある」と主張するためには、確実な証拠を提出する必要がある、という理屈です。
先日(2011年9月23日)、「ニュートリノが光速を超えた(かも知れない)」というニュースが流れました。これは、現代物理学を支える相対性理論に反する、まさに「ありそうには思えない」出来事でしたので、他の研究機関が追試を行うよう呼びかけられています。最先端の機器で計測された物理学的事象でさえ、そのように慎重に扱われるのです。
第1段階は、このような妄想の構造を扱います。即ち、
①言い分の十分な傾聴(特にその判断根拠については入念に聴きます。)
②明瞭な反証が無いことの確認(通常、明瞭な反証は無いことが多いのです。例えば、「盗聴されている」という主張に反証を挙げることは容易ではありません。)そして、明瞭な反証が無い以上、本人の主張にも幾分かの可能性が有ることの確認
③同時に、確証も無いことの確認(確証が有れば「妄想」ではありません!)そして、確証が無い以上、断定することもできないことの確認
④この論理について来れないと、周りから「おかしい」「妄想だ」「病気だ」と言われるであろうことの伝達(これが仕上げです。)
この[言われるであろう]という言い方には、妄想だの精神病だのと言っても、実体的な自然科学的事象ではなく、あくまでも人間社会の中で規定される心理社会学的な事象である、ということを言外に、しかし明確に伝える、という狙いが込められています。
「妄想」は従来「訂正不能」などとも言われていましたが、このような遣り取りで意外に納得される「妄想症」患者さんも少なくありません。しかし、先にも述べましたように、この定則的接近も、説得することが主目的なのではなく、むしろ患者さんの立地点(スタンス)と提示されたものからの距離(ディスタンス)を見る為のものです。
[第2段階]
第2段階は、幻聴体験の場合と同じく、着想内容が自身の内面に由来するものであることを確認して行く作業です。直接に目に見えない自分の内面を見ることが不得手な患者さんが多いので、この作業もなかなか難航することが多いのですが…
3)鬱への定則的接近
「鬱」とは、「落ち込むこと」ではなく「落ち込むことの拒否」である、ということを共有する為の手順の一例です。
①「落ち込むことは嫌ですか」と尋ねてみる。すると、ほぼ100%「嫌です」という答えが返ってきます。
②その「嫌だ」という思いを認める。一般に、落ち込むことは辛い苦痛な体験なので、原体験心性によって直ちに「嫌だ」と拒絶されます。それは万人に於いて共通の現象ですので、まずそのことを確認します。
③「落ち込むこと」は望ましくない現実を受け入れるプロセスに必然的に伴う現象であることを伝える。「落ち込むこと」は精神分析(クライン学派)で言うところの抑鬱態勢 depressive position であり、キュブラー=ロスが明確化した「自らの死の受容」の過程にも明記されています(⇒『幻想と喪失と悲哀』参照)。
④「落ち込むこと」を嫌がり過ぎると、現実を拒否し、何もかも投げ出すことになる、それが「鬱病」と呼ばれる状態であることを伝える。
このようにお話してきますと、患者さんが自ずとその「受け容れ難い現実」に思いを致し、納得されることも稀ではありません。しかし、そのように展開しないことも少なくありません。その場合には、落ち込むきっかけについて、患者さんと共に詳しく調べて行くことも必要となります(⇒『うつ』参照)。
以上の記述からお分かりのように、これらの「定則的接近」は多分に「認知療法」的です。強いて違いを挙げれば、「認知療法」に比べるとこれら「定則的接近」では、クライエントの「不合理な思い込み」を修正することよりも、相手の立地点(スタンス)と、提示した認識からの距離(ディスタンス)を見ること、そしてその立ち位置に寄り添うことの方に重きを置いている、ということでしょうか。
そして、冒頭にも記しましたように、当面の目的は何よりも「これらの体験が人間の思考によって扱い得るものであること」を伝え「破滅と脱落への恐怖」に手当てすることなのです。 |

第4節 治療関係に於ける相互作用
1)転移(神経症)と転移性恋愛
典型的には精神分析療法のセッティングに於いて、クライエントの幼児期に起源を持つ様々な問題が専ら治療者との間の事へと集約して来る現象を、精神分析学では「転移(ないし転移神経症)」と呼んでいます。そのような事が起こるのは、原体験心性の《述語的状況性の優位》という性質のお蔭です。つまり、同一の述語的状況(厳密に同一でなくとも類似していればよいのですが)が、主語的登場人物を替えて反復されるのです。
精神分析のセッティング以外の状況でも転移に類する現象は見られるのですが、精神分析のセッティングというのはなかなかうまくできていて、一方ではカウチ(寝椅子)に横になって自由連想を行う、というとても退行(幼児返り)促進的な指示を与えつつ、他方で時間や料金などの取り決めをきちんと交わすという退行禁止的な措置を行います。このサイトの用語で言えば、前者で「心の鎧(または自我)」の解除を求め、後者で「心の鎧(または自我)」の起動(再起動)を求めているのです。
もう一つあります。それは面接頻度に関する事なのですが、精神分析の治療構造では通常、1回50分程度のセッションが週に4~5回持たれることになっています。ところが、欧米では年に2回程度「長期休暇」が入ります。これがまた、一方で大いに依存感情を醸成しつつ、他方で「一人でいること」を強制する、という矛盾に満ちた構造になっています。
恐らくは、このような矛盾したメッセージで構成される二重拘束的double binding状況自体が、クライエントを支配している幼児期的問題状況と共鳴し、過去の未解決の問題を現在時点に甦らせることに一役買っているのでしょう。
フロイトFreud,S.のこの発見以来、転移は精神分析療法の重要な治療的契機と見做されて今日に至っています。
転移性恋愛と呼ばれるものも、このような転移現象の内の一つです。こう言ってしまえば簡単なようですが、ここには少し厄介な問題があります。そもそも「本当の恋愛」自体転移(それがエディプス水準であれば、相手が「父親」であったり「母親」であったりしますし、より早期のものであれば相手が「乳房」であったり「抱える腕」であったり、更には「子宮」であったりします)が関与しており、「恋病(こいやまい)」という言葉があるように、極端に言えば一つの病気(転移神経症)かも知れません(確か、どこかでフロイト先生もそんな事を仰っていたと思います)。そうであれば、「それは転移性の恋愛感情です」と言っても「本当の恋愛感情ではない」と言っていることにはならないのです。
通常の人間関係でしたら、片方が恋愛感情を抱いても片方が抱かなければ「片想い」ということで終わるのでしょうが、治療関係ではそれで「さようなら」とするわけにはいきません。まさにその転移をこそ扱わないといけないのですから。
この「扱う」というのは勿論その恋愛感情に素朴に応えることではなく、その恋愛感情の起源を探ると同時に、それが自分自身へと目を向けることを妨げて治療の進展への抵抗となっていないかを共に吟味することです。
[補足]「愛」についての無粋なコメント
「愛」は人々によって切に求められているにもかかわらず、分かっているようで分からない(或いは、さまざまな顔を持つ)不思議な事象です。そのお蔭で古今東西の文学・芸術の主題であり続けています。そして、そのような事情は、「狂気/精神病」とも相通ずるものだと言えましょう。
両者が共有するこのような事情には必然性があると思われます。即ち、両者が共に、私達が容易には自覚し難い原体験心性と深く結びついているからです。
原体験心性そのものに近い未熟な(自他の区別の無い/独り善がりな)「愛」はお互いを損ないます。何故なら、その「愛」は相手のためと思いながら、実は自分のためのものだからです。結果的に「(未熟な)依存」や「執着」でしかなくなります。
逆に言えば、自他の区別を前提とした、独り善がりでない「愛」が成熟した「愛」だということでしょう。しかし、それではそういう形容ぬきの「愛そのもの」とは何か、と問われれば、また分からなくなります。
フロイトは当初「リビドー」という擬似エネルギー概念で性愛の志向性と衝迫力を表現しようとしました。更に後には「エロス」という言葉で、性愛をも含み込んだ「まとめ上げ同化する力」を表し、「ばらばらに破壊する力」としての「死の欲動(タナトス)」と対置しました。そして、両者(エロスとタナトス)は初めの未分化な状態から分化すると考えていました。
要するに、最初は愛は同時に破壊的である、ということで、これは「食べる(同化する)ことが同時に対象を消す(破壊する)こと」であるという口愛期と呼ばれる乳児期の体験モードでもあります。冒頭の「未熟な愛」はこの状態に対応しています。そして「成熟した愛」は、破壊から分離された破壊を伴わない愛だ、ということになるでしょう。
[以上、《対話の広場》への2008年 5月 2日付けの投稿に加筆したものです。]
2)心の傷つきと修復
既に記していますように、人は原体験心性(≒未熟な自己愛)を持って生まれてきます。それはそのままではとても傷つき易く壊れ易いものでしょう。『問題事象の理解モデル』や『ライフサイクルと臨床的諸問題』のページでも触れていますように、乳幼児は一般に、養育環境によるサポートのもとで適度にコントロールされたフラストレーションを経験し、その中で心の傷つきと修復を繰り返しながら成長して行くようにできています。
いわゆる虐待、或いはそこまで行かない不適切養育や、こどもの側の発達的要因など、何らかの事情によって、不幸にもそのようなプロセスがうまく進行しないと、極端な場合「傷つくこと=生きて行けないこと」と認識され、傷つきを必死に避けようとするようになります。そのような人は皮肉な事に、実際は「とても傷つき易い人」となってしまいます。
勿論、誰でも原体験心性と無縁ではいられず傷つくことはイヤですが、通常はどこかで「仕方が無い、避けられない」と思って受け容れる構えができているものです。そのような心構え(つまり、傷つくことを避けない態度)ができていればいる程、その人は却って「傷つき難い人」であるでしょう。
治療関係は概ね心を育てる過程ですから、これもまた傷つきと修復の過程です。そして患者さん/クライエントは多くの場合、傷つきを必死に避けようとする「とても傷つき易い人」となっています。だとすればこの場合、治療は患者さん/クライエントが傷つくことを避けない「傷つき難い人」となることができるよう援助することですから、まずは治療者がそうでなければならないでしょう。 |

第5節 精神医学的常識への疑問
ここでは特に、薬物療法と「早期発見・早期治療」論の功罪、及び「精神分析」批判の妥当性について考察します。
1)薬物療法の功罪
薬物は確かに有効です。筆者は実のところ、ハロペリドール(商品名セレネース)を開発したポール・ヤンセン(Jansen,P.1926-2004)こそ、精神医療に実質的に最も貢献した人物の一人ではないかと思っています。更に彼は、晩年にあのリスペリドン(商品名リスパダール)まで開発したと言うではありませんか!
ハロペリドールのお蔭で精神医療は随分やり易いものになったのだと思います。
とは言え、リスパダールを売りに来たMRさん(製薬会社の営業マン)に「従来薬であるセレネース(とその副作用止めに頻用される商品名アキネトン)は認知機能に障害を与えるが、リスパダールにはそれが無いらしい」と聞いて愕然としました。そんな事とは露知らず、それまで私は、副作用を懸念する患者さんに「何十年ものんでいる人もいますが安全です」と保証していたからです(無論、遅発性ディスキネジアの厄介さは知っていましたが、意外にお目にかかりませんでしたし、「用量を抑えていれば良いか」程度にしか考えていませんでした)。不明を恥じるしかありません
m(_ _;)m
ところで、薬は何故有効なのでしょうか?
恐らく、人間の頭脳という極めて精密繊細な構造物に対して、薬物という物質は極めて大雑把な働きをしていると思われます。また、そうでないと困ります。何故なら、もしある薬剤によって細かい考えまで変え得る、というのであれば、それはまさに究極のマインド・コントロールであり、洗脳だからです。
そのような大雑把な作用でも意味が有るとすれば、それは必然的に「情動/感情」の領域です。「情動/感情」は(認知された)周囲の状況からただ自動的に生じてきます。認知の仕方自体は、「理解モデル」の章で見ましたように恐らく成育史的に規定されていて、すぐには変わらないので、今現に生じている不安や恐怖やパニックに対しては、薬物(鎮静剤や睡眠導入剤)を使うのが最も効率的です。
「心の鎧」の性能があまりよろしくないと、不安や恐怖やパニックに囚われ易い状況は続きます。そのような間も、薬物を一定量服用し続けると気持ちが安定し易くなって、不安や恐怖やパニックの予防に役立つかも知れません。
しかし、薬物にできるのはそこまでだと思われます。飲み続けても再発(再燃)する時はします(「飲み続けていれば再発しない」などと本気で信じている精神科医などいない筈です)。「心の鎧」や「自我」は様々な意味情報の中で発達してくるものです。そのような事に、脳内で大雑把にしか働かない薬物が大きく関与できる筈も無いでしょう(「そんな事ができるのなら、学校なんか要らない」というのが辻先生の口癖です)。
[補足1]薬物療法中心主義の神話
薬物療法中心主義の根拠として必ず持ち出され、今や大半の精神医療関係者の間で(思考停止としか思えないくらい)無批判的に受け容れられている「統合失調症のドーパミン仮説」や「鬱病のセロトニン仮説」のいかがわしさについては、『参考図書』にも挙げていますエリオットSヴァレンスタイン著『精神疾患は脳の病気か?』に詳しいです。
そもそも、薬もまた人間が産み出した「便利な道具」に過ぎません。それは主体的に利用されてこそ、主体性の醸成(=自我の育成)と矛盾せず、それを助ける物となります。逆に、薬に幻想的な期待を投げ掛けて「苦しいこと辛いことを薬によって消すことができる」と思い込んでいると、薬にすっかり頼ってしまい、自分を頼りにすること(主体性の醸成)が大きく妨げられてしまいます。道具が人間をコントロールすることが本末転倒であるように、薬が人間をコントロールすることも本末転倒です。
[補足2]服薬継続/服薬中断と転帰
第103回日本精神神経学会総会シンポジウム「統合失調症におけるストレス脆弱性の問題」に於ける発表「発病・再発および経過に関わるライフ・イヴェント」(中根允文)によれば、発症から2年後の短期転帰での適応不良例数は、服薬を継続していなかった16名中12名(75%)に及びますが、服薬していた27名に於いても10名(37%)を数えています。逆に服薬を継続していなくても25%は適応良好だったわけでもあります。
無論、母数が少ない上に僅か2年後の転帰ですので、統計学的説得力はさして無いのかもしれませんが、「服薬継続は絶対に必要、服薬していれば再発しない」という信仰への反証にはなるでしょう。
にもかかわらず、家族も精神医療関係者も、患者さんに薬をのませ続けることに異様なほど熱心です。何故でしょうか?それにも幾つかの理由が考えられます。
① 「薬をのみ続けていれば再発しない」と信じたい。
確たる証拠が無くても何かを信じて安心したい、というのは何も妄想症の患者さんに限った事ではありません。
② 薬が与えられのまれている限り、医療の枠組みに納まっていることになる。
これは、効く効かないは別として、投薬-服薬という行為自体が、問題事象を「精神病/精神障碍」として医療モデルの内部に納める働きをし、その事がまた人々の安心に繋がっている、というお話です。
③ 薬という目に見える具象物しか目に入らないようになっている。
何かトートロジィ(同語反復)のようですが、もう少し砕いて言うと、「こころや在り方という直接に目には見えないものを洞察する」ということが患者さんも家族も、そして精神医療関係者も共にできなくなっている、ということです。その為に、直接目には見えない「こころや在り方」の具体的結果に過ぎない「病的」言動(即ち「症状」)を、これまた具体的な物質である薬物でコントロールする、という発想しか持ち得ないわけです。
これらの事情の結果、患者さんは「薬をのまない=病気ではない」という図式で服薬を拒否し、精神医療関係者や家族は「薬さえのんでいれば治る」と言って服薬を強制します。そうして両者が不毛なバトルに陥っていることも、決して珍しい事ではないと思います。両者とも薬という補助的手段を絶対化し、中核的手段であるかのように思い違いしている点で、全く同じです。
確かに、「心の鎧」の性能が向上したり「自我」が確立されて来ていない状態のままでただ薬だけをやめても、再発(再燃)の可能性は高いでしょう。再発(再燃)するとしばしば「そら見たことか!やっぱり薬は必要なんだ」と家族も精神医療関係者も、そして患者さん自身もそう思うようになります。そのようにして、こころや在り方の問題はますます顧みられなくなってしまいます。
この事にはもう一つ重大な副作用が有ります。投薬-服薬というのは非対称な関係性を支えています。つまり、薬を与える人(医療従事者≒親)と薬を貰う人(患者≒子)という上下関係を固定化し強化することに自動的になっているのです。近年、身体医療の領域では患者さんの権利も徐々に認められて来て、医者-患者関係がかつてのような上下関係ではなくなりつつあるかも知れません(実はこれ自体も少々怪しいのですが)。他方、仮にも精神に影響を与えるような薬を媒介にした関係はなかなか対等とはなり難く、患者さんはしばしば子供の立場に置かれ続け、この事もまた反治療的に働くのです。
[補足3]服薬への説明の実際と「コンプライアンス/アドヒアランス」について
以上のような考えに基いて関わっていれば、患者さん達が薬を飲まれなくなるかと言えば、全然そんなことはありません。むしろ逆に、多くの場合、自発的に(自覚的に)飲まれるようになります。
対話が可能な状態のクライエンとの治療に薬を導入する際の実際の説明は、大体次のように行っています。
(この「実際の遣り取り」はあくまでも一つの例に過ぎません。大切なのは言うまでもなく「考え方」の方です。このサイトの他の所でもそうですが、臨床家の方々は、具体的な遣り取りの例についてはどうかお忘れ下さい。)
① 事情を十分に聴取した後、「強い不安」⇒「睡眠障害」⇒「判断力の低下」⇒「益々強まる不安」といった悪循環の存在を確認します。
② この悪循環を自力で解くのは困難であろうことを伝えます。
③ 対症療法ではあるが、とりあえず薬という物質は「強い不安」を鎮めて、悪循環を断つのに最も手っ取り早い手段であることを伝えます。
④ 「ずっと飲め」とは言わないが、薬もうまく利用すれば役に立つ人間が作り出した道具なので、頑なに利用しないのもどうかと思う、と伝えます。
このまま飲まなければ急性精神病状態に陥ることが必至と予想されるケースでは更に
⑤ 「入院はしたくないでしょ?だったら、飲んどいた方がいいよ。うまく効けばかなり長時間眠れる筈(はず)なので、家で入院しているつもりで眠れるだけ寝て下さい。その方が回復が早いですから」とご本人とご家族を説得します。
ここまで言っても「飲まない」と仰る方は稀ですが、それでも了承されなければ仕方が無いので(危険な行動化が高い確率で予想されれば強制入院もあり得ますが、通常は)お引取り頂きます
 (そのような患者さんでも、一二度入院しなければならなくなると、こちらのお話が妥当なものであることを認めて下さることが殆どです。) (そのような患者さんでも、一二度入院しなければならなくなると、こちらのお話が妥当なものであることを認めて下さることが殆どです。)
こんな風な遣り取りをしていますと、例えばこれまで他の治療者との間で拒薬や断薬を繰り返されていた患者さんも大抵は(良い悪いは別として)自ら服薬されるようになられます。つまり「コンプライアンス」complianceと呼ばれている服薬遵守率がむしろ上がるわけです。しかし、これはあくまでも結果であって(人間心理からすれば当然の結果なのですが)決して目的ではありません。[尚、最近ではこの「コンプライアンス」という語(これは元々は「服従すること」であって主に「法令遵守」の意味で使われているようです)が医療者側の一方的正当性を前提としていることへの反省から、固守/墨守/執着という意味の「アドヒアレンス」adherenceという語が使われているようです。これもあまり良い響きではないように思いますが…]
筆者は診察の際に原則として毎回最後に「余ってる薬や要らない薬はない?」と尋ねるようにしています。これは別に、拒薬や断薬の有無を探ろうとしているのではありません。余ってる薬や要らない薬があってよい、という文脈の下での問いです。何よりも、薬の効用について共に検討し、薬の利用にも責任を持って参加して頂くのが目的なのです。
[補足4]薬の「効能」と「副作用」
ある薬の「効能」と「副作用」は、その薬の様々な「作用」を人間が勝手に分類しているに過ぎません。
例えばパキシル™のようなSSRIは、神経細胞(ニューロン)の接合部(シナプス)に於けるセロトニンという神経伝達物質の再取り込みを選択的に阻害するようデザインされていますが、それが、極めて複雑で個体差も大きな脳の神経ネットワークの中でどのような結果を惹き起こすかまでは、到底予想しきれません。
開発段階や市販後調査などで出てきた、その薬と関係のありそうな都合のよい結果は「効能」に分類され、その薬と無関係とは言いきれない不都合な結果は「副作用」として報告されるのです(「無関係とは言いきれない」ということであって、実際には無関係なものも含まれている可能性はあります)。
故に、様々な薬剤情報は参考にはなりますが、それ以上のものではありません。あとは、個々の利用者が「自分の場合」をよく観察し、自分にとって役に立つように担当医と十分に相談しながら利用すべき(或いはしないべき)なのだと思います。
2)「早期発見・早期治療」論の功罪
製薬会社後援の研究会は勿論、学会などでさえ、精神疾患の早期発見・早期治療の重要性がしばしば説かれています。筆者には、そのような主張をされる先生方は本当に考えて仰っているのだろうか、といつも疑問に思われます。
確かにからだの病気を扱う身体医療に於いては、早期発見・早期治療は殆ど例外無く望ましいものです。肺炎などの感染症にしても癌などの悪性新生物にしても、早期に発見し早期に治療を開始するに越したことはありません。逸早く診断をつけることが経過の予測と治療法の選択を可能とし、半歩でも先手を打つことが確実に予後を良いものにします。しかし、精神疾患の場合はどうでしょう?
例えば、精神疾患の中でも臨床的に今尚中核を占めると思われる「統合失調症」の場合、未だに目に見える実体的(生物学的)原因はもとより疾患特異的マーカーさえ確定されていません。従って、診断はどの時点であっても「表出された臨床症状」に依拠してなされます。そこで、例えば中安信夫氏によって整理された「初期分裂病(初期統合失調症)」概念とその診断カテゴリィに依拠して、未だ十分には症状を呈していない「統合失調症」を「早期発見した」としましょう。そのような患者さんに「あなたは統合失調症の初期です」と言うことはさすがに無理があると思われたのでしょう、中安氏は「神経衰弱」などの古典的診断名を持ち出して説明すると仰っていましたが、そのように少々不誠実な対応をせざるを得ないところに、精神疾患に於ける早期発見・早期治療の矛盾が露呈しています。
筆者はむしろ、精神科の治療は概ね患者さんに半歩遅れてついて行く形の方が良いと考えています。それは私達の理解からすればこういう事です。つまり、一般に患者として私達の眼前に現れる人々は、「こころ」や「在り様」という直接には目に見えないものを捉えることが苦手(その力が不十分)です。その彼/彼女に「あなたはしかじかの精神疾患になりかけています」などと言ってもおよそ理解困難で、自己理解への何の助けにもなりません。それどころか、「精神科に連れて行かれた」というだけで直ちに「精神病=脱落」の意識が働いて、崩れかけている主体性(この場合には防衛的自我[このサイトで言う「心の鎧」]の働きですが)を更に無力化し、結果的に立派な「統合失調症」をさえ作ってしまいかねないのです。
「半歩遅れて行く」とは、問題が具体的な目に見える形で現れるのを待って、それから介入を考える、という姿勢です。そうすれば、私達は患者さんの中にあって患者さんが見ることのできていない問題を、外への具体的な現れとつなげて提示することができ、患者さんの自己理解を助けることができます。
筆者は早期対応を一概に良くないと言っているわけではありません。早期の治療的介入によって悪夢のような幻覚妄想体験を回避できるのであれば、それにこした事は無いとも考えています。しかし、それには崩れかけた防衛的自我(このサイトで言う「心の鎧」)を支えつつその問題点を扱うという相当デリケートな感受性に基く作業を要します。ただ「早期に投薬治療を開始すれば良い」という単純なものではないのです。
丁度、2006.12.25発行の『精神神経学雑誌』(Vol.108 No.12)の巻頭言に「統合失調症の早期発見・早期治療の流れ」と題された一文がありました。それには、DUP(duration of untreated psychosis=発症から治療開始までの期間)が1年未満のものは、1年を超えるものよりも、再発までの期間が有意に長い、という統計的研究結果から、統合失調症初回エピソード以前の前駆期からの働き掛けがより有効である可能性を想定した取り組みへの期待が述べられています。実際に精神疾患早期の訪問型治療チームによる相談・支援、診断・治療が行われたイギリスでは自殺率が6%減少し、ロンドン地区では入院が20%、経費が40%減少したそうです。
筆者は、総合病院精神科の外来で、前精神病状態 pre-psychotic state 或いは準精神病状態 sub-psychotic state と思われる患者さんを何人も診療させて頂きました(総合病院の精神科は精神科専門病院よりも受診に際しての抵抗が少ない為、明瞭な精神病症状が無い「前駆期」的患者さんも受診し易い為だと思われます)。確かにそのような患者さんは概ね、注意深い精神療法的関与と少量の向精神薬とで、入院加療を要せずに外来のみで治療を続けて行けます(従って、医療費も少なくて済むでしょう)。
しかし、これは患者さんが自ら求めて外来を訪れられた場合であることを忘れてはなりません。
DUPが「発症」を起点としているにもかかわらず、その統計結果をもって発症以前の「前駆期から」の働き掛けがより有効である可能性を想定するのは、実のところ「脳病モデル」ならではの発想です。我国の現状で無邪気に「精神病予備軍探し」のようなことを始めればむしろ、先に述べたような事情で「医原的精神病」を産み出すことさえ危惧されます(イギリスの施策の詳細は把握していませんが、早期治療チームを構成するスタッフの質も、事の成否を大きく左右することでしょう)。
そもそも[発症から治療開始までの期間(DUP)が1年未満のものは、1年を超えるものよりも、再発までの期間が有意に長い]という統計結果にしても、このような書き方ではあたかも身体疾患のように、早期の加療(この発表を行ったCrow,T.J.は典型的な生物学的精神医学者ですから、「治療」は概ね薬物療法を指すでしょう)によって脳内の疾患過程が抑えられる、と読めます。しかし、これは明らかに偏った解釈です。真相を究明する為には、発症から治療開始までの期間(DUP)を左右する多くの要因(例えば家族関係や経済状況、医療環境など)と再発との関連性をもきちんと分析すべきでしょう。
3)精神分析批判への反批判
合州国での精神分析の斜陽化と生物学的精神医学(ネオ・クレペリン主義)の隆盛(?)を受けて、近頃本邦でも精神分析があたかも歴史的失敗であったかのように喧伝する「啓蒙書」が目に付くようになりました。
確かに「定型的精神分析療法」は寝椅子で自由連想を行うことが条件で、1回50分を週4回以上の頻度で3年~5年は続ける、しかも基本的に自費、という途方もない実践で、余程時間とお金に余裕のある人しか受けられず、しかも「自己覚知(自分をより深く知ること)」に主眼が置かれ、「治療的効果/治癒」はその(喜ばしい)副産物という位置に置かれています。つまり、治療法としては全く実用的ではないのです。それよりも、服用するだけで不安や抑鬱に一定の効果のある薬の方が評価を受けるのも止むを得ない事かも知れません。
しかし、それでも筆者は「精神分析は擁護されるべきだ」と思います。それは、精神分析を通してしか達成できない事があると思うからです。そして、そこから私達は人間の心について多くの事を学ぶことができるからです。実用的でないからと言って、そのやり方や学問的成果が誤っているということにはなりません。
精神分析の学問的成果を否定するような議論は、「心」や「意味」の次元が「脳」や「物質」の次元とは別に存在することを解さない人達の的外れな暴論だと言ってしまえばそれまでなのですが、そこでは人間の心とその病理の精神力動的理解まで否定され、全ては神経伝達物質やニューロン(神経細胞)の機能異常で片付けられるといった主張があたかも実証済みであるかのように述べられています。そして、それらの人達は更に、フロイトの精神分析のみならず(中には、初期フロイトの外傷理論のみを精神分析理論だと思って批判している論者までいる始末ですが)、そこから発展した精神療法的接近までも全てが間違っているかのように主張しています。これは大変嘆かわしい事です。
『精神と身体』の処でも触れましたように、脳は意味情報を扱う器官です。もちろん物質的存在ですから直接に物質(例えば薬)の影響も受けますが、同時に意味情報の入力の影響も受け、それを処理する中で自らが変化し成長発達して行く器官なのです。
精神分析やそこから派生した精神療法/カウンセリングを初めとする様々な理解と働き掛け(「治療精神医学」はそうしたものの最良を目指しているのですが)は、主に意味情報を介して脳に働き掛けているとも言えるわけで、「心の成長発達を促進する薬」が現れない限り(そんな薬はあり得ないと思いますが)、決して無用となるものではないのです。
[補足]精神分析の抑圧?
フロイトの『ある幻想の未来』や『文化への不満』に於ける痛烈なキリスト教批判や西欧近代文明批判を読んでいますと、当初の激しい批判に抗して欧米の知識人層を中心に受容されていった精神分析が、今またそのキリスト教社会や、更に発展しつつある高度資本主義文明によって(今度は統計的実証主義を振りかざして、より合理化された形で)抑圧されようとしているのではないか、という連想に駆られます。
精神分析が本来、私達のこころの中の反常識的世界を明らかにする実践であることを考えますと、精神分析が持続的発展を遂げることによって常識的世界に与えるインパクトは計り知れないでしょう。従って、精神分析の表面的凋落の裏にそのような精神分析への恐れが作動しているというのは、強(あなが)ち的外れではないのかも知れません。
|

第6節 ご家族の関わり方へのヒント
―EE(expressed emotion)研究(“Expressed Emotion in Family”by Leff,J.&Vaughn,C.1985,邦訳『分裂病と家族の感情表出』金剛出版)より―
EE(expressed emotion)というのは直訳すれば「表出された感情」という意味で「感情表出」と訳されています。ジュリアン・レフLeff,J.とクリスティン・ヴォーンVaughn,C.という人達が中心となって、CFI(Camberwell Family Interview)の短縮版を用いて、特に患者さんへの批判のパターンに注目しながら家族にインタヴューを行い、次のような見解を述べています。
1)高EE(批判的で、情緒的に巻き込まれ過ぎ):かなり侵入的。
患者が静かに引き籠っている時に、繰り返し接触を持とうとする。患者のプライヴァシィを尊重しない傾向がある。患者の寝室のドアを閉めることを嫌がり、予告も無しに患者の部屋に入ろうとしたりする。患者の日課を監視し、余計なアドヴァイスをしたりもする。患者の話に対して受容的でなく、繰り返し患者を事実に直面させようとする。病気や患者の障害を許そうとはしない。⇔患者には、防衛的な引き籠りがよく見受けられる。過剰な刺激やストレスに対するもう一つの一般的反応は攻撃である。
2)低EE(批判や情緒的巻き込まれ過ぎが殆ど無い):患者に合わせて、保証し社会的サポートを行えばいいのか、或いは距離をとればいいのか、というやり方を身につけている。患者に共感を示し、患者の苦しみを理解しようと努める。患者の奇妙な行動や妄想に対する合理的な説明(例:まるであの子の幼い頃の事が、大人になった今の生活の中に現れて来たみたい。あの子は全部ごちゃまぜにしてしまってるみたい)を求める。患者の機能低下に耐える能力が高い。⇔患者は、控え目で侵入的でない家族を避けることはない。
これらを踏まえて「統合失調症患者が急性症状の回復の後に良好な経過を辿る為には、家族の侵入的でない寛大なアプローチ(即ち低EE)が有効である」というのが彼らの結論です。
しかしながら、高EEがまさに<逆転移>であることは自明ですが「低EEもまた一つの‹逆転移›だ」という指摘もあって、事はそう簡単には行きません。
‹逆転移›という文脈で見てみると、原体験心性に由来する「狂気/精神病」という転移に対し、高EEの方がごく素朴に感情的に反応しているのに対して、低EEの方は距離を保って合理的な見方に徹することで、却って「狂気/精神病」を拒絶している可能性も考えられます。
しかし、最も大切な事は、当事者を追い詰めないことです。それにはやはり低EEの方が良いのでしょう。 |

第7節 治療的変化の道筋
最後に、以上のような関わりの中で何が起こるのかということをごく簡単に言うと、次のようになると思います。(下図の➟)
病んだ子供⇒臨床的事態⇒健康な子供⇒健康な大人
(ブレイクダウン)
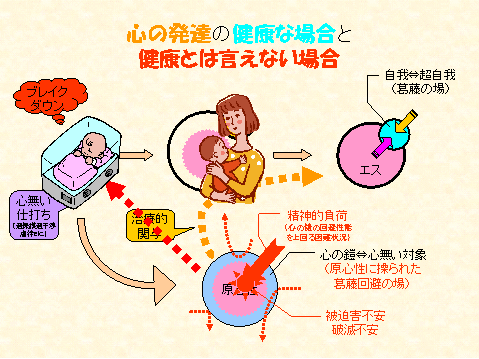
「病んだ子供」というのは「心の鎧」で防衛している状態です(⇒『こころの理解モデル』)。その防衛が破綻して臨床的事態が生ずるのですが、それは最悪の場合「原体験心性」が無防備に晒されてしまった状態で、心にとっては死に等しい事態でしょう。
さりながら、治療的サポートの中で心の「死と再生」がうまく進行しますと「健康な子供」が誕生し、やがては「健康な大人」として機能するようになる、という訳です。
さて、私は出発点に「病んだ大人」とは書きませんでした。私が今までお会いして来た患者さん方は皆さん、私には「病んだ子供」に見えたからです。だからと言って「子供扱い」を推奨しているのでは決してない、ということは、このサイト全体を御覧頂ければ分かって頂けると信じています。 |

第8節 精神療法・カウンセリングの底流
或いは
「何が癒しを齎(もたら)すのか?」
最後に、以上の議論ではまだ十分に掬(すく)いきれていないと思われる極めて重要な問題、即ち「何が癒しを齎すのか?」を巡って、精神療法・カウンセリングそのものの分析を少し試みておきましょう。これは、フロイトの精神分析やそれから派生した様々な分派・学派、ロジャーズのパースン・センタード・アプローチやそれから派生した流派、認知行動療法の諸派、本邦の森田療法や内観療法、等々、現在存在する無数のセラピィの一つ一つを分類整理しようというものではなく、それらそれぞれに含まれている幾つかの普遍的とも思える治療的要素を改めて取り出し考察する試みです。
1)古代~中世に遡る楽観的神秘主義の流れ
=「自然治癒力」への信頼
⇒成長促進的関係(環境)の提供
「神秘主義」と言うとちょっと怪しげにも聞こえるかも知れませんが、この言葉で言わんとしていますのは、人間の理性的働き以前に(或いは、人間の理性的働きを超えた処で)働いている「正体不明の何か」が存在する、という主張です。そして、「楽観的」と形容しましたのは、その「正体不明の何か」が基本的には「よいもの」であると信ずるからですが、これは「全ての生きとし生けるものには仏性が宿っている」といった仏教の考え方と通ずるものがあります。
故に、本邦で発達した森田療法や内観療法は基本的にこのような前提に立っていると言えるでしょうし、グロデックの「エス(Es)」、ユンクの「セルフ(Selbst)」、ビオンの「O」、ウィニコットの「真の自己(true self)」、ロジャーズの「無人格(impersonality)」等の概念も、このような系譜に連なっているもののように思われます。
(註)フロイトは「エス」という術語をグロデックから借用しましたが、フロイトの「エス」は生の欲動(エロス)と死の欲動(タナトス)の戦場であり、「エス」を無条件に称揚したグロデックとは捉え方が異なっています。そしてその結果、フロイトに於いてはそのような闘いを適応的に調整する「自我」の働きがあくまでも重視され、自我心理学へと繋がって行きます。
この流れに於いては、どちらかと言うと「作為」を排して、患者(クライエント)が自らの内なる「何か」に耳を傾けそれに親しむ、ということをいかに保障するか(そのような環境をいかに提供するか)ということが、治療の中心となります。
[EMDRに関する補足]
EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)は、眼球運動(或いはその代わりとなるリズミカルな左右交互刺激)という非常に作為的な手技を多用しますが、それにもかかわらず、この療法はここに分類されるでしょう。何故なら、その手技は、クライエントが自らの注意を安全な現在に繋ぎ止めつつ過去の辛い記憶へとアクセスすることを可能にすることで、「本来の情報処理過程」という少々謎めいた「自然治癒」のプロセスの作動が促され、そのことによって治癒がもたらされる、とされているからです(EMDRに関するもう少し突っ込んだ考察は『EMDRの衝撃』にあります)。
2)近代的な理性的自我中心主義の流れ
=洞察至上主義
⇒明晰な分析結果の提供
これは、近代以降の市民社会が前提としている考え方で、自我による認識(認知/自覚)を何よりも重視します。解釈を通しての洞察を重視する精神分析諸派や誤った信念の是正を目指す認知(行動)療法の諸流派がこの流れに属するでしょう。
この流れに於いては、どちらかと言うと作為的な「技法」が重視され、自我の理性的判断能力・統制能力が当てにされています。
この流れの最も素朴な形のものとして、SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)やコーチングを含めることもできそうです。実際、SSTは認知行動療法の一つとされています(⇒『SST普及協会』HP)し、コーチングも精神分析から派生した交流分析(TA)や、認知行動療法に近い神経言語プログラミング(NLP)といった理論体系を拠り所としているようです。
[認知行動療法に関する補足]
近年、精神療法と言えば認知行動療法、と言われるくらい、認知行動療法が隆盛です。恐らくは、少なからぬ病態に関してその「治療効果」が「実証されている」のと、技法がマニュアル化されていて、比較的に実践し易そうに見えるからなのでしょう。
「治療」を追求してきた治療精神医学の実践の中にも、「期せずして」認知行動療法的要素は多々含まれています。
しかしながら、言うまでもなく、「認知行動療法」にも限界はあります。例えば、ターゲットとすべき不当な信念を当人が言語化できないことなどもあります。
より本質的な問題として、患者と治療者の二人で共同作業を行って行く、という「治療同盟」と、それを支える信頼(いわゆるマイルドな陽性転移)が成立していなければ、治療は恐らくうまく行きません(この点に関しては、古典的精神分析療法と事情は同じです)。
「やり抜くことworking through/Durcharbeiten」と「馴染みの法則」
長年治療に携わってきてしみじみ思うのは「ひとは変わり難い」ということです。たとえ「あっ、分かった!」と思っても、分かった時の感動は一時的なものでいつの間にか色褪せてしまい、得られたはずの認識が霧散してしまうことが少なくありません。精神分析の創始者Freud,S.がDurcharbeiten(ドイツ語:通常「徹底操作」と訳されています)の必要性を指摘したのはさすがです。
「あっ、分かった!」というのは、いくら感動を伴っていても所詮は理性による認識です。しかし、ひとを支配するのは理性よりも感情/情動です。こちらは原体験心性(エス)に直に根差しています。そして、原体験心性(エス)を支配するのがポジティヴ/ネガティヴの法則(快‐不快原則)と共に「馴染みの法則」です。
従って、ひとを動かすには、現状への馴染みに逆らって、新たな状況への馴染みを作る必要が有ります。その為に、精神分析であれば、機会あるごとに同じ解釈を繰り返す(「徹底操作」)、決まった治療構造で頻回に会い続ける(そうすることで治療者との間に「感情転移」と呼ばれる新たな馴染みが形成される)、といったことが工夫されていますし、認知行動療法ではまさに「行動療法」の部分がこれに相当します。
〔この部分、2022.08.09に補足〕
3)現代の行動科学的システム論的アプローチの流れ
=変化至上主義
⇒戦略的介入
これは、人間(及びその集団)を一定の法則に従って作動している一種の機械と見做す考え方に基いています。こう言うとえらく極端な考え方のようにも聞こえますがそうではなく、これこそは現代の科学的人間理解そのものに他なりません。
このアプローチでは、治療とはその作動の仕方を変えることであり、その為に有効な介入を考案し「処方」します。故に、この流れに於いては、治療は高度に作為的となります。
これは未だ筆者の単なる印象に過ぎませんが、実際の臨床では上記2,3の立場をきちんと突き抜けて上記1に達することができれば理想的なのかも知れません。或いは、真に上記1の機能に到達する為には、上記2,3の修練も欠かせないのかも知れません。しかしまた、もしかすると仏教で言う「妙好人」のように、ごく自然に上記1の治療的態度を実践できる「天性の治療家」も、多くはないでしょうが居られるのかも知れません。 |

第9節 集団療法
治療技法としての集団療法に関しては、若い頃に「エンカウンター・グループ」に興味を持って少し勉強した程度で、筆者自身が実践することはほぼ無く、余り書くべきことは有りません。もともと集団が苦手という筆者の性向も関係しているかも知れません。
ここでは、アルコール依存症に対する自助グループについて、日米の興味深い差異を見ておくだけにします。
- 米国⇒AA(アルコホーリクス・アノニマスAlcoholics Anonymous)
- 日本⇒断酒会(日本にも上記AAは存在しますが、日本的なのはこの断酒会です)
何が興味深いかと言うと、この二つは日米の文化や国民性の違いを反映しているように思われるのです。即ち、AAは「自我を捨てて大いなるものに委ねること」を目指します。いわば「自力本願」から「他力本願」への転回です。これに対して断酒会は「自我の強化」を目指しているように見えます。これは「他力本願」から「自力本願」への転回です。
或いはこうも言えるでしょう。AAでは「無理になった自立」をやめて「健康な依存」を手に入れることを、断酒会では「病理的な依存」をやめて「一定の自立」を達成することを目指している、と。
このように、現象的には方向性が正反対にも見える両者ですが、「無理になった自立」と「病理的な依存」が、或いは「健康な依存」と「一定の自立」が、それぞれ表裏を成すものだと気づくと、結局は同じ方向を向いていることが分かります。
(この項は2020.01.05作成)
|


| 第11節 オープン・ダイアローグ 当初はこの章にオープンダイアローグも含めておこうと思ったのですが、おまけのページの五つ目(第ⅩⅥ章)に載せてしまいましたので、そちらを参照して下さい。 |

第12節 まとめ :「治療」とは
最後に、改めて「治療」とは何かということについて整理しておきましょう。筆者が最近ようやく辿り着いた答えは、とてもシンプルにこうです。
「 治療とは、ヨシヨシしながら繋げることだ 」
「ヨシヨシする」とは、何か不快な体験(欲求不満、葛藤、怒りや悲しみ、無力感、等々)をしていて、その体験とそれを体験している自分を丸ごと「こんなの嫌だ‼」と投げ出そうとしているのを「ヨシ」即ち「そのままで善し」として共に抱えること、更には主体的努力に対して、それをきちんと評価し褒めることです。このことを通して、嫌な事を抱える力が育ち、能動的主体としての自信、健康な自己愛が育まれていきます。
かつてアレクサンダー,F.という人が、治療者の(概ね健康な)人格と触れ合うことによる「修正感情体験」を治療機序の一つとして提唱し、古典的な精神分析家達の批判を浴びたことがありましたが、その主張はより洗練されて自己心理学や対人関係論学派に受け継がれているようです。「ヨシヨシすること」は、その具体的な作業内容を示しています。
次の「繋げる」というのは、無意識を意識に、感情を論理に、過去を現在に、自己を他者に、個人を社会に、というように様々なものを結びつけることです。
筆者の師、故辻悟先生は、治療のエッセンスを当初①共感②共検討③対決(直面化confrontation)と定式化されていましたが、晩年には③を「決断を一人にしないこと」と修正されています。そして「ヨシヨシ」と抱えることの重要性を繰り返し強調されていました。
辻先生の①~③と「ヨシヨシしながら繋げること」は一見ずいぶん異なっているように見えます。しかし、①の共感は自己と他者が繋がることですし、その為には病理の理解が必要で、病理は無意識/感情/過去に根差しており、それを「理解する」とは意識化し論理の光を当て今ここに繋げることです。それらを共に探っていくのが②の共検討であり、③の決断(行動)に向けて励ますことは、現実の社会に繋げることであり、それにはやってみたことを評価し褒めることが不可欠です。
ですから、「治療とは、ヨシヨシしながら繋げることだ」という定式化は、辻先生の抽出された治療のエッセンスを別の角度からまとめたものと言えます。
更に、この定式化は精神療法だけでなく、脳と薬とを繋げること(薬物療法)、患者と治療とを繋げること(システムとしての精神医療の提供)をも包摂しています。勿論それらが無条件に善であるとか必須だとかと言うのでは決してありませんが…
(この項は2020.01.02作成)
|

|
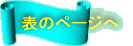 |

   |
|
|