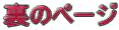 |
| 第Ⅳ章 精神・心理臨床に於ける問題事象の理解モデル |
|
冒頭にも記しましたように、
「正統的」精神医学は自然科学の一員たらんとして、
精神・心理臨床に於ける問題事象を極力「脳の故障/障碍」の結果と見なし、
その故障/障碍を特定すべく励んでいます。
脳の研究者の方々が
そのような見通しの下に研究に精を出される
ことを別段とやかく言うつもりはありません。しかしながら、
実験によって検証できるのは、実は「仮説の誤り」に限られます。
「仮説の正しさ」は直接には検証できず、他のあらゆる可能性を否定して
いって初めて、控えめに「その仮説は恐らく正しいだろう」と言い得るのです。
今尚そのような十分な検証に耐えるだけの成果が上がっていないにもかかわらず、
いわば「見通し」が既に「事実」であるかのように一人歩きしてはいないでしょうか?
私達はその「他の可能性」を探りましょう。この章では、
「脳の故障/障碍」以外の水準から、
精神・心理臨床に於ける問題事象が
どこまで説明可能であるか
を考察します。
無論、
ここでの議論もまた、
殆ど実証不可能なものです (^ ^;) |
かつて
「不登校」についてまとめていた時に、
ウィニコットの「偽りの自己」論に
行き当たりました。
(『思春期青年期の不登校(第1報)精神病理学的考察』
大阪府立公衛研所報第29号精神衛生編,1991)
「不登校」の中には、
中核的と思われる「空間状況恐怖」
から「対人恐怖」「思春期妄想症」
までの広い病態水準が含まれていましたが、
「偽りの自己」モデルはそれら全てを
共通の枠組みで
考えることを可能にしてくれました。
更に筆者は、
外来で出会う「うつ」や「統合失調症」の
患者さんの理解にもこのモデルが
有用であることを実感し、
「健康」から「病気(精神病)」までを、
「偽りの自己」という枠組みのヴァリエーション
としてモデル化し得ると考えるに
至りました。
実のところ
ウィニコットの「偽りの自己」は
勝れて臨床実践的な概念で、
それは
「分析することができるのは本当の自己だけである。
偽りの自己を分析していっても、つまり
内在化された環境に過ぎないものを分析していっても、
それは失望に終わるだけであろう。」
という彼の記述に、
端的に表現されています。
当時は、この警句の意味がまだ十分に
分かってはいなかったのですが…f(^_^;) |
[重要な補足]心の実相―モデルを越えて―
ここに「モデル」で示されたものは、実は本当の心ではありません。本当の心は、その人の主体そのもので、決してこのように「モデル」として客体化できないのです。
それは、「本当の」とか「偽りの」とか区別されることもありませんし、何らかの操作の対象とされることもありません。
それは形成されることもどこかへ行ってしまうこともなく、常に既にはたらいています。ただ、人はそれに気づかないということがあるだけです。そして、ここに示しました「モデル」は、その気づかない有様の、かなり大雑把な可視化の試みに過ぎないのです。
本当の心、自分の主体そのもののはたらきに気づくことができれば、ここに示しました「モデル」はもはや不要となります v(^-^)
|
1) 原(体験)心性 primal mind
まず最初に、第Ⅱ章で既に触れた「原(体験)心性」についておさらいしておきましょう。これは、人間が持って生まれた心性であり、胎児期~新生児期、つまり子宮内生活~誕生前後の赤ん坊が生きているであろう心性です。
「原(体験)心性」という語はいかにも専門用語然としているので、筆者は治療場面では専ら持って生まれた赤ちゃん(赤ん坊)のこころと表現しています。 |
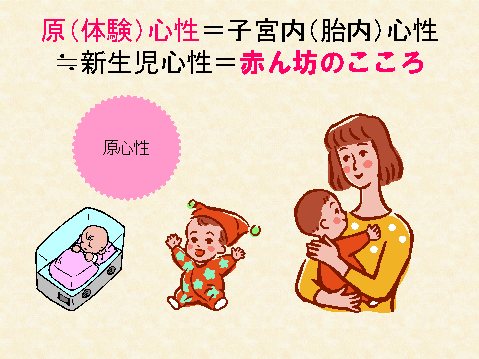
想像力を働かせれば分かる事ですが、この心性は次のような構造的特性と法則性を有しています。
① 内外(自他)の区別が無い ∴空間や状況=自分
② 受動的(受け身)である⇒感じたり思っているだけ
③ 今ここに在るものが全て(体験の直接性)⇒述語的状況性の支配
④ 状況の持続によりかかる(馴染みの法則)
⑤ ポジティヴな事象に一体化し、ネガティヴな事象は異常視し
排斥し遠ざかろうとする(フロイトFreud,S.の快-不快原則)
⑥ 問題意識を持ちえない
⑦ サイレントに終生活動し続ける |
2) 「一次ナルシシズム(自己愛)」と欲求不満
上述の「原体験心性」は、実はかつてフロイトFreud,S.がゲオルク・グロデックGroddeck,G.に倣って[グロデックはニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche)に倣って]「エス」と名づけたものと別のものではないでしょう。
ドイツ語の「エス」Es は、英語のit(それ)に相当し、ドイツ語でも英語でも、天候などを表す場合に「仮の主語」として用いられます。グロデックやフロイトは、心の無意識的な深層が、主体として名指し得ない(つまり、主語とはなり得ない)性質のものであることを的確に見抜き、仕方無しに「それ」と名づけたわけです。
従って当然のことではありますが、「原体験心性」の諸特性は、フロイトFreud,S.が「一次ナルシシズム」primary narcissismと呼んだものと重なっています。そしてフロイトは、精神病をこの心性への退行だと考えていました。
さて、原体験心性の上に挙げたような性質から、赤ん坊は「何でも思うようになる」と思っています。「何でも」と言うのは、自他の区別が無いからであり、「思うようになる」と言うのは、「思っているだけ=思う事が全て」だからです。
しかし、実際の生活ではそうは行きません。お母さん(養育者)がどんなに頑張っても、赤ん坊のニーズを100%満たすことはできません。そして赤ん坊は欲求不満を体験します。通常、赤ん坊はそれを自分の中に置いておくことができません。そこで、むずかったり、泣き喚いたりして外部へ放り出すことになります。 |
3) 養育環境の赤ん坊への適応がうまくいかなかった場合
まず、心の成長が不幸にしてうまくいかない場合について見てみましょう。これは様々な事情から、赤ん坊●が心の栄養(これは一般に「親が子に注ぐ愛情」と抽象的に言われるものでしょうが、具体的には赤ん坊の泣く様子から空腹を察知しての授乳に見られるように「赤ん坊の状態に気配りし、あまり大きな不快感を与え続けない」「赤ん坊のちょっとした達成を喜び褒め上げる」といった類の事でしょう)を十分にもらうことができず、遠ざけようとした不快な思い●が誰にも抱えられること無く放置されたり、養育者側に生じた不快な思い●が赤ん坊側に「お前のせいだ!」と投げ投げ返されたり↓することが繰り返されることによって生ずると思われます(下図左)。
EMDRの創始者シャピロShapiro,F.は、死に直面するような狭義の心的外傷を大文字のTのTraumaとし、それに対して、さして目立たなくとも日常的に自尊心を傷つけられたり無力感や劣等感や無価値感を植えつけられたりするような出来事を小文字のtのtraumaと呼んで、後者もまた一定の精神病理の源たり得る、と主張しています。
これらの区別を念頭に置きますと、PTSDの研究者ハーマンHerman,J.が単純型PTSDと呼んだものは、この大文字のTのTraumaに基く後遺症で、それに対して複雑型PTSDと呼んだものは0~複数の大文字のTのTraumaと無数の小文字のtのtraumaの後遺症だと言えます。
Trauma ⇒ 単純型PTSD
(Trauma)+trauma+trauma+…… ⇒ 複雑型PTSD
この時、赤ん坊は健康な自己愛(「自分は世界に受け容れられている」「自分は信用できる」「自分は価値のある存在である」などの自己肯定的思い)を育むことができず、専ら自分を守るという機能を発達させ「心の鎧」を作ります(下図右)。この「心の鎧」は、実のところ原(体験)心性に支配されており、自分が困るということ、葛藤するということをできるだけ回避し、問題はことごとく自分以外の処に位置づけようとします(away化)。
[註]下図の右で「心無い対象」と書きましたが、これは「外界の対象が結果的に子供にとっての心無い対象となってしまう」という意味で、決して現実の養育者を誹謗しているのではありません。
「心の鎧」の性能、即ち「問題をaway化するの能力」には、様々な程度があります。最も性能が貧弱な場合には問題に圧倒されて立ち往生するだけ(⇒カタトニィ)かも知れませんし、少し性能が良くなれば適当に外在化して「幻覚妄想」を形成するかも知れません(⇒精神病)。もっと高性能であれば、周囲の現実の中からうまい受け皿を見つけて、そこにうまくくっつけることでしょう(⇒パーソナリティ障碍)。
また近年では、心的外傷がしばしば「解離」という事態をもたらすことも再発見されています。つまり、体験の辛さが心の許容度を上回る場合、その体験は意識の連続体から切り離され、当面の間「隔離保存」されるのです(第3節参照)。そのようにして隔離保存されたものが「心的外傷」と呼ばれることになるのですが、それは主に、その体験をもたらした対象との関係状況から成っています。
下図では、原心性●が「心の鎧」○を支配しているという事情を、原心性●と「心の鎧」○を同心円で描くことによって表現してみました。
また、「分割/解離」は殆ど目立たない場合も少なくなく、あっても様々な強度が存在するようですので、それらを白い実線や点線で表しました。
「心の鎧」のaway化機能の内で最も効果的なのは、言葉を操る機能です。フランスの精神分析家ジャック・ラカンLacan,J.はいみじくも「語りは騙りである」という有名な指摘を行っていますが、特に語りが騙りになってしまうのは、言葉がaway化の為に駆使される場合です。 |
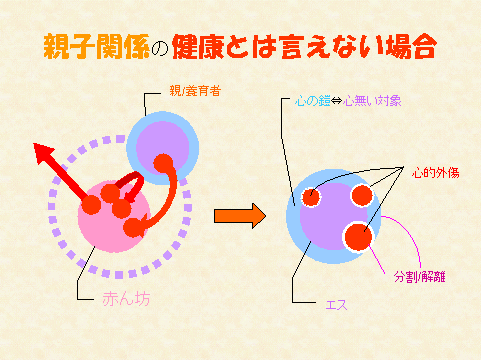
幼児虐待に関する最近の研究では、
被虐待児に於いては、海馬などの萎縮が認められるそうです。
幼少期に強いストレスを受けると、ストレス・ホルモン(コルチゾール)の分泌亢進を介して
海馬の神経発達遺伝子の発現が抑制され、神経栄養因子が十分に増えず、
海馬のシナプス形成が妨げられて、海馬体積の減少を伴う
ストレス脆弱性をもたらす、とも
言われています。
つまり、
脳の発育異常は、
遺伝や胎内環境などの先天的要因に限らず、
後天的要因でも起こり得る、
ということです。
[補足]
最近たまたま、
赤ん坊の心(原体験領域)の大半が
外傷的対象関係体験で埋まってしまったような方々に
何人か続けてお会いしました(敢えて図示すれば下図のようでしょうか)。
そのような場合、恐怖や怒りといった強烈な感情さえ、
ご本人には全く感じられないようです。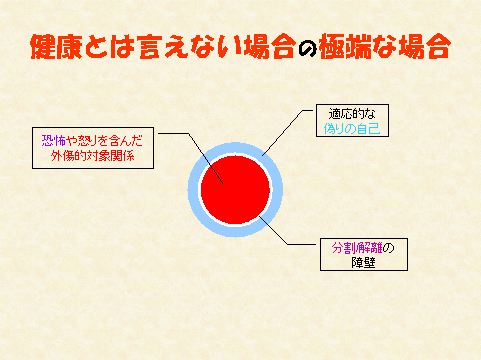
この在り方は、
案外安定していますが、
時に分割/解離の障壁が崩れ、
怒りが突発的に噴出することもあるようです。
4) 養育環境の赤ん坊への適応(「こころのお世話」)がうまくいった場合
次に、心の成長がうまくいく場合です。当然の事ながら、この方が事情は些か精妙です。この場合、赤ん坊は自らが常に歓迎されていると感じ、健康な自己愛(自己肯定感、自己信頼感、自尊心など)を発達させます。赤ん坊が遠ざけようとした不快な思いや、養育者側に生じた不快な思いは、ひとまず養育者によって受け止められ抱えられます。そうして、しばしば赤ん坊に役立つ形で返されます(下図)。そのおかげで、赤ん坊は殊更自分を守ろうとする必要も無く、ありのままで居れます。
同じ事を「愛情」と「理解」という言葉を用いてもう少し別の言い方をしてみましょう。するとこうなります。
即ち、この「うまくいった場合」には、親は赤ん坊~子供と言えども一個の人格/主体であると捉えています。もちろんまだ子供の主体は十全には生まれていません。しかし、親はそれが既にそこにあるかのように慎重に配慮しながら扱うのです。それは「理解しようと努力する姿勢を伴った愛情」です。必ずしも子供の心が十分に理解できなくてもよいのです。理解できなくても、嫌になって投げ出すのではなく、理解しようと努力しつつそこに共に居る、ということが大切なのです。
このような、子供の自己(主体性)を喚起し支持する養育者の機能のことを、英国の小児科医で精神分析家のウィニコットWinnicott,D.W.は「ほどよい(まあまあの)母親」good enough motherと表現していますし、合州国の精神分析家ハインツ・コフートKohut,H.はもう少し抽象して「自己対象」selfobjectと概念化し、それに対する子供の体験を「自己対象体験」と名づけています。
そして、こういう事の繰り返しから、子供はいつしか苦痛や葛藤を抱える養育者の機能を取り入れて身につけ、更に合理的客観的に考え判断する機能(いわゆる自我の自律的機能)を発達させて行くのです。
(このような心的装置をフロイトFreud,S.に倣って「自我(+超自我)」と言っておいてもよいのですが、抱える機能を強調して“containing-self”と呼んでもよいでしょう。)
下図では、原心性(エス)●からの自我・超自我複合体●の自律性を強調する為に、エス●と自我・超自我複合体●の中心をずらせて表現しています。
このような養育者の姿勢を私達は簡潔に何と呼べば良いでしょう?筆者は患者さんとの実際の遣り取りから、これを「からだのお世話」との違いを強調して、「こころのお世話」と呼ぶのが、使い勝手が良いようだと感じています(「心のケア」と言うと、語としては同じ意味ですが、幾分抽象的でしっくりこないし、災害時の救援活動を連想してしまいますから…)。尚、「お世話」という言葉を筆者は、熱心な統合失調症治療者でクライン派精神分析家の東中園聰氏の語りからいつの間にか取り入れていた、と思われることを付言しておきます。 |
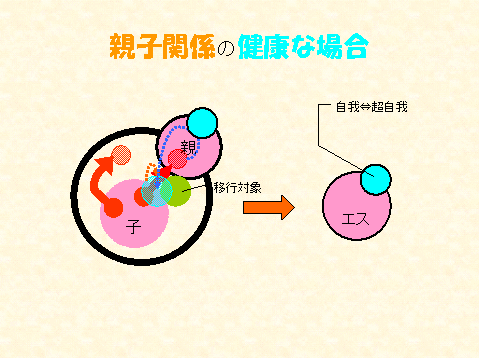
自我(内的自己)と超自我(内的対象)は
その発生の時点から既に常に
それぞれが単独で存在するのではなく、
対(つい)として存在しており
それらが一つ(或いは複数)の複合体を
成している、と考えられます。
それをここでは、「自我・超自我複合体」
と呼んでおきました。
なお、
健康であればあるほど、
「自我・超自我複合体」は
複数のものがバラバラに存在するのではなく、
緩(ゆる)やかにではあってもまとめられている
であろうことは、言うまでもありません。
ここから翻(ひるがえ)って、
先の、心の成長が不幸にしてうまくいかなかった場合には、
単数へのまとまりを当然の事として期待することはできない
こともまた、言うまでもないでしょう。
[補足1]
上の模式図が
フロイト先生の提示された
それと少々異なっていることは、余り
気にしないで頂けると幸いです。どうせ直接には
目に見えない領域のお話ですから、筆者が臨床的に
有用だと感じているまとめ方を提示したまでですので…ただ、
この違いは、意識から出発して無意識を発見したFreud,S.と、
その発見を前提に無意識(原体験)の方から再構成した
筆者らとの違いに起因しているのかも
知れません。
Freud,S.は、超自我を、
エス的幻想によって加工された蒼古的親イマーゴ
を核とした精神内界的審級とし、更にそれは結果的に
親の超自我部分をあたかも文化的遺伝子のように
受け継いで行くものであると見ていました。
それ故にFreud,S.の模式図でも、
超自我は自我と並んで
エスと外界(の知覚)とを
橋渡しするような位置に描かれています。
(それにしても、フロイト先生の模式図では、
まだまだ自我が大きくてエスは控え目ですね (^_^;))
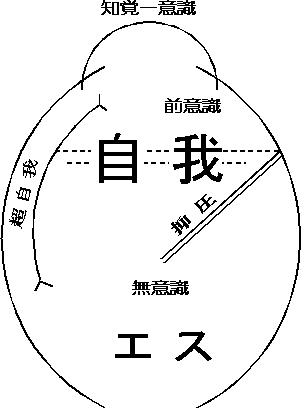
Freud,S.による「心的人格の構造関係」の図
(『精神分析入門(続)』第31講,1933)
[補足2]「主体」と「自我」
ごく大雑把には、「主体」を客体化したものが「自我」だ、とひとまず言えます。しかし、厳密にはそうは言えません。「主体」を「客体化する」ということ自体が絶対的な矛盾であり、不可能だからです。
フロイトは、ドイツ観念論哲学の伝統に違わず、ドイツ語の“(das)Ich”即ち「私」という一人称単数をそのまま「自我」という術語として使用していました。この事実を尊重すれば、「自我/私」は言語的コミュニケーションの空間の中でこそ成立している「主体の代理物(エージェント)」だと言えます。
この言語的コミュニケーションにも二つの次元を区別することができます。一つは排他的二者関係(dual)の次元で、「我‐汝」が対峙する境域です。フランスの精神分析家ラカンLacan,J.は、この境域が成立する瞬間を「鏡像段階」として描出し、「自我」moiは相手の瞳に映った(相手が見た/相手に見させた)自分のイメージに過ぎない、と主張しました。もう一つは三者的公的関係水準で、同じくラカンはその三者的公共性を保証する絶対的他者を措定して「大文字の他者」l'Autreと名づけ、「主体」(S)はそれに向かいつつ決して到達せずに横道(自我)に逸(そ)れてしまうことを指摘しました。
他方、英国でフロイトの著作を英訳する際に(より医学用語らしくという意図からだったようですが) “(das)Ich”には英語の“I”ではなくラテン語の“ego”が当てられました。恐らくそれによって「自我」は一層実体化(客体化)され、ついにはハルトマンHartmann,H.によって「自我装置」ego_apparatusと呼ばれるようになります。そしてそのような捉え方は「精神分析的自我心理学」としてアメリカの精神分析諸派の中で主流派を形成したのみならず、認知機能や脳機能の実証的研究とも親和性があった為、アメリカでは精神医学の基礎学問の一つと見做されるようになりました。
因(ちな)みに、これらの流れは歴史的には、アメリカ流自我心理学を激しく非難したラカンが国際精神分析協会から破門され、他方の自我心理学的精神分析も関係論的精神分析やナラティヴな(間主体的な)方法論に取って代わられ斜陽化している、という形で落着しつつあるようです。
尚、先に原体験領域から分化してくる機能部分を「自我と超自我」ではなく「自我・超自我複合体」と考えるべきことを述べていますが、実はここに更に「主体」を加えなければならないでしょう。この「主体」は、人生の最初期には原心性(エス)そのものでしょうが、様々な能力が発達してくるにつれ流動的で掴み処の無いものとなるでしょう。そしてそうだとすると、ここで見ている「健康な」人間の心は、より詳細には「原体験領域」と、「主体\自我」「自我・超自我」という垂直と水平の二つの二重構造から成り立っている、と言えましょう。 |
5) 動的二重構造Dynamic Double Structure
以上、便宜上二つの極端な場合に分けて述べましたが、治療的関与の経験からは、実際には二つの構造は単独で存在する実体ではないように思われます。(例えば H2O+CO2⇌H++HCO3- といった化学反応のように)人間の心はすべからくこれら二つの構造の混合状態であり、二つの構造の間を時と場合によって揺れ動いているものだと考えられます。
完璧な養育が現実にはあり得ない以上、これは当然の事でしょう。そして、「健康」wellnessと「病気」illnessは相対的なものでしかなく、平衡がより左辺に偏っていれば「病的」とされ、より右辺に偏っていれば「健康」とされるのでしょう(下図)。
「心の鎧」の性能が貧弱なほど、また自己の存在を脅かす環境的圧力が強ければ強いほど、平衡は左辺に偏るものと考えられます。 |
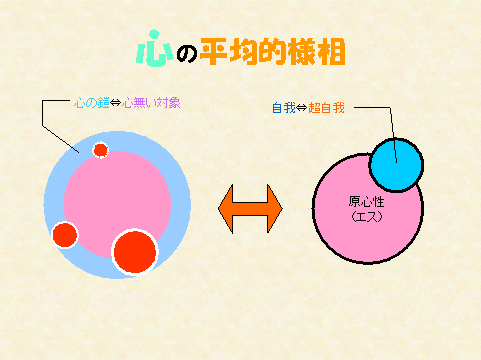
Winnicott,D.W.の
「本当の自己 true self / 偽りの自己 false self」の議論では、
自我心理学的な「自律的自我」は「偽りの自己の健康な場合」とされています。
それは上の図では、右辺の「自我」に相当します。そして
左辺の「心の鎧」は「偽りの自己の健康とは言えない場合」つまり
「原心性(エス)に支配された偽りの自己」だ
ということになります。
「心の鎧」という言葉は、患者さんやご家族に説明する際に伝わり易かったので採用しましたが、
例えば「偽我 pseudo-ego」とでもすれば、
「偽我(ギガ)」と「自我(ジガ)」でなかなか語呂も
良かったかも知れません f(^-^;)
実はFreud,S.は、
まず『本能とその運命』(1915)に於いて
一次ナルシシズム(=原体験心性)に引き続く自我の発達に関して
知覚をつかさどる「現実自我」real egoと
快感原則に支配された「快感自我」pleasure egoとを
既に論じ分けています。そして更に、その最晩年には
「自我の分裂」Ichspaltungについて語っています。
それによると
超自我やエスとの葛藤からの自立性を持った自我(Hartmann,H.の「自律的自我」)は
現実との関わりを保ち、
他方の自我は現実から離反しています(「現実から離反した自我」)。
そして彼は、
① どちらか優勢な方が意識に現れ、劣勢な方は無意識に沈んでいる、
②「現実から離反した自我」が「自律的自我」よりも優勢となった場合が精神病である、
と考えたようです。
(この部分、小此木啓吾著『現代の精神分析―フロイトからフロイト以後へ―』
講談社学術文庫(2002)を参照しました。)
だとすれば、
上記右辺の「自我(+超自我)」は「自律的自我(+超自我)」に、
そして左辺の「心の鎧(+心無い対象)」は「現実から離反した自我(+幻想的対象)」に
相当します。
また、
Klein,M.-Bion,W.R.の概念モデルに拠れば、
上の図はまさに Ps(妄想分裂ポジション)⇔D(抑鬱ポジション)に相当します。
更にまた、
Bion,W.R.-Rosenfeld,H.の
「人格の精神病部分 psychotic part /人格の非精神病部分 non-psychotic part」の議論は、
上図で、「心の鎧」が貧弱でせいぜい幻覚妄想を作る程度のものの場合だと考えられます。
その場合、左辺が「精神病部分」で右辺が「非精神病部分」だということになります。
元々万人に存在する
とされていた「精神病部分」が、
クライン派の論文を見ていても、いつの間にか
精神病者に固有のもののように扱われていることを、
かねがね不思議に思っていましたが、
《「心の鎧」がどれほど高性能でも精神病的破綻は生じ得ることから、
万人に存在する上図左辺は「精神病部分」と同一視され易いのですが、
それが真に「精神病部分」と呼ぶに相応(ふさわ)しいのは、
「心の鎧」が相当に貧弱な場合に限定される》
と考えれば、納得することができます。
更にまた、
早期にフロイトと袂を分かち、
「集合無意識」に注目することで「元型」などの概念化を行い、
「分析心理学」という独自の体系を築いた有名なカール・グスタフ・ユングJung,C.G.は、
無意識にこそ人格の中心となる「自己」Selfが存在することを見出しましたが、
ユング派でかつ発達を考慮するロンドン学派に近いとされる
ドナルド・カルシェッドKalsched,D.は、
その「自己」の暗黒面として、
トラウマ(心的外傷)を負った人に於いて、
その人(personal spirit)をそれ以上傷つけないように現実から引き離してでも守る為に
元型として圧倒的なヌミノース的な力を振るう「自己」を特に
元型的「自己ケア・システム」と呼んでいますが、
それは「ダイモン的表象」と対になっています。
以上のお話を整理すると下の表のようになり、
各論者はそれぞれ微妙に強調点が異なるものの、
基本的な認識はそう大きくは違わないことが分かります。
| 研究者 |
左辺 |
右辺 |
| 辻+筆者 |
原心性 +
心の鎧+心無い対象 |
原心性 +
主体的自己+法(ダールマ) |
Freud,S.
(Hartmann,H.) |
エス +
快感自我+幻想的対象 |
エス +
現実自我(自律的自我)+超自我 |
Klein,M.
Bion,W.R. |
妄想-分裂ポジション |
抑鬱ポジション |
Bion,W.R.
Rosenfeld,H. |
人格の精神病部分 |
人格の非精神病部分 |
| Winnicott,D.W. |
真の自己 +
偽りの自己の不健康な場合 |
真の自己 +
偽りの自己の健康な場合 |
Jung,C.G.
Kalsched,D. |
自己ケア・システム+
自己に同一化した自我
+ダイモン的表象 |
自己+
人間的自我+親イマーゴ |
なお、
Rosenfeld,H.-Steiner,J.らの破壊的な
「自己愛構造体narcissistic organization/病理的組織化pathological organization」は、
自己愛的万能感に満ちた躁的態勢が固定化したもの、或いは
天国のような理想化された安全地帯として
描き出されていますが、
詰るところ、
上図左辺Ps position(妄想分裂ポジション)の「心の鎧」が
極めて有効に機能している場合のことを言っているに過ぎないように
筆者には思われます。
上図をもう少しダイナミックに表示してみました。
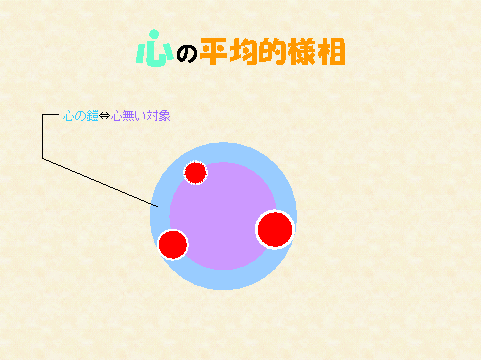 |
[補足3]「否定のモーメント」
「否定のモーメント」というのは、原体験心性に基いて、ネガティヴな体験、更にはその体験をしている自己存在までをも否定しようとする主体の活動です。臨床像としての抑鬱と密接に関連しています(この抑鬱は、上述の「抑鬱ポジション」の「抑鬱」とは似て非なるものです;臨床像としての抑鬱はむしろ、「抑鬱ポジション」の「抑鬱」をネガティヴな体験として否定するところに生じています)。 |
[補足4]「心の鎧」の二つのモード
原体験心性に支配され、away化の防衛を行う「心の鎧」ですが、それにも大きく二つのやり方があるようです。
①内向モード:退避/引き籠り/内閉といった様相で示されるやり方です。相手が圧倒的に強大だと体験された時には、このやり方になり易いのではないでしょうか。この場合「否定のモーメント」は内に深くしまい込まれます。
合州国のトーマス・オグデンOgden,T.H.という精神分析家は、クラインの後を継いで自閉症の精神分析治療に取り組んだ英国のビック、メルツァー、タスティン等の研究を発展させて、「自閉-接触(膚接)ポジション(autistic-contiguous position)」という心理構造を提出しています。彼によればこのポジションは、「体験に意味を与える最も原始的なモードと相応するもの」であり「自己の体験世界が、感覚体験、特に肌の表面での感覚の体系に基礎を置いている心理構造」です(『精神分析の第三主体』邦訳194頁)。
―この自閉-接触モードに於いては、主たる不安は、一貫した自己の体験の根本となるものが依拠している感覚上の境界が感じられなくなること(境界の喪失)である。/人はしばしば「第二の皮膚形成second skin formation」(Bick,E.1968,1986)によってこの種の不安の防衛を行う。(邦訳194頁)
―リズムがあることと(特に皮膚表面での)感覚的な接触の体験が、存在することbeingの連続性についての基本感覚となるのである。(邦訳67頁)
オグデンはこの「自閉-接触ポジション」を、クラインの「妄想-分裂ポジション」「抑鬱ポジション」と弁証法的関係にある第3のポジションと位置づけていますが、ここで言う内向モードが非常に極端な形になっていて、生きた対象との関係や対人関係から全面的に撤退したものとなっている場合である、と見做すこともできます。
しかし、「自閉-接触ポジション」の「生きた対象との関係や対人関係からの全面的撤退」という様態はもはや、ここで言う《away化の防衛を行う「心の鎧」》という範疇に入り難いのもまた事実です。やはり一つの独立した様態と見做すべきなのかも知れません。
②外向モード:攻撃/行動化/情動放出といった様相で示されるやり方です。相手に対し何某か反撃可能な場合には、このやり方になるでしょう。この場合には「否定のモーメント」は、周囲に向かって「違う!違う!」と否定の言辞を発し続けることによって表現されます。 |
前節では、
個体の心の成長発達
という視点から問題を見てきました。
この節では、同じ問題を養育の視点から見てみましょう。 |
0) 子育て失敗の諸要因
上述のような理解は、精神科の仕事をしていて思う「仕事のかなりの部分は、子育ての失敗(上述の「親子関係の健康とは言えない場合」が質的かつ/または量的に一定の限度を超えていたと思われる場合)の尻拭いだ」という実感に沿ったものです。
そのような子育ての失敗には二通りあって、
- 子供に過度の精神的ストレスを与えること、と
- 子供に余りにも精神的ストレスを与えないこと、です。
通常、前者は「虐待」と呼ばれ、後者は「過保護」と呼ばれています。
いずれも、子供の自我(主体性)の形成を妨げ、いずれも、子供の気持ちを十分に尊重することができない養育者(父かつ/または母)によってもたらされます(「過干渉」はいずれにも成り得ます)。
子供の気持ちを十分に尊重できないのにもまた原因があります。大まかに整理しますと、以下のようなところでしょうか。
①自然な共感能力が不十分である。
養育者(父かつ/または母)がいわゆる自閉症スペクトラム障碍である場合が典型的でしょうが、反社会性パーソナリティ障碍のように養育者自身がひどい虐待を受けて育っているために、自然な共感能力が損なわれている場合もあるでしょう。
或いは養育者(多くは父親)が未熟な自己愛の持ち主で共感性を欠く上に、職場でのストレスや家庭内の不満を持っておくことができず、家庭内暴力に至る場合もあるでしょう(家庭内暴力はそれ自体虐待であると見做されます)。また、幻覚妄想や抑鬱のような精神症状の増悪時に共感不全を呈する場合もあるでしょう。
②自然な共感能力は十分に持っているが、不安を抱えられないために、子供に関わることで自らの不安を解消しようとしてしまう。
境界パーソナリティ障碍のように、養育者(多くは母親)自身がその養育者との関係が健康なものでなかったために、自らの不安を抱えておくことができず、子供にその不安を移してそれに関わること(投影同一化)によって、自らの不安を解消しようする場合です。
③自然な共感能力は十分に持っているが、望まない出産のためにどうしても子供を愛せない。
「望まない出産」になる原因もまた複数あり得るでしょう。レイプや性的虐待による妊娠、若年者や未婚者の場合、妊娠後の不仲、等々です。これらの中には、72時間以内に飲めば有効な経口避妊薬や人工妊娠中絶などで技術的に回避可能な場合もあります。また、養育を乳児院などの施設や里親に託す、といった道もあるでしょう(但し、それらが常に良好な結果をもたらす、とは限らないようですが)。
④自然な共感能力も、不安を抱える力も十分に持っているが、それを支える環境に恵まれず、能力を発揮できない。
「恒産無ければ恒心無し」と言われるように、経済的困窮が心理的余裕の喪失をもたらし、その結果、子育ての失敗に至ることも多々あります。核家族や核分裂家族化、コミュニティの結びつきの希薄化などで、母子が孤立し易い、といった社会的状況も無視できないでしょう。
「虐待の世代間連鎖」が指摘されて久しいですが、既にお分かりのように、子育ての失敗はまた次の世代の子育ての失敗のリスクを高めます。そして多くの場合、社会経済的な生活水準はより低い方へとシフトします。単純化して言えば、子育ての失敗は拡大再生産されるのです。
結局のところ、これからの社会に於いては、善い悪いは別として、「子供は家庭で育てる」という考えから「子供は社会で育てる」という考えへと発想を転換して行かざるを得ないようにも思われます。
これらの情勢をこれ以上ここで扱うことは筆者の手に余りますので、この辺でやめておきます。 |
1) 心を理解することの難しさ
心(こころ)は、直接には見えません。私達はそれを、関わりの中で相手の表情や態度、言動から読み取らねばなりません。しかし、実はこういう言い方も正しくありません。これでは、《様々な徴候を詳細に観察し、過去のデータと照会する》といった方法で機械にも可能な事のようです。
私達が他人の心を真に理解するには、私達自身が同じような情緒/感情を自分自身の内に感じることができなければなりません。でなければそれは「共感」ではなく、まさに機械による「読み取り」と変わらなくなってしまいます。
ところで、私達が特に「共感を伴う理解」を必要とするのはどのような時でしょうか?どちらかと言えば、楽しい時よりも辛かったり悲しかったりする時ではないでしょうか?そうだとすれば、私達が他人の心に「共感を伴う理解」を持つ為には、「辛い」とか「悲しい」というネガティヴな情緒/感情を嫌がってすぐに消そうとせずに、自分自身の心の中に置いておくことができなければなりません。実はこれがなかなか難しいのです。
そもそも文明は、欲求や欲望がなるだけ即時に充足され、「辛い」思いや「悲しい」思いをしないことを目指して発展します(これは、ポジティヴな体験をもたらす対象/状況とは融合しようとし、ネガティヴな体験をもたらす対象/状況からは遠ざかろうとする原体験心性に起因しています。無論、その欲求や欲望が専ら一部の特権集団のそれであることで、しばしばより大きな不幸を招いては来ているのですが)。
少なくとも物の溢れた先進諸国では(格差の問題は依然存在するにせよ)「辛い」思いや「悲しい」思いは以前よりは忌避し得るものとなりつつあります。そして、それをより確実にする為に、周囲に溢れる様々な情報に拠ることになっています。
このような状況の中で、自分の心の中の「辛さ」「悲しさ」としっかりと向き合うこと、そのことによって心というものを理解することが、ますます困難になっていると思われます。 |
2) 「過保護・過干渉」の構造
「おまえのことを思ってしてるんだ」「あなたの為に言っているのよ」というのは、世の多くの親達のセリフです。そしてそれは、多くの場合(つまり明らかな虐待の場合を除けば)嘘ではありません。しかし、それでもそれが「過保護・過干渉」となり、子供の主体性を育み損ねてしまうことがあります。それは、親(養育者)が子供を一個の独立した主体と見ることができず、その心を独自のものとして思い遣ることができず、子供の考えや気持ちを自分自身の考えや気持ちと区別できていない場合です。親(養育者)が葛藤やそれに伴う苦痛を苦手として、忌避しようとしている場合にそうなります。⇒awayの構造
そのような場合に親(養育者)は、子供が困っていたり困りかけていたりすると、それを見て自分の内に生じた不安や心配を(それは自分の中のものなので、ひとまず自分がそれをどう受け止めるのかが問われているのに、その事に気づく間も無く)即座に消し去ろうとします。そしてその為に、そういう気持ちを感ずる契機となった外界の出来事(この場合は子供の窮地またはその予期)に介入し、その事態を解消しようとしてしまいます。それがうまく行けば行くほど、子供は「困る」という体験を奪われ、いつまでも子供のままに留まるのです。
親(養育者)と子供とのこのような関係も、「健康とは言えない場合」の一つです(下図)。つまり、子供の内的事情(心=考えや気持ち)を結果的に無視した形でなされる親(養育者)の介入は、(あくまでも「結果的に」ですが)一種の「侵襲」となってしまうのです。
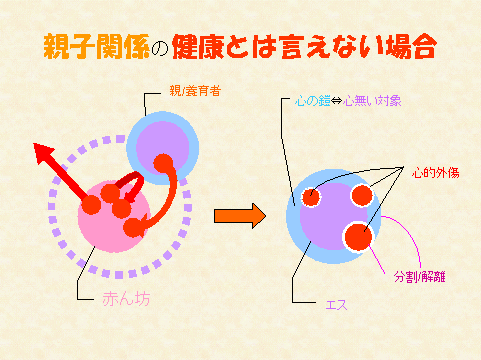
|
3) 「放任」と「虐待」
「放任」と「虐待」も、親(養育者)が葛藤やそれに伴う苦痛を苦手として、忌避しようとしている場合に生じます。勿論これも上図の「親子関係の健康とは言えない場合」に含まれます。
「放任」は、子供と関わると親の側に必然的に生じてくる心身の負担、時間的制約から逃れる為に最も有効な方法です。TVやゲームに子守をさせることは、個々の家庭の事情を超えて、今や社会の趨勢になっていると言えます(ゲーム業界は我国の巨大な産業です)。
「虐待」は、子供と関わると親の側に必然的に生じてくる心身の負担や、親自身の葛藤や欲求不満のはけ口を子供に求めることから生じます。
[補足]「犯人探し」の不毛
上記のような言い方をすると、「また親を責めている」と思われるかも知れません。しかし、親には親の事情があることも当然ながら承知しています。精神科臨床に於いては、「○○が悪い!」と「犯人探し」をすることは、アウェイの構造を強化するだけで不毛なことです。
大切なことは、対策を立て有効な対応を組む為に「とにかく事実を具によく見る」ということなのです。
虐待は一応、
①放任よりも極端に子供の世話を欠いた「ネグレクト(育児放棄)」、
②しばしば「躾だ」と主張される身体的暴行、
③性的悪戯や近親相姦などの性的虐待、そして
④子供に恐怖を植えつけたり自尊心を破壊するなどの精神的(心理的)虐待
の四つに分類されていますが、実際にはこれらいくつかが重複していることもままあります。
行政的には②の身体的暴行がしばしば傷害~傷害致死につながる為に重視されています。また①のネグレクトも、時に子供の生存に必要な最低限の条件(栄養、衛生など)をも欠くに至っていることがあり、注意を払われています。
しかし精神科臨床の立場からは、③の性的虐待は青年期以降に解離性障碍をもたらし易く、①のネグレクトや④の精神的虐待は思春期青年期以降に明らかとなる統合失調症やパーソナリティ障碍の要因の一つとも成り得、いずれも疾患/障碍の一次予防の観点から看過することはできません。 |
4) 子供が家族システムを維持しようとすること
子供はまだかなりの程度、自分の受け皿となっている周囲の家族と原体験的な融合関係にあります。つまり、「自分の事=家族の事」となっているのです。その為に、その受け皿である家族に何らかの葛藤が生じたり、崩壊の危機が訪れたりすると、それを自分の事として苦しみ、懸命に修復しようとします(無論この動きも、苦痛回避を希求する原体験心性に因っています)。
この修復への努力は意識的に行われることも有りますが、(なにぶん原体験心性が関与していますので)しばしば無意識的無自覚的に行われます。そうすると結果的に、何らかの問題行動なり“病理的”言動なりの形をとることとなり、家族療法で言うidentified patient(患者と見做された存在)が生まれます。そして、「患者」とその「症状」がしばしば家族を繋ぎ止め、家族システムを存続せしめるのです。 |
| 第1節で「養育環境の赤ん坊への適応がうまくいかなかった場合」に登場しました「心的外傷」は、その後どうなるのでしょうか。ここでは特に、生命を脅かされるような大トラウマ体験の運命について触れておきたいと思います。 |
1) 大トラウマ体験の「隔離保存」
主体がその時点では受け止めかねるような体験は、意識の連続体のようなものから一旦切り離され、しかるべき時まで隔離保存されるようです。これも、広い意味ではアウェイの機制だと言えますが、それを行う主体そのものの統合が損なわれる、という点では少し違ってもいるでしょう。
そのメカニズムは、歴史的に幾つかの名前で呼ばれています。
まず、精神分析の創始者フロイトは、彼が最も基本的と考えた「苦痛な感情体験とそれに関連した表象の意識からの追放」という防衛機制を「抑圧(suppression)」と呼びましたが、大トラウマ体験の場合には、狭義の反復強迫(下註)など、快原則に従う通常の「抑圧」ではうまく説明できない点があることも認め、「死の衝動」の存在を想定したりしました。また、晩年には「自我分裂(Ich-Spaltung/splitting of the ego)」という事態が在り得ることを渋々ながら認めています。
(註)反復強迫:本人に自覚の無いままに繰り返される特異な対人関係パターン。
フロイトは当初、この概念を「転移」現象に対して用いましたが、後には特に外傷的体験のような不快な事象が再現反復される場合について考究しましたので、「反復強迫」と言えばこの「不快な事象が再現反復される場合」を指すことが多いと思われます。
精神分析の領域で子供の分析に携わったメラニィ・クラインは、対象関係に着目して「良い対象関係を悪い対象関係から守る」機制として「分割(splitting)」という言葉を用いました。
更に、同じく対象関係に注目していたハインツ・コフートは、フロイト流の抑圧を「水平分割(horizontal splitting)」、クライン流の分割を「垂直分割(vertical splitting)」と見倣しています。
最後に、フロイトと同時代に活躍したピエール・ジャネは、「解離(dissociation)」を、防衛というよりももっと受動的な「統合の困難」という、一種の発達停止と捉えていました。
近年の「心的外傷-解離」論は、どちらかと言うとこのジャネの見方に近いようですが、防衛という側面も無視できないことはあります。 |
2) 大トラウマ体験の「回帰」
隔離された大トラウマ体験はそのまま消えてしまうことも変形されることもなく保存され、再体験される機会を常に窺っているように見えます。
フロイトが観察した狭義の反復強迫(運命的悲劇の繰り返しや繰り返される悪夢(外傷夢))や外傷体験のフラッシュ・バック、多重人格(解離性同一性障碍)で見られる「交代人格」といった形で、過去が臨場感を伴ってリアルに再現されるのです。
「過去の体験がそのまま変形されることもなく」と言うことには恐らく異論もあるでしょう。一般に、記憶というものはかなり変形されるものであることが知られています。
しかし、大トラウマ体験の記憶に関しましては、それが生じた発達段階に於ける認識能力による制約は当然受けるために、決して客観的に正確であるとは言えないでしょうが、一旦刻まれた記憶そのものはあまり変形を被っていないように思われます。
[補足]内的幻想による修飾
精神神経症の原因となる程度の「小トラウマ」につきましては、フロイトが見出しましたように、エディプス複合などの内的幻想による大幅な修飾を被っている場合も少なくないのでしょう。
|
3) 大トラウマ体験の「同化」
大トラウマ体験の回帰は、一種の自己治癒の試みとも考えられます。しかし、多くの場合、治癒は成就せずに空しく繰り返されてしまいます。
筆者はこれまでのところ、この大トラウマ体験を同化することは、かなり困難な作業である、と感じています。
しかし他方で、医療的関わりとしましては、この「同化」を目標とするよりも、より適応的な対処能力を身につけることを目標とする方が現実的であるし、それで十分に有用である、ともされているようです。 |
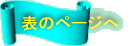 |
|
|
|
|