『はじめに』の「精神医学史概説」にも書きましたように、精神医学はこれまでにも何度かのパラダイム・シフトを経て来ています。そして今また、その知の基本的枠組み(パラダイム)が地殻変動とも言うべき大きな変化を起こしつつあります。
この変化は、精神医学の中心領野からの
①「統合失調症」研究に於ける「ストレス脆弱性」モデルの出現
に加えて、従来いずれも精神医学の周縁に位置していた二つの領域、
即ち
②大災害や犯罪被害などに対するメンタル・ヘルスの領域から出た「ストレス~トラウマ(心的外傷)~PTSD」といった概念群と不適切養育maltreatmentによる「複雑性PTSD~発達性トラウマ障碍」といった概念、逆境体験ACEsによる心身への広範な悪影響の調査
及び
③乳幼児~児童精神医学の領域から出た「反応性愛着障碍RAD:reactive attachment disorder」或は「早期関係性障碍relationship disturbances in early childhood」、そして「高機能発達障碍(下註)」という概念群
が広く受け容れられるようになったことによって齎されつつあります。
(註)このサイトでは、従来の「軽度発達障碍」に替えて「高機能発達障碍」という用語を使用しています。詳しくは、裏のページ『高機能発達障碍』を参照して下さい。 |
0.はじめに
まずは、「精神疾患」というものにまつわる根本的な問題に触れておきましょう。
1)「疾患」か「障碍」か、それとも「個性」か
近年注目されるようになった「高機能発達障碍」に関して、それを治療すべき「疾患」と考えるよりもむしろ「個性」と考え配慮すべきだ、という主張は一般向けの解説書などでは普通に見られます。
また、「性同一性障碍」gender identity disordersに関して、それを「障碍」と捉えるよりもむしろ「個性」と考え尊重すべきだ、という主張も徐々に受け容れられつつあるように見受けられます(この場合には「身体的性=生物学的性」と「精神的性=社会的性」の不一致そのものは「疾患」と見做され、外科的内分泌学的「治療」の対象とされています)。
以上二つの事例が示しているのは、「疾患の分類」どころか、そもそも「疾患」と見做すのか「障碍」と見做すのか、それとも「個性」と見做すのかということにも決定的な答えは無く、主にその時々の社会的情勢によって決している、という事実です。
これら三つの捉え方に伴う特徴を(簡略に過ぎることを承知で)整理しておきましょう。
|
疾患 |
障碍 |
個性 |
| 位置づけ |
一時的異常 |
持続的異常 |
正常 |
| 積極的治療 |
可能であれば(1)
対象となる |
原則として
対象とはならない |
対象とはならない |
| 福祉的保障 |
原則として
対象とはならない |
重症度に応じて
対象となる |
対象とはならない |
| 社会的受容 |
sick role(2)として
最も受容され易い |
ある程度受容され
つつあるか |
漸く受容の緒に
ついたところか |
(1) 積極的治療が不可能である「疾患」は、速やかに「障碍」に準ずる形で扱われるようになります。
(2) sick role(病んでいるという役割):「病人」はその病んでいるとされる間は日常の役割を一時的に免除され、「病人」という役割を与えられます。
2)「ストレス」概念について
「ストレス」という術語が日常用語となって既に久しく、また、専門用語である「心的外傷後ストレス障碍」にも「ストレス脆弱性」にも「ストレス」という術語が含まれています。
生理学者キャノン(Walter Bradford Cannon,1871-1945)、セリエ(Hans Selye, 1907-1982)らによって医学領域に齎されたこの「ストレス」という概念には、次のような性質があります。
①「こころ」と「からだ」をつなぐ概念である。―「ストレス」概念の有用な側面
ストレスをもたらすとされるストレッサーstressorには「物理化学的ストレッサー」と「心理社会的(認知的)ストレッサー」とがありますが、メンタル・ヘルス領域で問題となるのは勿論、後者の「心理社会的(認知的)ストレッサー」です。そしてそれは、「こころ」の領域で入力され、脳を含む「からだ」に生理的変化をもたらすのです。
この事は、たとえ第一義的に「身体疾患」であるとしても、精神的ケアを疎かにしてはいけないことを教えてくれます。
②「質より量」の概念である。―「ストレス」概念の不十分な側面
セリエの学説の画期的であったのは、様々に異なったストレッサーに曝された場合でも、共通した性質の生体反応が生ずることを示した点です。この事によって逆に、結果として生じた生体反応の強度を何かを指標として判定し、そのことによって質的に異なった様々なストレッサーを唯一つの尺度の上に並べることができるわけです(善い悪いは別として)。
本来、「心理社会的(認知的)ストレッサー」は或る意味を持ってその意味を通じて生体に働き掛けてくるのですが、ひとたび「ストレス」という言葉に翻訳されてしまいますと、そこにあった固有の意味は消去され忘却されてしまう危険性があります。
私達は、以下に検討します「心的外傷後ストレス障碍」や「ストレス脆弱性」という概念に於いても、上記特徴のプラス面とマイナス面が常に影を落としていることを見て取ることができるでしょう。
[「ストレス」概念に関する簡潔な紹介はここにあります。]
|
1.「高機能発達障碍」再考
――「防衛(の失敗)」か「先天的な中枢神経発達異常」か
それとも「特殊な適応的発達」か?――
私達は今日、アスペルガー症候群や高機能自閉症、学習障碍、注意欠陥/多動性障碍等をごく素朴に「高機能発達障碍」と呼んでいますが、果たしてそれらは全て「障碍」でしょうか?
1)生物学的原因論の限界
自閉症はかつて(力動精神医学全盛期には)、原初的破滅不安~分離不安への硬直的な(「甲殻的な」)防衛として理解されていました。しかし、この仮説は次第に省みられなくなっています。そして今日では、自閉症はもとより「高機能発達障碍」に関しても、多くの生物学的精神医学者が「脳の遺伝的潜在能」に「欠陥」を見出そうと努めています。
しかしながら大局的に見るならば、例外的な一部のケースを除いてこの生物学的戦略が正鵠を射ている可能性は低いのではないかと思われます。何故ならば、
①もしも、「高機能発達障碍」が実数として増えているのではなく、以前から一定の割合で存在したのだとすれば、そして、かつては「異常/障碍」と見做されず、例えば「ちょっと変わってる」くらいで済んでいたのだとすれば、「遺伝的潜在能」に「欠陥」を見出そうと努めるよりも、その前に、何故今日「高機能発達障碍」が「異常/障碍」として浮かび上がるようになって来たのか、ということを問うべきでしょう。
②もしも、「高機能発達障碍」が実数としても増えているのだとすれば、二つの可能性が考えられます。
一つは、その多くに「遺伝子レヴェルの変異」が存在するという可能性です。もしそうであれば、それは現代日本人に昨今「膨大な数の突然変異」が生じていることを意味します。いくら「環境汚染」等を勘案しても、それはちょっと考え難いのではないでしょうか。
もう一つは、遺伝子の発現のレヴェルでの変異が多発している可能性です(⇒エピジェネティクス)。近年、同じ遺伝子でも環境刺戟によって発現するしないが左右されることが分かってきています。この「環境」には、出生後の養育環境のみならず、胎生期からの胎内の環境も含まれています。そして、胎内の環境は母体の身体的状態はもとより、精神的状態からも少なからぬ影響を受けます。
遺伝的素質とこのような環境要因の関係に関する実証的解明は、未だ素描のようなレヴェルまでしかなされていないようですが、要するに遺伝子で全てが決まるのでは全くなく、環境からの刺激によって遺伝子の発現がコントロールされて神経細胞の分化が左右され、神経ネットワークの形成に関わる出生後の様々な学習体験にも影響を及ぼしていく、といったもののようです(「当然そうだろう」としか言いようのないお話ですが)。
この場合にも、個体に於ける遺伝的素因のみを探究することは、「木を見て森を見ず」的な対応になってしまうでしょう。
2)発達論的再検討
他方で、ここ数十年の間の母子を取り巻く環境の変化は歴然としています。地域コミュニティや家族の繋がりは崩壊して久しく、少なからぬ母親が孤立した中で、誰かに十分に不安を抱えられることなく妊娠から出産、子育てを行い、更に子供達は早くから人間的触れ合いよりもTVやゲームなどの情報機器に囲まれ、睡眠時間を奪われ過剰な知覚刺激に曝されて生活することが、半ば当たり前となっています。
既に脳の神経発達に関する研究からは、「汎用的な幼若脳が遺伝的潜在能と環境からの適切な刺激入力の相互作用によって、様々な機能を持ったモジュールの有機的システムへと特殊化して行く」[もう少し砕いて言えば、「元々はどのようにもなり得る(=汎用的な)未熟な脳が、遺伝的素質と環境からの適切な刺激との相互作用によって、様々な機能を持った部分組織(=モジュール)が有効に統合された脳へと仕上げられて行く」といったところです]という中枢神経発達(=精神発達)のイメージが語られています(まぁこれは、昔から一般に言われている「氏か育ちか」という二分法を「氏も育ちも」と言い換えたに過ぎないのですが…)。
このように、「高機能発達障碍」というのは決して単純な先天的中枢神経発達障碍などではなく、実際には幾分かの(多くは決定的ではない)先天的素質(下註)の上に、上記のような子供達を取り巻く環境のドラスティック(激烈)な変化が絡み合った、とても複雑な臨床事象です。その上に、虐待やいじめを受け易いことから来るいわゆる「二次障碍」が加わると、もうどうしようもなく複雑になるでしょう。
(註)このような先天的素質のことを杉山氏は最近、「発達凸凹」と呼んでおられます(『発達障碍のいま』講談社現代新書,2011年7月20日刊)。或は、愛着形成に必要なちょっとした能力発現の遅れと言っても良いのかも知れません。また、脳の進化論的な先祖返りのような場合も有るのかも知れません(例えば、瞬時に見たものを完璧に記憶してしまう反面、言語を自由に操ることのできないチンパンジーの脳に近いものを持って生まれるて来ることが稀に有っても不思議ではないのではないでしょうか?)
いわゆる定型発達が「適切な刺激入力との相互作用」を必要とすると言う時、それをもたらす環境は(恐らく一世代か二世代前の)人間的触れ合いと、(過剰な感覚刺激から守られた)適度な静穏さを前提としているでしょう。勿論昔だって、そのような理想的な状態であったことは稀だったでしょうが、それにしても現代の世相は余りにも理想からかけ離れ過ぎているのではないでしょうか。
そうだとすれば、現在増えつつある「高機能発達障碍」者は、そのような現代の変容した養育環境、即ち人間的触れ合いを欠いた過剰な感覚刺激との相互作用によって、そのような環境に適応的なものに特殊化した脳を持ったのだとは言えないでしょうか。そのように(恐らく人間の子供にとって苛酷な)現実に適応した彼らを「発達障碍」と呼ぶのは、いかにも失礼なことかも知れません (-_-;)
(註) 筆者はこれまで、自閉性障碍(いわゆるカナー型自閉症)については何らかの先天的要因が無視できないようだ、と考えていましたが、2015年春現在、その考えにも再考が必要だという考えに傾いています。
|
2.PTSDの再登場
PTSDは、近現代の大規模な戦闘、大規模自然災害、レイプ等の犯罪被害、家庭内暴力や虐待といった、およそ人間に降りかかる様々な災厄による精神的被害を可視化する画期的な概念として再登場しました(「再登場」と言っていますのは、この概念はフロイトやジャネの時代から存在する古くて新しい概念だからです)。
1)(単純simple)PTSD概念の射程
リニューアルされたPTSD概念がまず提示した視点は、
①生死に関わる体験は脳に痕跡的変化(これは強固な「学習」であるとも言えるでしょう)を惹き起こす。その変化は、類似の状況ないしその状況を連想させる刺激に対する極端な過敏さと、そのような状況ないし刺激に曝された時に最初の体験をリアルに想起する(フラッシュバックと呼ばれます)という結果をもたらす。
恐らくそれらは、自然界に於いては「同様の危険を逸早く察知して回避する」という自己保存の目的に適った仕組みではあるが、人間界に於いては更に人間の持つ思考力から「予期不安」を生じ、過剰な回避行動を惹き起こす為に、却って生活上の不利益をもたらしてしまう。
というものです。その後これに次の見解が付け加えられています。
②PTSDと呼ばれるそのような慢性的反応に関しても、実はその生じ易さに個体差が認められる。そして、その個体差自体、必ずしも先天的なものとは限らず、幼少期に受けた虐待や偶発的事故などの外傷的体験(それをここでは「原外傷体験」と呼んでおきます)に由来するものである可能性がある。
2)複雑性complex(複合型combined)PTSD概念の射程
更にジュディス・ハーマンJudith Lewis Hermanが指摘しています「複雑性PTSD」やビッセル・ヴァン・デア・コークBessel A. van der Kolkらが指摘しています「複合型PTSD」の場合、
③長期に亘り持続ないし反復された外傷的体験は、従来のPTSD(単純型PTSD)に見られる比較的限局された不安反応をもたらすに留まらず、その人のパーソナリティ(対人的社会的行動パターン)に深刻な影響を与える。
と言われています(この事は既に「強制収容所症候群」等に於いて確認されています)。
ひとたびこのような視点が得られますと、そのような目で子供の成育環境についても再吟味することができます。その時に留意すべきは、
a) 子供は大人に比べて世界が狭く限られており、苦痛に耐える力が弱く、魔術的に考え魔術的に自己防衛する。
b) 子供にとって養育者の存在は必須であり、養育者は絶対的で抵抗困難な存在である。
という点が大人の場合とは少々異なっている、という事実でしょう。これらの事情の為に、大人から見ればさほど外傷的とは思われない状況でも、子供にとっては極めて高度に外傷的である、ということがあり得るのです。
大人の場合、ナチスの強制収容所に於ける体験のように「長期に亘り持続ないし反復された外傷的体験」は一部の人々に人格の全面的退行(幼児返り)をもたらし、それは防衛的反応であってむしろ個人の精神(大人の部分)に保護的に働くようだ、と言われています(⇒「強制収容所症候群」)。
しかし、子供の場合には未だ守られるべき大人の人格は存在しておらず、外傷的体験の影響はその後の精神的発達(知的発達やパーソナリティの発達)に直接的に影響を及ぼすでしょう。そうだとすれば、
④「発達障碍」や「パーソナリティ障碍」や「ストレス脆弱性」と言われるものの成り立ちに関しては、成育歴に於ける養育環境側の失敗の影響を十分に詳細に吟味しなければならない。
と主張することが許されるでしょう。
(註)近年では、幼少期にストレスを受けると、ストレス・ホルモン(ヒトの場合はコルチゾール)の分泌亢進を介して海馬の神経発達遺伝子の発現が抑制されて、神経栄養因子が十分に増えず、海馬のシナプス形成を妨げ、海馬体積の減少を伴うストレス脆弱性をもたらす、とも言われています。
[補足1]「固着‐退行」とPTSD
「固着」fixationという概念はフロイトFreud,S.が、人間の発達上のある段階に「強過ぎる欲求充足や欲求不満を伴う非常に印象的な体験」が存在したことによって、その時点での体験モードが成長後もその個人の言動を強く支配し続けていることを記述する為に用いた概念です(フロイトは「その段階にリビードーが固着している」と表現しました/「リビードー」libidoというのは「流体(或いはアメーバ)のイメージで捉えられたエス(原体験心性)」だと思えばよいでしょう)。そして一般に、人は現在的に何かの困難に直面すると、その固着点まで退行(幼児返り)する、そしてそれは自然治癒の営みである、ともされました。
感覚が過度に鋭敏となり、微細な兆候からも過去の外傷的体験の「その時その場」に立ち返ってしまうフラッシュバックを伴う“PTSD”は、この「固着-退行」の非常に極端な場合、即ち「固着点」に於いて「生死に関わる外傷的事態」(原外傷体験)に曝された場合である、と言えます。フロイトは晩年、心的外傷体験を「心の刺激障壁(バリア)」が破損することと捉え、恐ろしい場面を繰り返し夢に見る「外傷夢」を「心の刺激障壁(バリア)」を修復しようとする営みであると考えていたようです。
DSM-Ⅲ以来「神経症」概念は解体され、それと共にフロイトに由来する神経症理論も等閑視されている感がありますが、PTSD概念の再登場は「固着‐退行」モデルの再評価を意味しているでしょう。
[補足2]発達性トラウマ障碍DTD(Developmental Trauma Disorder)
2013年3月に発表される予定のアメリカ精神医学会「診断と統計のマニュアル第5版(DSM-5)」の策定途上に提案されています幾つかの診断概念の中に「発達性トラウマ障碍DTD(Developmental Trauma Disorder)」というのがあるようです。最終的にこれがDSM-5の中に組み込まれるのかどうかは筆者の知るところではありませんが、たまたま目にした「モデル事例」を見る限りでは、思春期青年期に顕在化する非行や摂食障碍、自傷行為といった問題行動から、対人恐怖や幻覚妄想に至る多くの病態が、狭義の虐待はもちろん、さまざまな不幸を含み込んだ成育史上の問題に由来する、という発想からの提案のようです。
詳しい経緯も筆者には分かりかねますが、恐らくこれは複雑性(複合的)PTSDをより具体的に言い換えたものなのでしょう。
〔補足の補足〕
結局、DSM-5にはこのDTDは組み入れられませんでした。このことも含め、DSM-5は実に中途半端なもの(と言うよりも、益々妙なもの)になってしまったように思われます。今後も果てしなく改訂できるように、ローマ数字をアラビア数字に(つまり“Ⅴ”ではなく“5”に)したようですが…
|
3.「ストレス脆弱性」モデル再考
――「高機能発達障碍」も「原(心的)外傷~複雑性PTSD」も――
生物学的視点から精神疾患を解明できると信じて来た精神医学者達は、この間も尚精神疾患の生物学的「原因」探しを続けていました。そこに登場したのが、1980年のDSM‐Ⅲの公表に僅かに先立って発表された「ストレス脆弱性」モデルです。
1)「ストレス脆弱性」モデルの本質
統合失調症の病因論的仮説としてZubin,J.&Spring,B.によって1977年に提唱された「ストレス脆弱性」モデルは、先述のような「ストレス」概念の性格から、いわばコンピュータの基本OSのようなもので、その上でさまざまなソフトウェア(これが「疾患」に相当するでしょう)を走らせることができます(実のところ、その適用可能範囲は精神疾患に留まりません。糖尿病などの生活習慣病はもとより、感染症や悪性新生物(癌)にまでも、こうしたモデルを当て嵌めることが可能なのです)。
このモデルは精神疾患に関しては、まず遺伝的要因と胎生期~周産期の合併症による脳へのダメージとを含み込み、次に乳幼児期~児童期の養育環境の問題をも吸収し、最後に疾患発症の引鉄となる生活上の出来事(ライフ・イヴェント)をも考慮に入れる、まさに生物‐心理‐社会‐生態学的な包括的モデルです。つまり、このモデルに於ける「ストレス脆弱性」は、先天的な中枢神経発達障碍の可能性をも含み込んだ「高機能発達障碍」にも、乳幼児期(場合によっては胎生期にまで遡る)に於ける「原(心的)外傷~複雑型PTSD」にも、共に開かれているわけです。そして、このモデルに於いては、「精神疾患」として結実する一つの臨床像は、さまざまな要因が立体的複合的に関与した一つの「歴史的構造物」だということになります(1980年に登場したDSM-Ⅲの多軸診断システムもこうした発想に沿ったものでしょう)。
2)「ストレス脆弱性」モデルの射程
こうした特性の為に、このモデルは、従来の「内因性」「外因性」「心因性」という古典的三分類はもとより、「精神病」「ボーダーライン(パーソナリティ障碍)」「神経症」という三分類、更には近年の「発達障碍」と「ストレス~トラウマ(心的外傷)~PTSD」の間の垣根をも取り払ってしまいました。
このモデルの登場によって、生物学的探究もその位置づけがそれまでとは大きく変わらざるを得なくなりました。つまりその意義が、精神疾患の「原因」解明ではなく、「外的条件(ストレス状況)と内的条件(脆弱性)との相互作用」の生物学的記述へと変化することとなったのです。
勿論、精神医学の専門家の中にも今尚たとえば、
「自閉性障碍(広汎性発達障碍)と統合失調症やスキゾイド~スキゾタイパル・パーソナリティ障碍(或いはAD/HDと統合失調感情障碍(非定型精神病)や境界パーソナリティ障碍)をどう鑑別するか」、
即ち
「高機能発達障碍と、精神病やボーダーライン(パーソナリティ障碍)といった伝統的精神疾患とをどう鑑別するか」
という方向に問いを立てておられる方々もおられます。しかし、むしろ今は全てをまとめて、たとえば「ストレス脆弱性スペクトラム」と言ってしまう方が現実に即しているように思われます(⇒宜しければ本HPの『統合失調症の三重外傷モデル』の「新しい分類の試み」もご参照ください)。
ここに来て、クレペリンが構想した「疾患単位の確立」という企ては、完全に破綻したと言えるでしょう。
[補足]薬効の謎
「高機能発達障碍と、精神病やボーダーラインといった伝統的精神疾患とは、全く別の臨床実体で、相互排他的/並列的に扱われるべきだ」という主張に有力な根拠を与えていると思われる臨床経験に、薬効の違いが挙げられます。つまり、少なからぬ専門家達によって報告されています「統合失調症に有効な抗精神病薬が、高機能発達障碍の統合失調症様症状には殆ど或いは全く無効だ」という経験です。
この経験が概ね真実であるとして、これは本当に両者の独立性を主張する根拠であり得るのでしょうか。
そもそも、ある薬剤が「有効である」というのは、実はとてもアバウトな判定です。つまり、プラセボ(偽薬:治験=臨床試験に於いて実薬と区別がつかないようにして与えられる、薬効の無い見せかけのもの)よりも統計的に有意に「有効」であればよいのです。しかも、特に精神科領域の場合、客観的指標が乏しいために、その「有効性」は多くの場合、アンケート形式で調査された被験者や治験実施者の主観的な印象判断に基いています。筆者の昔の体験からも、その判断はとてもとても曖昧なものです。かつて多くの「脳代謝賦活剤」が「有効」と判定されて市場(医療現場)に出回り、恐らく膨大な医療費が使われましたが、その後大半の薬物が「無効」とされ消えて行った、という笑えない歴史的事実も存在します。
そのようにして判定されても、実際のところ、抗精神病薬のみならず抗鬱薬、抗不安薬等、何れをとっても、プラセボが「有効」4割(!)程度のところを実薬は「有効」6割かせいぜい7割程度のことが多いように思われます(面白いことに、統計的有意差は、母数が大きくなればなるほど、僅かな差でも「有り」と出ます)。そうだとすれば、元々残りの3,4割は「無効」だということです。
周知の如く、高機能発達障碍が注目されるようになったのは比較的最近のことです。それまでは勿論、その後でさえも少なからぬ「高機能発達障碍の統合失調症様症状」が統合失調症と見做されている筈です。よく言われますように「発達史を十分に確認しなければ、正しく発達障碍だと診断できない」のであれば、横断的状態像だけでは鑑別できない、ということなのですから。
以上のことを踏まえますとやはり、そもそも「統合失調症」と見做されてきた一群の中には最初から発達障碍ベースの統合失調症様反応も含まれており、それらには抗精神病薬が効き難いのだ、と考える方が合理的だと思われるのです。因みに、「新しい分類の試み」で紹介しましたクレペリンの歴史的記述も、この考えを支持していると思われます。
3)臨床的関わりから見た「ストレス脆弱性」
では、「ストレス脆弱性」そのものの本質は何でしょう。
多くの患者さん達と関わって来て見えて来るのは、愛着形成の問題と、それと表裏をなしている自己形成の問題です(⇒『高機能発達障碍論』)。つまり、さまざまな程度と様態の「愛着形成不全=自己形成不全」が存在し、それこそが、ライフサイクル上のさまざまなストレスへの脆弱性をもたらすのです。
ですから、「ストレス脆弱性スペクトラム」は即ち「愛着形成不全/自己形成不全スペクトラム」である、ということになります。
|
4.「精神疾患/精神障碍」再定式化の試み
「高機能発達障碍」を念頭に置いて眺めて見ますと、これまで多用されていた伝統的精神疾患概念である「統合失調症」「統合失調感情障碍(非定型精神病)」「パーソナリティ障碍(ボーダーライン)」等と診断されている事例の内に、実は、「自閉性障碍」や「AD/HD」が少なからず認められます。そういう場合、現時点では「誤診」とする議論が優勢です。しかし、それは決して「誤診」や「無知」によるものではなく、伝統的精神疾患概念そのものが問われているのだ、と筆者には思われます。
ここで上述のように「ストレス脆弱性」を一旦「ストレス脆弱性スペクトラム」或いは「愛着形成不全/自己形成不全スペクトラム」という捉え方にまで自由度を拡げた上で、再度(あくまでも筆者の臨床的印象で、ですが)、様々な「精神疾患/精神障碍」を定式化しなおしてみましょう。そうすると概ね次のようになります。
1)「ストレス脆弱性」の構成:さまざまな「愛着形成不全/自己形成不全」
まず、狭義の「精神疾患/精神障碍」としての「精神病」のベースとなり得る「ストレス脆弱性」の中味について見ておきましょう。尚、以下はかなり強引なカテゴリィ化だとは思われますが、分類せずに考察することは不可能ですので、已むを得ません。
①精神遅滞圏:先天的要因(遺伝的かつ/または母胎環境的発達制限要因)の存在がかなり疑われ、言葉の発達の遅れをはじめとした知的能力全般の遅れを示すが、人間対象への自然な興味関心や同一化は必ずしも障碍されるとは限らず、自然な幼児的愛着や交流を認めることも多い。但し、後年「精神病的破綻」に至るケースでは、既に自然な愛着や交流は損なわれているかも知れない。
②高機能自閉スペクトラム症圏:先天的要因(遺伝的かつ/または母胎環境的発達制限要因)の存在がある程度疑われ、人間対象への自然な興味関心や同一化が発展し難く、その影響もあって出生後の養育環境との不協和も生じ易い。問題は遅くとも、集団の中に置かれる幼稚園~小学校に於いて顕在化する。
[補足1]二次性PDD?
発達障碍の臨床と研究の両面で先導的に活動されています児童精神科医の杉山登志郎氏は、反応性愛着障碍の抑制型が広汎性発達障碍(PDD)と酷似していることを指摘した上で、反応性愛着障碍では、治療しつつフォローすると対人関係に劇的な改善が見られる、と述べておられます(『発達障害の子どもたち』151-152頁)。
この事は逆に見れば、養育環境側の問題による反応性愛着障碍が治療を受けられないまま放置された場合、二次性にPDDを呈し得る、と言っていることにならないでしょうか。
③AD/HD圏:先天的要因はあるかも知れないが、特異的決定的なものではなく、恐らくは主として乳幼児期の養育環境側の共感不全と過剰な知覚刺激への暴露(或いは慢性化した睡眠不足)に由来する。多くは小学校状況に於いて、不注意、落ち着きの無さ、ルールに従えないこと、等により顕在化する。不注意や問題行動によりしばしば周囲からマイナスの評価を受け、その為に一層の安全感欠如に至り、更に落ち着きを欠く、という悪循環に陥る。また、この悪循環により自己を肯定的に受容することや自尊心を持つことが妨げられ、ある種のパーソナリティ障碍へと発展することもある。
[補足2]「一次性AD/HD」と「二次性AD/HD」
先の杉山登志郎氏は、本来のAH/HDの他に、虐待によるAD/HD様症状があることも指摘しておられます。AD/HDが虐待を誘発し易い、という事情とは別に、です。その上で、両者の違いにまで触れておられます(『発達障害の子どもたち』159-160頁)。
同氏によれば、虐待によるAD/HA様症状では、
①症状に日内変動が大きいこと(鬱病のように夕方~夜にテンションが上がる)、
②対人関係が単純率直ではない、そして
③困難に直面すると朦朧となったり記憶がとぶ等の解離症状が見られる、
といった点で、本来のAD/HDとは異なり、薬剤反応性も異なる(本来のAH/HDでは覚醒剤系の中枢神経刺激剤が第一選択であるのに対して、虐待由来のAH/HD様症状では中枢神経刺激剤は無効で、少量のSSRIと非定型抗精神病薬のカクテルがしばしば有効)とのことです。
ここまできちんと指摘されますと、AD/HDを「本来のAH/HD」と「虐待由来のAH/HD様症状」とに論じ分けざるを得ないように思われます。杉山氏はAH/HDという概念をあくまでも「本来のAH/HD」に限定して用いておられますが、現時点で実際に両者を明確に区別しておられるのは恐らく同氏くらいのもので、一般には両者共に「AH/HD」と診断されているように思われます。故に、ここでは両者をそれぞれ「一次性AD/HD」と「二次性AD/HD」としておきましょう。そうしますと、上記の「AD/HD圏」というのは明白な虐待を想定したものではなく、「一次性AD/HD」に相当します。
明白な虐待に伴う臨床事態は、ここでの議論とは別に論じる必要があるようです(次項参照)。
④ボーダーライン圏:先天的要因は恐らく問題ではなく、主として乳幼児期の養育環境側の持続的反復的共感不全による「抱える自己」の形成不全と二者関係への固着に由来し、思春期青年期に顕在化する(⇒『ボーダーライン』)。
[補足3]明白な虐待と解離性障碍
今日の知見からは、幼少期に於ける明白な身体的かつ/または性的虐待が「解離」という現象をもたらすことは、ほぼ確実だと思われます。問題の所在から分類していますここでの議論に於きましては、解離性障碍や「二次性AD/HD」も概ねこの辺りに位置づけられるでしょう。
ボーダーラインにいつも解離症状が認められるわけではありませんが、合併していることも決して少なくはありません。そのことも、解離性障碍や「二次性AD/HD」をこの辺りに位置づけることを正当化しているでしょう。
⑤神経症圏~「正常」:乳幼児期や児童期に若干の固着点を有し、精神科的問題を呈さずに人生を全うする場合もあるが、思春期青年期或いは壮年期更年期に神経症症状や抑鬱症状を呈することもある。
以上のお話を思い切り簡略化して表にまとめますと次のようになります。
|
大 ← 「ストレス脆弱性」=「愛着/自己形成不全」 → 小 |
| \ ストレス
\脆弱性
構成要因\
のタイプ \ |
精神
遅滞圏 |
高機能自閉
スペクトラム圏 |
AD/HD圏 |
ボーダーライン圏 |
神経症圏
~「正常」 |
| 先天的要因 |
+ |
+ |
± |
- |
- |
| 周産期要因 |
± |
± |
± |
± |
- |
| 乳幼児期要因&課題 |
(顕在化) |
(顕在化) |
+ |
+ |
± |
| 児童期要因&課題 |
顕在化 |
顕在化 |
顕在化 |
± |
± |
| 思春期青年期課題 |
|
|
|
顕在化 |
(顕在化) |
| 壮年期退行期課題 |
|
|
|
|
(顕在化) |
| 主な対象関係機能水準 |
不定 |
1.5者 |
1.5者~2者 |
(1.5者~)
2者(~2.5者) |
(2者←)2.5者~3者 |
(註1)この表は「表」としてどうしても平面的でディジタルな表現になっていますが、実際には各タイプがもっと立体的に関連していて(次註参照)、しかもアナログな(つまり連続的に移行する)ものだと思います。
(註2)例えば「自閉スペクトラム症」をベースに「ボーダーライン」や「神経症」が生じ得るように、この表の「ストレス脆弱性」の各タイプは理念的カテゴリィに過ぎず、現実には重複することも大いにあり得ます。それが、「各タイプが立体的に関連している」ということです。
(註3)この表及びこのHPで使用しています1者、1.5者、2者、2.5者、3者というのは余り一般的な術語ではありません。筆者は概ね次表にまとめたような意味で使用しています。
| 関係性 \ 本HPでの意味内容 |
| 1者水準 |
対象が生ずる以前の原体験世界 |
| 1.5者水準 |
物的対象(移行対象(1))との関係世界 |
| 2者水準 |
母子の共生関係を祖形とする排他的2者関係(自己対象(2)関係)の世界 |
| 2.5者水準 |
対人葛藤が物的対象や身体領域に置き換えられている世界 |
| 3者水準 |
公的一般的秩序が排他的2者関係に優越する世界 |
(1)「移行対象」:英国の精神分析家で小児科医のウィニコットWinnicott,D.W.の提出した概念。外界の対象でありながら、子供が自分の万能的な愛の創造物であるかのように認識している対象(母親の乳房やお気に入りの縫い包(ぐる)み、等)。この子供の認識は大人の見方からすれば勿論「錯覚」なのですが、子供の健康な発達の為には、その対象の帰属(外界の存在物か子供の愛による創造物か)は決して問われるべきではないとされています。
(2)「自己対象」:米国の精神分析家で自己心理学の創始者ハインツ・コフートKohut,H.の提出した概念。その基点は、自己を喚起しまとまりを与え維持し力づける(母親的)人間対象のこと。しかし、その後この「自己対象」概念は推敲されて、その主観的側面の重要性が再認識されて「自己対象体験」と捉え直され、それと同時に拡張されて、具体的な被養育体験からコミュニティや社会に於ける役割評価、更には種々の文化芸術に触れることに至るまで、自己にまとまりを回復させ力づけることであれば、あらゆる体験がそれであり得ると考えられるようになっています。従って、これを日常の言葉で言い換えると、「こころの支え」の体験と言えるでしょう。そして、それらは「自己対象体験」の発達ラインを構成している、とされています。
2)「精神病/統合失調症」の再定式化
上記のように、「精神病」のベースとなる「ストレス脆弱性」(=「愛着形成不全/自己形成不全」)の候補には実に様々なものが考えられますが、これらのベース(「ストレス脆弱性」)のどれの上にも、然るべき精神的負荷(ストレス)が降り掛かることによって、1者水準(原体験心性)ないしその近傍への退行(或いは、このサイトの「理解モデル」で言えば「心の鎧/自我」の機能麻痺に伴う原体験心性の表在化)が生じ得ます。そしてそれこそが、これまでに精神科臨床で出会われていた「統合失調症」をはじめとする「精神病」であると言えます(⇒「統合失調症の新しい分類の試み」)。
このような観点に立つ時、その病像はベースとなっている「ストレス脆弱性」(=「愛着形成不全/自己形成不全」)と、そこに加わった精神的負荷の性質や強度、持続期間などによって決定され、経過は主にベース(「ストレス脆弱性」=「愛着形成不全/自己形成不全」)の性質と治療的関与及び福祉的関与(ケースワーク)、更には社会的認知受容の関数であると考えられます。
このように考えますと、古くから「単一精神病」説が根強い支持を集めている事情をも、無理なく理解することができるでしょうし、マンフレート・ブロイラーがまとめた「統合失調症の経過」が恐ろしく多岐に亘る(実に様々な経過パターンが存在する)こともまた、全く当然のこととして理解できましょう。
つまり、「1者水準(原体験心性)ないしその近傍への退行(「心の鎧/自我」の機能麻痺に伴う原体験心性の表在化)」という点では「精神病」はただ一つの事態なのですが、それが様々な「ストレス脆弱性」というベースの上に生ずる為に、そして発症の契機となった様々な事情や様々な治療的関与などがある為に、実に様々な病状や経過が齎されるわけです。
また、精神病状態(昏迷状態や錯乱状態或いは幻覚妄想状態)からの回復後は少なからぬ事例で、伝統的に「人格水準の低下」と呼ばれている、高機能自閉スペクトラム症に極めてよく似た状態を呈します。これも、高機能自閉スペクトラム症との異同を云々するよりも、実際に高機能自閉スペクトラム症的な1.5者水準での防衛的適応であると考えてしまう方が自然であると思われます。
(註)このHPで提出しています「統合失調症の三重外傷モデル」で想定している「統合失調症」は、ここでは概ね、高機能自閉スペクトラム症圏の一部、AD/HD圏及びボーダーライン圏の「ストレス脆弱性」=「愛着/自己形成不全」の上に生じた精神病状態だ、ということになります。
[補足]「ネオ・グリージンガリズム」
ヴィルヘルム・グリージンガー(Wilhelm Griesinger:1817-1868)という人は、19世紀半ばに活躍した精神医学者です。「全ての精神病は脳病である」というテーゼが有名ですが、それは主に、「精神病」を宗教や哲学的心理学から開放し、科学的な究明の対象としようという意図に基づいていたようです。『はじめに』の「精神医学史概説」でも触れましたように、彼は実際のところ、今日の観点から見ても決しておかしくない主張を展開していました。
精神病の生物学的研究はネオ・クレペリニズムの旗の下に進められてきましたが、その最新の成果(殊に遺伝子やエピジェネティクス研究)からも、統合失調症と双極性感情障碍(躁鬱病)が、当のクレペリンが構想したような個別の実体とは言えなくなってきたことから、今度は「単一精神病」説の立場だったグリージンガーを称揚し、ネオ・グリージンガリズムを唱えておられる学者もおられます。
筆者は別段そのことに異を唱える者ではありませんが、実に150年を経てグリージンガーに回帰するとすれば少なくとも、精神医学の最重要課題である機能性精神病の本質に関する理解は、この150年余の間に殆ど進んでいなかった、ということになりはしないでしょうか。素直に喜べない状況です (-_-;)
(この部分2012.01.15に追記)
|
5.「経過」について
―「悲哀反応/適応障碍/薬物依存症治療」からのヒント―
先に[経過は主にベース(「ストレス脆弱性」=「愛着/自己形成不全」)の性質と治療的関与及び福祉的関与(ケースワーク)、更には社会的認知受容の関数である]と書きましたが、それでも一般的な経過を想定することは、ある程度は可能でしょう。
この問題には、「悲哀反応/喪の作業」の研究、「不登校」で特によく観察されてきた適応障碍のパターン、及び薬物依存(特に覚醒剤)の治療経過モデルから接近することができます。
これら三者を並べて、精神病(特に初回エピソード)の経過と比較し易くしたのが下の表です。
| 悲哀反応 |
不登校 |
覚醒剤依存 |
精神病 |
経過モデル |
|
|
心気的時期 |
乱用期 |
前駆期 |
準備段階 |
起 |
| ショック |
攻撃的時期
(家庭内
暴力) |
幻覚妄想状態 |
発症 |
混乱期
(現実との
格闘) |
承 |
| 否認 |
受診/断薬
症状消退 |
受診/初期治療
急性期症状消退 |
怒り
取引 |
刺激期
薬物渇望期 |
中核的治療期 |
| 抑鬱 |
内閉的時期 |
|
精神病後
抑鬱 |
抑鬱
(現実の受容) |
転 |
| 受容/再起 |
再適応 |
再起 |
再適応 |
再起 |
結 |
このように並べて見ますと、勿論「症状」に違いはあるものの、前半の準備段階から混乱期を経て終盤の抑鬱、再起に至る流れは概ね共通していることが見て取れます。まさに「起」「承」「転」「結」ではないでしょうか(これは、《一つの閉じて安定しているシステムに外部から何らかの入力が加わって、次の安定した状態に至るまでのプロセス》として、身体疾患はもとより、あらゆる事態に共通するパターンだと言えるかも知れません)。
精神疾患の場合にこの流れは、精神分析クライン派のポジション論を参照すれば、至極当然の事として理解できます。即ち、病初は受容困難な現実に直面して「妄想-分裂ポジション」paranoid-schizoid positionに伴う原始防衛機制で応じる為に少なからぬ混乱を生じているのですが、徐々に「抑鬱ポジション」depressive positionというより現実受容的な態勢に変化し、最終的に現実への再適応を果たす、というシナリオです。
ここでもう少し詳細に見てみますと、「起」に関してこれらの間に違いがあるのは当然として、問題は、各事象間での「承」(つまり「妄想-分裂ポジション」)の様態の違いでしょう。悲哀反応では《ショック→否認→怒り→取引》となるところが不登校では《心気的時期→攻撃的時期(家庭内暴力)》、覚醒剤依存では《乱用期→幻覚妄想状態→断薬による症状消退→刺激期(薬物渇望期)》となり、精神病初回エピソードでは《前駆期→発症(幻覚妄想状態)→初期治療による症状消退→中核的治療期》となっています。
これを見ますと、悲哀反応と不登校は概ね様態が共通していますが、恐らくは通常の脳機能の範囲内の出来事だからなのでしょう。それに対して、覚醒剤依存と精神病は共に幻覚妄想状態を来たすだけでなく、症状消退後いち早く「もう大丈夫です!」と主張することなども非常によく似ています。この二者では過剰覚醒に伴うドーパミン系ニューロンの過剰活動等で共通点がありそうです。 |
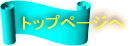 
|