2002年、
schizophrenia の訳語が
長年使用されていた「精神分裂病」から
「統合失調症」へと変更されました(その経緯はここにあります)。
この術語の変更が本当に社会的疎外を払拭するか否かは
現時点ではまだ不透明ですが、
術語が持つ拘束力を
軽視すべきではないでしょう[下註]。
そこでここに、少々気になる術語を
原語/日本語訳にこだわらずに取り上げ
若干の考察を加えてみることにしました。
[註] 2018年7月1日現在、訳語の変更は見事に奏功したように見えます。これには、いわゆる非定型抗精神病薬の販売促進キャンペーン(曰く「統合失調症は薬で格段に良くなります」的な)の与るところも大なのでしょうが、やはり「精神分裂病」が背負っていた負の遺産から解き放たれたことも大きかったのでしょう。(2018.07.01)
ちなみに、
「対人恐怖/社交恐怖」を意味する“social phobia”の「社会恐怖」、
「非行」を意味する“conduct disorder”の「行為障碍」などという
迷訳につきましては、いちいち取り上げませんでした。
⇒最新の追加 |
【attachment】
これは長らく「愛着」と訳されてきました。日常言語としては全く正しい訳語です。では、何が問題かと言えば、「愛着(形成)」をジョン・ボウルビィらが「子供が養育者を安全基地として利用できるようになること」と再定義しているからです。そして、この定義に基づいた「愛着」が、この業界の術語として定着しました。
ボウルビィらの再定義は、彼らの方法論の柱である客観的な行動科学的研究には役立つものだと思いますが、その為に英語のattachmenntや日本語の「愛着」が本来持っている主観的な側面(「愛情によってくっついている」という感覚)がきれいに捨象されています。
そして、困ったことに、専門家ほど術語化した意味を重視しますので、今や私達は「愛着」という言葉をボウルビィらが再定義する以前の、もっと情緒的な厚みのある日常の言葉として使えなくなってしまっています。うっかり日常語の意味で使うと「間違っている」と言われてしまうのです。
しかし、これでは本末転倒です。日常語の持つ豊かでそれ故曖昧でもある意味内容を明確にすることは重要ですが、その為にその語が持つ豊かさを削ってしまっては、まさに「角を矯めて牛を殺す」ようなものです。
臨床に於いて扱うのは、ボウルビィらが捨象してしまった主観的な世界に於ける傷つきです。
ではどうすればいいのか?
あまりいい方法ではありませんが、術語化している方の「愛着」をせめて「ボウルビィの愛着」と限定語つきで使うべきでしょう。
(2018.07.01)
|
【autism】
“auto-”は「自(の)」、“-ism”は「主義/状態」で、“autism(英語)/Autismus(独語)”は従来「自閉/自閉症」と訳されてきました。この言葉を最初に用いたオイゲン・ブロイラー(1911)は、次のように述べています。
―もはや外界との交流の全く無くなった最も重症な分裂病者(統合失調症患者:引用者註)は自己のためだけの世界に生きている。彼らは叶えられたと思っている願望や迫害されているという苦悩を携えて繭の中に閉じこもるように自己の内に閉じこもり、外界との接触をできる限り制限している。内面生活の相対的、絶対的優位を伴う現実からの遊離のことを我々は自閉Autismusと呼ぶのである。(邦訳『早発性痴呆または精神分裂病群』医学書院,1974,73頁,下線部強調は引用者)
―我々の比較的重症な入院患者は、大部分彼らのコンプレクスにとって重要でないような病院の出来事を正しく理解し、それを心にとめておくことができる。(同書73頁の注;いわゆる「二重見当識」)
他方でこの術語は、レオ・カナーやハンス・アスペルガーによって採用されて以来、今日の「自閉症スペクトラム障碍」に至るまで、通常は幼児期に気づかれます社会的相互性やコミュニケーションの障碍と強いこだわりという特性に対しても使用されています。
確かに筆者の経験でも、長期に亘って精神科病院に入院されてきた慢性統合失調症と言われるような方々が示される言動と、思春期青年期の「自閉スペクトラム症」と診断される方々の言動とは、区別し難いように思われることがしばしばあります。その意味で、両者に同じ術語を使用することは正当化されそうです。ドイツの児童青年精神科医ラインハルト・レンプも「自分自身を見る能力」の障碍という点に於ける両者の共通性を指摘しています。
しかし、レンプも指摘していますように、一旦「他者」との世界が獲得された上で言わば退行し自閉症様状態を呈していると思われる「慢性統合失調症」患者と、どうも「他者」との世界が未だ十全には獲得されていないように見える「自閉スペクトラム症」者とでは、当然違いも存在します。これにもいろいろ議論はあるでしょうが、筆者が多く出会いました思春期以降の「自閉スペクトラム症」の方々の特徴は、筆者には、主体としての自己を極端に欠いた「ウルトラ・アウェイ」だと思われました(下註)
(註)ultraは英語の発音では[  ltr ltr ](≒アルトラ)でしょうが、日本語では「ウルトラ」の方が分かり易いと思いますので、ここではそうしておきます。術語「アウェイ」につきましてはこちらを参照して下さい)。 ](≒アルトラ)でしょうが、日本語では「ウルトラ」の方が分かり易いと思いますので、ここではそうしておきます。術語「アウェイ」につきましてはこちらを参照して下さい)。
先のレンプの議論に於ける「自分自身を見る能力」は即ち「観察自我の働き」ですが、それは直接的実在体験を間接化する働きであり、述語的状況性に呑み込まれた状態から相対的に自由な、主語的「主体」を獲得する働きだとも言えます(この時、同時に主語的「他者」も獲得されます)。従って、「自分自身を見る能力」の障碍は即ち「主体」形成の障碍でもあります(下註)。
(註)実は、ユング派分析家の河合俊雄氏にも、広汎性発達障碍(≒自閉スペクトラム症)は「主体の欠如」と考えられる、という指摘があります(『発達障碍への心理療法的アプローチ』創元社,第1章の五~六)。
このように、社会的相互性やコミュニケーションの障碍と強いこだわりを「主体(主語的自己と主語的他者)の獲得不全/ウルトラ・アウェイ」と捉える時、“autism”「自閉症」という術語はちょっと違うと言わざるを得ません。
[補足](2018.07.01)
筆者の記憶が正しければ、神田橋條治氏が「自閉ではなく自開だ」とどこかで述べておられたように思います。
自他の区別の成立以前の体験様式は、自他の区別の成立以後の「他の有る自」ではなく「他の無い自」言わば「原自」ですが、それも広く「自」と考えれば、それは「他」即ち「非自」を持たないのですから同時に「世界全体」でもあるので、まさに世界に開けています。
つまり、当事者の側から見れば、生じているのは「自開」という事態であり、周囲の側の目にはそれが「自閉」に映る、ということです。 |
【borderline】
精神科領域で“borderline”と言いますと、主に二つの場合があります。
一つは知能の「境界域」即ち、知的障碍と正常知能の間の知能のことです。
そしてもう一つは「境界例」で、広義には今日の「パーソナリティ障碍」の全体を、狭義にはその中でも「情緒不安定パーソナリティ障碍」、或いは更にその中の「境界パーソナリティ障碍」を指します。
ここでは、後者の意味での「境界例/ボーダーライン・ケース」を取り上げます。
「境界例/ボーダーライン・ケース」というのは、元々は「神経症だと思って精神分析的治療を始めたら一過性の幻覚妄想等の精神病症状を呈したり酷(ひど)い行動化(アクティング・アウト:多くは自己破壊的行為)をきたしたりする、精神病と神経症の間(境界/ボーダーライン)に位置する病態」という意味でした。
しかし、この術語が使われ始めたアメリカでいつの間にか、「境界例」という言葉が「精神科臨床に於ける厄介者」というような意味を帯びるようになった為に、なるべく「境界」という言葉を当てる対象を限定しようとしたように見受けられます。
日本でも、「境界例」という言葉は一部で「ボーダー」と略されて、アメリカに於いてと同様、「精神科臨床に於ける厄介者」を意味してはいましたが、「パーソナリティ障碍」という言葉が輸入され、それが「人格障害」と訳される為に、むしろこちらの方が「人格の劣った者」という極めてネガティヴなニュアンスを帯びてしまったようです。
しかも、「パーソナリティ/人格」は変わらない、故に治療の対象ではない、というシンプルな論理が、精神科臨床に於いてさえ、罷(まか)り通るようになってしまいました。
しかし、筆者は最近、この「境界例/ボーダーライン・ケース」という言葉はもっとポジティヴに評価すべき言葉だと思うようになりました。
何故なら、ボーダーラインの患者さん達はまさしく旧来の様々なボーダーを破壊して新しい在り方をもたらす存在だからです。ボーダーラインの患者さん達のお蔭で、精神病と非精神病の断絶も、精神医療と社会との垣根も、患者と医師との権力的関係も、全てが改変され、恐らく改善しました。
私達は、ボーダーラインの患者さん達のこのような功績に敬意を表し忘れないようにする為に、「境界例」という言葉をもっとポジティヴに評価し、積極的に使用すべきではないでしょうか。 |
【developmental disorder/発達障碍(発達症)】
「発達障碍」という術語は2014年現在、医療や教育、福祉の領域で既に定着した感があります。しかし、この術語もまた、大きな矛盾を含んでいると思います。
元々は、先天的な中枢神経系の発達異常が想定された上での術語でした。その意味で、アメリカ精神医学会の診断統計マニュアルの最新版DSM-5が、わざわざ「神経発達症」neurodevelopmental disorderとしているのは正しい変更だと思われます。
但し、そうすると、従来の「統合失調症」研究で指摘されている病前の脳の状態もまさに「神経発達障碍」です。
また、最近のエピジェネティクスの知見に拠れば、どの遺伝情報が使われるかということには環境も影響すると言います。学習に伴う脳の可塑性も考えると、純粋な「先天性」というものは空論なのかも知れません。
更に、虐待の被害を「第4の発達障碍」と見做し得る、という杉山登志郎氏の議論もあります。そうだとすると「発達障碍」というカテゴリィは「持続性反復性トラウマによる複雑性PTSD(発達外傷性障碍)」とも接続します。そしてこれはしばしば、解離性障碍をはじめとする神経症やボーダーライン、場合によっては精神病をももたらします。
このように見ていくと、脳炎や頭部外傷などの後遺症(「高次脳機能障碍」等の脳器質性障碍)を除く大半の精神障碍は「発達症」の上に成り立っている、とも言えます。
そうなると、これはもう一つの診断カテゴリィではなくなってしまうのです。 |
【disorder】
国際的に影響力の大きなアメリカ精神医学会発行の『精神疾患の診断分類マニュアル』第4版(DSM‐Ⅳ)は、精神疾患を表すのに“disorder”という単語を用い、これが日本語では一律に「障碍」と訳されています。ここには二つの不思議が存在します。
①“disorder”と“illness”,“disease”
一つは、アメリカを初め国際的に何故“disorder”という術語が採用されたのか、という点です。「疾患/病気」という意味では“illness”や“disease”という単語も存在し、「精神疾患」は一般に“mental illness”,“mental disease”とも表記されます。例えば「躁鬱病」は英語で“manic depressive illness”でしたが、これが現在、「気分障碍/感情障碍」“mood disorders/affective disorders”の中の「双極性障碍」“bipolar disorders”となります。
この事に関しては、ICD-10(WHOの国際疾患分類第10版)序論の「用語上の問題点」の1に、[disease(疾患)やillness(疾病)という用語を使用する際に生ずる本質的で重大な問題を避ける為]と記され、[disorderは決して正確な用語とは言えない]とも記されています。
名詞としての“disorder”は、「整った秩序」という意味から「常態,健康な状態」という意味の“order”に否定の接頭語“dis-”「非…,無…」がくっついて、辞書的には
[1] 混乱, 乱雑. 混乱, 乱雑. |
[2] 無秩序; 無秩序;  騒動, 暴動. 騒動, 暴動. |
[3] (心身の)不調,(軽い)病気. (心身の)不調,(軽い)病気. |
 ・ ・ |
mental ~ 精神病. |
[ 新グローバル英和辞典 提供:三省堂 ] |
|
を意味しています。
他方、“illness”は“well”の反意語である“ill”の名詞形で、一般に「良好でないこと=不健康,病気」を意味しています。“disease”は、“ease”「安楽なこと」に否定の接頭語“dis-”「非…,無…」がくっついて、「安楽でないこと=病気」という意味になります。
これらを見比べてみますと、“illness”は本人の感じる良好さ、“disease”は本人の感じる安楽さが基準であるのに対して、“disorder”の方は外から見た秩序が基準となっているようにも思われます。先に触れましたICD-10序論にあります「disease(疾患)やillness(疾病)という用語を使用する際に生ずる本質的で重大な問題」というのが、「所詮、精神疾患とは社会的に規定されるものであって、生物学的に同定し得る実体としての病気など存在しないのかも知れない」という議論を指しているのだとすれば、この“disorder”の使用はむしろ妥当なものなのでしょうが…
②「疾患(病気)」と「障碍」
二つ目の不思議は、“disorder”の訳語に「障碍」が選ばれたことです。
実は「障碍」という日本語は、個人の特質としての機能障碍(impairment)、そのために生ずる制約としての能力低下(disability)、その社会的結果である社会的不利(handicaps)を包括する概念[ 大辞林 提供:三省堂 ] で、次のように実に多くの英単語が対応しています。。
・a impediment [defect](欠陥)
・a impairment(機能障碍)
・a disability(能力低下)
・a handicap(社会的不利); a disorder
“disorder”は確かにこれら「障碍」を意味する語群に含まれてはいますが、そのせいかこの「精神疾患」を表す筈の語が「障碍」と訳されたことで、「精神疾患」概念と本来の「障碍」概念の間に無用の混乱が持ち込まれているようにも思われます。
いっそのこと“disorder”の日本語訳を「~病」または「~失調」としてしまってはどうでしょう。そうすると、例えば「パニック障碍」は「パニック病」、「摂食障碍」は「摂食失調」、「パーソナリティ障碍」は「パーソナリティ失調」となり、そんなに違和感は無いのではないでしょうか。
そうして、例えばそれらの「病/失調」が5年以上続けば自動的に「障碍」として認める、というようにでもすれば、精神科の臨床現場に於ける「病(疾患)」と「障碍」の無用な混乱も避けることができるように思われるのですが…
[補足]「障害」と「障碍」と「障がい」
近年、「障害」という語に含まれる「害」という字の印象が当事者を傷つけかねない為に、「がい」と平仮名で表記することが公的にも是とされています。筆者は、漢語を平仮名書きにすることには少々抵抗を覚えますので、本サイトでは以後、原則として「障碍」と表記しています。 |
【Durcharbeiten(独)】
フロイトが提出したこのドイツ語(英訳はworking through)は従来より「徹底操作」と訳されていますが、この場合の「操作」は、解釈を与えられたクライエント(被分析者:精神分析を受けている人)が、自らの内界に於いて抵抗と戦いつつ、解釈を吟味し受け入れていく過程を指しています。しかし「操作」と言うと、人が他者を(分析家が被分析者を)操作する、と誤解されかねないので、訳語の変更の提案も以前から有りました。
mourning workが「喪の作業」と訳されていることを考えますと、これも「徹底作業」の方が良いように思われます。これだと、誤解したとしてもせいぜい「分析家と被分析者との共同作業だ」という程度でしょうし、「共同作業」というのもあながち間違いではないでしょうから。
因みに、この「徹底作業」が必要であることを見出したフロイトはさすがだと思います。解釈を与えてもクライエントが変わらなければ「この解釈は無効だ、間違っているのだ」と考えても良さそうなものですが、彼は(自分の解釈の正しさによほど確信が有ったのか)そこで引き下がらずに、指摘を繰り返しながら変化を待ったのですから。
解釈を理性で正しいと知的に理解しても人はすぐには変わらない、というこの事実は、無意識/エス(このサイトでは「原体験心性」)の保守性(「馴染みの法則」)に基いています。筆者は最近、この「馴染みの法則」が治療的にも大いに役立っていることを再認識しています。
この「馴染みの法則」を活用していることでまず思い浮かぶのは、少しずつ望ましい行動を含む新しい状況に慣れさせていく「行動療法」でしょう。しかし、精神分析もまた「徹底作業を経て解釈を受け入れることで生じた新たな認識が馴染みの状況となることで以後の患者を支配して行く」ということ無しに治療は不可能であり、そう考えるとあらゆる治療的働き掛けが「馴染みの法則」を当てにしているのです。
「馴染みの法則」は実に強力で偉大です (^_^;) |
【good enough mother】
これは、フロイト以降もっとも重要な精神分析家の一人、ドナルド・ウィニコットWinnicott,D.W.(1896-1971)の重要な術語の一つです。当初「十分に良い母親」とされていましたが、それだと「100%良い母親」という意味に誤解されかねない、ということで、やがて「ほど良い母親」と修正されました。筆者も長年この「ほど良い母親」に馴染んできましたが、最近この修正でも不十分であることに思い至りました。
そもそも、最初の「十分に良い母親」の「十分」という日本語にも「100%」という意味の他に「まだ至らないところはあるがもうそれで十分だ」と言う場合の「不完全だが許容範囲」という意味があります。そして、後者の意味を生かせば、この訳語でもウィニコットの意図と合致しています。
現在広く使われてます「ほど良い母親」の「ほど」も、本来たとえば「ほどほどに」と言う時の「完璧を求めずに」というニュアンスを意図して採用されたものです。しかし、「ほど良い」という日本語はむしろ「至適」という意味で使われることが多いのではないでしょうか。good
enough motherが結果的に至適になることはあっても、現在進行形で至適であると言うのではウィニコットの意図に反してしまいます。
だとすれば、むしろ「許容範囲の母親」、これが硬ければ「まずまずの母親」「まあまあの母親」くらいの方が誤解が少ないかも知れません。
|
【hysteria/Hysterie/ヒステリィ】
これは、古代ギリシャ・ローマの時代に女性の精神変調に対して、それが子宮υστέρα (hystéra)が暴れることに由来すると考えられてつけられた病名で、メランコリィなどと共に西洋文化圏に於いて実に2千年もの歴史を持っていました。しかしそれが、アメリカ精神医学会発行の『精神疾患の診断分類マニュアル』第4版(DSM‐Ⅳ)やWHOの国際疾患分類第10版(ICD-10)では、恐らく以下に述べますような理由から、「解離性障碍」と「身体表現性障碍」、そして「演技性パーソナリティ障碍」(下記補足参照)を中心に幾つかの「パーソナリティ障碍」に解体されてしまっています。しかも「転換性障碍」がDSM-Ⅳでは「身体表現性障碍」に、ICD-10では「解離性障碍」に含まれる、という混乱ぶりです。
この病態は実際には男性にも見られ、「原因が子宮にある」というのはもちろん誤りでした。また、この病名が有名になり過ぎてか、日常会話に於いて女性の情緒不安定な様子を指して、少なからず侮蔑的に「ヒス(テリィ)」などと呼ぶようになってもいました。
ですから、「ヒステリィ」という病名の使用が好ましくないと言うのも分かるのですが、この病名を放棄することでこの病名と共に蓄積されてきた重要な臨床的洞察が失われてしまったこともまた否めないと思います。失われた重要な洞察として、筆者は次の二つを挙げたいと思います。
①「解離症状」「身体表現性(転換性)症状」「演技的自己愛的で排他的二者関係に親和的な傾向」の内的関連性への洞察
②「ヒステリィ精神病」という概念に示される、本来「神経症」水準とされる解離機制と精神病症状との連続性への洞察
結局のところ、全ての精神疾患が、当サイトで提示していますように、拡張版の複雑性PTSDとストレス脆弱性モデルで理解されるようになれば、その時にこそヒステリィという病名の歴史的使命は果たされ、本当に不要となるのでしょう。
[補足]「演技性パーソナリティ障碍」histrionic personality disorder
これもまた、患者さんに向かって説明しにくい診断名の一つです。英語のhistrionicも日本語の「演技性」も共に、明確な意図に基づく演技を連想させます。しかし、本当にそうであれば治療の対象となるでしょうか?
この概念のもととなったヒステリィ者の言動は、あくまでも無意識的なメカニズムに支配されていると考えられていました。だからこそ、当人の意識的努力の及ばない現象として、治療の対象とされたのです。
実際のところは、パーソナリティ障碍の項でも述べましたが、この水準の病態では、意識的(意図的)か無意識的か、というよりも「無自覚的」と表現した方が実情に近いと思います。 |
【Post-Traumatic Stress Disorder】
これは日本語ではほぼ例外無く、真ん中で区切って「(心的)外傷後ストレス障碍」と訳されています。しかし、案外この訳は自明ではないのではないでしょうか。
筆者は実は1995年、阪神淡路大震災やオウム真理教の地下鉄サリン事件などでようやくPTSDが注目され始めた頃、、現在は児童虐待やPTSDの専門家として知られているアメリカ帰りの某心理臨床家が、「外傷性ストレス後障碍」が正しいのではないか、と呟くのを聞いて、なるほどそうだ!と思っていました。ところが、何年経ってもそうは訂正されず、専ら「心的外傷後ストレス障碍」が流布して今日に至っています。
Post-Traumatic ▼ Stress Disorder:「(心的)外傷後ストレス障碍」
X
Post-Traumatic Stress ▼ Disorder:「外傷性ストレス後障碍」
この二つ、果たしてどちらが正しいのでしょうか?
Acute Stress Disorder(ASD)という診断名もあります。こちらは日本語でも「急性ストレス障碍」と訳されていて、急性の「ストレス障碍」とも「急性ストレス」による障碍とも取れるようになっていますが、DSM-Ⅳに於けるPTSDとASDの違いが、実はその持続期間(ASDが4週間以内、PTSDは1ヶ月以上)でしかないことを考えると、ASDは急性の「ストレス障碍」かも知れません。
他方、Traumatic Stress(外傷性ストレス)という術語が存在します。この術語を冠した学会も存在しますし、書名にもなっています。もしもTraumatic Stressが術語として確立しているのであれば、Post-Traumatic Stress Disorderも「Traumatic Stressの後(Post-)のDisorder」とする方に軍配が上がりそうなのですが… |
【sublimation】
これは通常「昇華」と訳されています。しかし、これは少なくとも筆者にとっては、一つの外国語をもう一つ別の外国語に訳したようなものでした。つまり語だけを聞いても、意味がさっぱり分からないのです。
他方で、この「昇華」というプロセスは、ある表現が芸術か猥褻かという議論に不可欠のようです。そうだとすればいっそ「妥協」か「偽装」と訳した方がしっくりくるように思ってしまいます。
|
【true self / false self】
これらは、かのウィニコットD.W.Winnicottの提出した術語ですが、とても平易な言葉で、その点ではフロイトS.FreudのIch(私→自我)やEs(それ/形式上の主語→エス)、Über-Ich(私を超えたもの→超自我)と同じです。
これらの概念に基づいた病態理解が非常に一般化できることは、本サイトでも述べているとおりです。通常それぞれ「本当の(真の)自己」と「偽りの自己」と訳されています。
しかし、これらの訳語には、このまま臨床で用いますと、「この自分じゃなくて、どこかに本当の自分が有る」とか「偽り?人を騙しているんだ」と誤解されるような響きがあるなぁ、と長年考えていました。そこでこれまでは、true
selfを「赤ん坊~子供の部分」ないし「在りのままの自分」、false selfを、悪く言えば「借り物の自分」、良く言えば「周囲の状況に適応する大人の部分」と表現してきました。
最近気づいたのは、true selfは「こころ(心情)」だ、ということです。ただ、true selfを「こころ(心情)」と捉えるのは良いと思うのですが、そうするとfalse selfをどう捉えればいいのか?それで思い至ったのは、false selfは「ことば(言語)」だ、ということです。
上述のように、フロイトは人間の精神構造に関して、エス・自我・超自我の3つの審級を導入しました。興味深いことに彼は、親イマーゴに由来する超自我はエディプス複合解消の産物としてエスに深く根ざしている、と指摘しています(「自我とエス」邦訳33頁,フロイト全集18,岩波書店,東京,2007)。
これに対して、true self/false selfという、ウィニコットの導入した2分構造はいかにもシンプルです。
フロイトは神経症者から得た臨床素材を基に、本当に精緻な議論を展開していますが、ウィニコットは幼児や精神病者から得た臨床素材から考察しています。この点に注目しますと、3分法と2分法の違いは、対象とした患者の病態水準の違いに因るのだろうとも思われます。
エス・自我・超自我の区分とは別にフロイトが最後まで保持していたものに、無意識・前意識・意識という区分が有ります。これも3分法ですが、前意識は本質的に意識と変わらないとされていますので、これは事実上の2分法です。しかも、無意識は事物表象のみで成り立っていて、言語表象と結びついて初めて意識の領域に入れるのだ、と述べているように、両者の区分は言語と深く関わっています。
true self/false selfというウィニコットの導入した2分構造が、むしろこの無意識/意識の2分法の延長上にあると考えれば、true self/false selfをこころ(心情)/ことば(言語)と言い換えることは、あながち間違ってはいないと思えてきました。 |
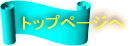 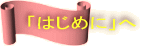
|